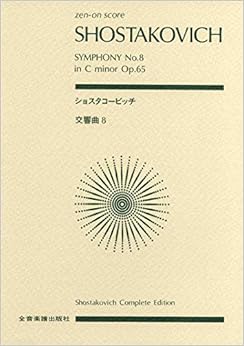ドミートリイ・ショスタコーヴィチ (Dmitri Shostakovich,1906-1975)作曲の交響曲第8番 ハ短調 Op.65 (Symphony No.8 c-moll)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。交響曲第8番は「戦争交響曲」の第2番目です。
この第8番はショスタコーヴィチの交響曲の中でも最高傑作と言われてる作品です。もっとも人によって意見が異なるので、第4番が最高傑作という人もいます。筆者は少なくとも一桁の交響曲の中では間違いなく最高傑作だと考えています。
お薦めコンサート
🎵ペトレンコ(指揮)/ロイヤル・フィル、ピアノ:辻井伸行
■2023/5/26(金) サントリーホール
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (ピアノ 辻井伸行)
ショスタコーヴィチ:交響曲第8番
■2023/5/21(日) フェスティバルホール
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 (ピアノ 辻井伸行)
ショスタコーヴィチ:交響曲第8番
🎵NHK交響楽団/ジャナンドレア・ノセダ
■2023/6/16(金) 19:30 開演 ( 18:30 開場 ) NHKホール (東京都)
ショスタコーヴィチ 交響曲第8番ハ短調
解説
ショスタコーヴィチの交響曲第8番について解説します。
第2次世界大戦を振り返って
第2次世界大戦は、欧州やロシアでも悲惨な戦いを強いられました。しかし、ソヴィエトは「一歩もひくな」を合言葉に、3カ月の激戦の末、1943年にはドイツ軍を包囲し、殲滅することに成功します。その後、ウクライナも解放しました。
「創作の家」にて
ショスタコーヴィチの交響曲第8番は「創作の家」で、1943年に一気に書き上げられました。ファシストとの戦争の勝利に沸くべき時に、ショスタコーヴィチは悲劇的な性格を持つ交響曲を作曲し、それを発表すると世の中に議論を巻き起こします。つまり、ファシストとの戦争に勝った時に悲劇的な交響曲を書いたのだから、ショスタコーヴィチはファシスト側についているのでは?と誤解されそうになったのです。
そのような批判のため、ショスタコーヴィチは自身を擁護する発言を繰り返します。1953年、スターリンの死の年になって、交響曲第8番の意図は以下のように訂正されました。
この作品は、人民の苦しみを表現し、恐ろしい戦争の悲劇を反省しようとする試みだった
「ソヴィエト音楽」1956年第9号
曲としては、ベートーヴェンの『運命』と同じくハ短調に始まり、最後はハ長調で終わるというもので、そこだけ見ると勝利の交響曲なのですが、実際は短調の領域が長く重々しいもので、ハ長調になって盛り上がっても最後は静かに暗く終わるため、どう聴いても勝利の交響曲には聴こえません。
長い短調の第1楽章、戦争を思わせる第3楽章、印象的な嬰ト短調の第4楽章が中心となり、実質的には悲劇を表徴した交響曲になった、といえます。ハ短調で始まり、ハ長調で終わる、というのは本当は批判を避けるためのフェイクだったのかも知れませんが、その効果はありませんでした。
連合国各国での初演
初演は、1943年9月21日にムラヴィンスキー指揮のソ連国立交響楽団によって行われました。批判は様々あったにせよ、この曲も交響曲第7番『レニングラード』と同様、1944年以降、アメリカ、メキシコ、イギリスなど、連合国各国で初演されています。
曲の構成
ショスタコーヴィチの交響曲第8番は5楽章構成です。中心となる第3楽章にスケルツォ的位置づけの行進曲を配置し、これを中心にシンメトリックな構造になっています。例えばマーラーの交響曲第7番『夜の歌』に似た構成ですね。第3楽章は明らかに戦闘を意味するダイナミックな音楽で、この交響曲が戦争によって支配されていることを象徴しています。
■第1楽章:アダージョーアレグロ・ノン・トロッポーアレグローアダージョ(ハ短調)
陰鬱で不気味な雰囲気が長く続く楽章です。しかし、後半にクライマックスがあり、これが第5楽章で引用されることでシンメトリックになっています。
■第2楽章:アレグレット(変ニ長調)
楽観的なスケルツォです。よくロシアにいそうな楽天的なタイプの人物像で、皮肉も入っていますね。
■第3楽章:アレグロ・ノン・トロッポ(ホ短調)
ヴィオラがリズムを刻む上に、荒々しく管楽器が主題を演奏します。パーカッション、特にシンバルの活躍が印象的です。
■第4楽章:ラルゴ(嬰ト短調)
パッサカリアです。非常に印象的な名曲です。ただ、ラルゴのパッサカリアはあまり聴いたことが無いです。プラームスの交響曲第4番の第4楽章位のテンポでないとパッサカリアに聴こえないです。筆者は解説書を読んで始めてこの楽章がパッサカリアであることを知り、聴き方が変わりました。
■第5楽章:アレグレットーアダージョーアレグレット(ハ長調)
本来フィナーレが来れば、勝利の交響曲と言えますが、ショスタコーヴィチは嘘はつけませんでした。第1楽章のクライマックスが再現され、あまり勝利を感じさせないうえ、最後は静かに終わります。
おすすめの名盤レビュー
それでは、ショスタコーヴィチ作曲交響曲第8番の名盤をレビューしていきましょう。
ムラヴィンスキー=レニングラード・フィル (1982年)
ムラヴィンスキー=レニングラード・フィルは、交響曲第8番の初演者であり、ショスタコーヴィチと意見交換しながらリハーサルし、初演を行った。そのためムラヴィンスキー盤は初演の時から既に音楽が完成していて、自分の解釈に強い自信を持っている。そのため、古いモノラルで聴いても、新しい録音で聴いても大きな印象は変わりません。このレニングラードでのライヴ録音は昔から定番ですが、ピッチに問題があることが指摘されていましたが、なかなか修正されませんでした。最新盤ではピッチの問題も修正され、ムラヴィンスキーのタコ8の代表盤としての地位を固めました。
第8番は「戦争交響曲」の2曲目で、第2次世界大戦の惨状を目の当たりにして、戦争の悲惨さや激しさを交響曲にしていますが、ムラヴィンスキーは贅肉をそぎ落としたシャープな響きで、その全てをストレートに深みをもって表現しています。第1楽章はあくまで憂鬱で、第2楽章は皮肉をあまり表に出していません。
第3楽章はこのムラヴィンスキー盤の白眉です。何があろうとも常に一定のテンポで進む、弦やスネヤなどのリズムは正確であることによって、人間が抵抗できない何かを表現していると思います。第4楽章のパッサカリアは、恐怖感を感じるくらいリアルです。第5楽章はハ長調とは思えない憂鬱な音楽ですが、盛り上がりはスリリングです。
ムラヴィンスキー=レニングラード・フィル (1978年ウィーン)
ムラヴィンスキー=レニングラード・フィルのロシアでの録音はデッドで残響の少ないものが多いです。来日公演も東京文化会館など、当時の日本のホールは大きすぎて、音響は割とデッドでした。ウィーンのムジークフェラインはムラヴィンスキー=レニングラード・フィルと相性が良いホールで、第5番『革命』も最近まで代表盤はウィーンライヴでした。ただ、残響が多めなので、雰囲気はとても良いのですが、細かいところが聴こえない時があり、最近では1982年盤やそれ以前の録音を最新技術でリマスタリングなどを行って、そちらが代表盤になっています。
いずれにせよ、ウィーン盤はとても迫力があり聴き易いので、特に初心者にはお薦めです。レニングラード・フィルの重厚な響きをしっかり聴くことが出来ますし、第8番の凄さがストレートに分かります。第3楽章など、ウィーン盤のほうが迫力あると思うんですけどね。
ムラヴィンスキー=レニングラード・フィル
ムラヴィンスキーはほとんど映像を残していません。特にロシア国内では活発な活動の割りに、映像は少なく、残された映像は画質が悪いです。このDVDも画質も音質も褒められませんが、ムラヴィンスキーが一番得意とする第8番は1984年ステレオなので、比較的画質は良いですが、あまり期待しないで観てください。どんな指揮をするのか、ムラヴィンスキーはあまり派手に動く指揮者ではありませんが、そんな指揮からこの音がでるのかぁ、と感心します。
コンドラシン=モスクワ・フィル (1967年来日)
コンドラシンは、最もハイレヴェルと言える彼のショスタコーヴィチの交響曲全集の中でも第8番を得意としており、素晴らしい名盤です。このスタジオ録音は古いとはいえ、十分演奏の凄さを伝えてくれるもので、この演奏で十分ムラヴィンスキーに匹敵すると思います。ただ、ムラヴィンスキーと比べると憂鬱さの繊細な表現が少なく、その代りダイナミックで熱気のある演奏になっています。第8番を理解するには、ムラヴィンスキーより分かりやすいかも知れません。今回のCDはライヴ録音でさらにテンポが速く、壮絶な演奏です。コンドラシンはライヴで燃え上がるタイプの指揮者なんですね。
第1楽章は早めのテンポで緊張感に満ちています。ストレートな演奏で、本質を突いていきます。モスクワ・フィルの弦の響きはレニングラード・フィルほどの深みはないですが、管楽器、パーカッションはレヴェルが高いです。テンションの高さはムラヴィンスキー以上です。盛り上がりは壮絶といえるレヴェルで、リズミカルでスケールも大きいです。第2楽章はコンドラシンもあまり皮肉は感じないですね。これは交響曲第13番『バビヤール』でも言えますが、まじめな指揮者なんでしょうね。
第3楽章はオケの力の差で、ムラヴィンスキーのほうが有利ですね。モスクワ・フィルも悪くは無いのですが、この白熱した状況だと、テンポも少し走っています。冷徹に一定のテンポを刻み続けるムラヴィンスキー盤のほうに凄みがあります。だた迫力は凄いものがあり、金管やパーカッションのダイナミックさはムラヴィンスキーを上回っています。第4楽章は少し早めのテンポであるためか、ちゃんとパッサカリアに聴こえます。第5楽章は、緊迫感がありダイナミックです。表現がストレートで理解しやすいです。
コンドラシンの演奏はテンポが速めなので、鳥瞰的に曲を聴くにはとても良いです。交響曲第8番を一体化した音楽として一気に聴けます。
プレヴィンとロンドン交響楽団の演奏です。音質もしっかりしていますし、演奏のクオリティも非常に高い名盤です。クールすぎず迫力と熱気もあります。
ロンドン交響楽団の迫力が前面に出ており、プレヴィンならではの響きの色彩感もあります。スコアの読みも非常に深く丁寧で、各所のオーケストレーションを的確に生かした演奏で、ショスタコーヴィッチが意図した緻密な響きが再現されています。またクールな中にシリアスで深みがあり、じっくり聴くことができます。
第3楽章のアンサンブルは速いテンポでも完璧で完成度が高いです。ロンドン響の特徴を活かしたスリリングな演奏です。第4楽章はシリアスで少し遅めのテンポでじっくり演奏しています。曲の良さが出る的確なテンポ設定ですね。第5楽章は良く練られた表現で圧巻です。
ロシアの演奏家とはまた違った角度で、この名曲を捉え直した名盤です。プレヴィンの良さが良く出ています。
インバル=東京都交響楽団
交響曲第8番の曲の作りを活かした演奏をしているという点では、非常に素晴らしい演奏です。インバルはウィーン響との全集がありますが、落ち着いて真面目に演奏した結果、不協和音が響きすぎて、曲によっては気持ち悪い位でした。
今回の東京都交響楽団との演奏は、それとは全く違う大胆な解釈となっており、しかも曲の特徴を良く生かしていて、本質をつかんでいる驚きの演奏です。
特にテンポ取りが素晴らしく、第2楽章もこれなら皮肉が十分感じられます。第3楽章はインバルは都響の能力を超えないギリギリの演奏をしていると思いますが、クオリティは本当に凄いです。第4楽章は適切なテンポ設定で、完全にパッサカリアに聴こえるし、その上で味わいを感じます。ウィーン響との演奏よりもそれぞれ1分以上短くなっています。
この演奏はもっと注目されてもいい名演です。時代のリアリティはもう再現することは難しいですが、今までダイナミックさだけを売りにした演奏も多かったと思います。スコアを読み込んで様式をしっかり理解すれば、今後もまだまだ名盤は出てくるだろう、と思います。
ロジェストヴェンスキー=ロンドン交響楽団
CD,MP3をさらに探す
演奏のDVD,Blu-Ray,他
ネルソンス=ロイヤル・コンセルトヘボウ管
DVD,Blu-Rayをさらに探す
楽譜・スコア
ショスタコーヴィチ作曲の交響曲第8番の楽譜・スコアを挙げていきます。
![ショスタコーヴィチ : 交響曲 第8番 (Shostakovich : Symphony No.8 / Evgeni Mravinsky | Leningrad Philharmonic Orchestra) [1982 Live] [SACDシングレイヤー]](https://m.media-amazon.com/images/I/51wrWXcVPaL._SL500_.jpg)
![シューベルト : 交響曲 第8番 「未完成」 | ショスタコーヴィチ : 交響曲 第5番 (Schubert : Symphony No.8 | Schostakovhich : Symphony / Evgeni Mravinsky | Leningrad Philharmonic Orchestra ~ 1978 Wien Live) [SACDシングルレイヤー]](https://m.media-amazon.com/images/I/51XCWYpLkFL._SL500_.jpg)
![Mravinsky Conducts Shostakovich Leningrad Philharmonic Orch [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41eiMi8GKiL._SL500_.jpg)




](/wp-content/uploads/ToRakuten.png)