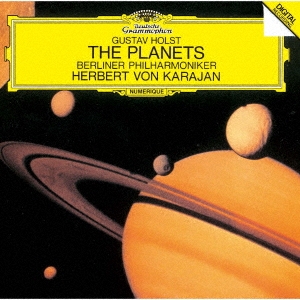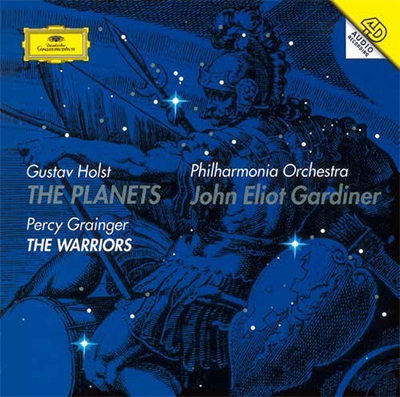グスターヴ・ホルスト (Gustav Holst,1874-1934)の組曲『惑星』作品32 (Planets Op.32)といえば、オーケストラファンのみならず、幅広いジャンルで大人気の名曲です。お薦めの名盤も数多くありますので、レビューしていきます。また下のほうにスコアへのリンクもありますのでご活用ください。
解説
組曲『惑星』と作曲者のホルストについて解説します。
「ジュピター (木星)」は大人気
「木星」の中間部のメロディですが、イギリスではエルガーの威風堂々の中間部と同じくらい人気があります。
上の「木星」はイギリス人で「惑星」の初演者であるサー・エードリアン・ボールドとロンドン・フィルの演奏です。いろいろな演奏がありますが、ここはボールドのイギリス人らしさを感じますね。「イギリスらしさ」というのはなかなか説明が難しく、ドイツの重厚さとも違いますし、チェコの芳醇さとも違います。でも確かにイギリスらしい力強さと紳士らしさを兼ね備えた響きがあるんですよね。
平原綾香のアレンジも有名で人気が高いですね。こんな感じで世界的に歌われています。
ホルストは普段は民族的な組曲が多い
ホルストはイギリスの作曲家ですが、普段はどちらかというと民族的な組曲などを作曲しています。例えば、イギリスの観光地で有名な「コッツ・ウォルズ」交響曲など。ホルストの生家はコッツウォルズにあり、チェルトナムの生家はいま「ホルスト博物館」になっています。結構、面白い博物館でした。
また、弦楽合奏の「セントポール」組曲や吹奏楽の組曲も有名です。「日本組曲」という曲もあります。普段は、比較的小編成で民族音楽を取り入れた曲を多く作曲しています。
『惑星』へのチャレンジ
そんなホルストが急に組曲『惑星』のようなスケールの大きいスペクタクルな音楽を作曲できるなんて驚きです。1913年に友人の作家クリフォード・バックスから占星術の手ほどきを受け、強い興味を持つようになったのでした。そして、第1曲『火星』が1914年に作曲され、1916年に全曲が完成しました。4管編成でパイプオルガンや女声合唱を伴う大曲となりました。
非公開の私的な初演は1918年9月29日ロンドンでエードリアン・ボールトの指揮によりニュー・クィーンズ・ホール管弦楽団により行われました。全曲の公開演奏は1920年11月15日にアルバート・コーツ指揮ロンドン交響楽団により行われました。
ホルストの時代は、宇宙船なんて無かったですし、宇宙のイメージは今のような宇宙船や人工衛星といったものではなく、占星術のイメージでした。今、曲を聴いていると、どうしても宇宙船や人工衛星が出てきそうですけれどね。映画監督のジョージ・ルーカスはスターウォーズの音楽を作曲する際にジョン・ウィリアムズに「惑星」を引用して「こんな曲を作ってほしい」とリクエストしたようです。
組曲『惑星』は初演した当初は注目されましたが、その後、忘れ去られた時期ありました。それでも初演指揮者であるイギリス人指揮者のサー・エードリアン・ボールトは『惑星』を合計6回録音する位、演奏を続けていました。
そしてカラヤン=ウィーンフィル盤が1967年に登場した時に、組曲『惑星』は再評価され、その後多くの演奏家が『惑星』を録音しました。
それに続き、メータ盤、マゼール盤、デュトワ盤など多くの名盤が誕生しました。「木星」の中間部はポピュラー歌手にもアレンジされて歌われるほどです。
組曲「惑星」の構成
「惑星」の各曲にはそれぞれの星の名前がついています。副題はそれぞれの星の持つ占星術での意味です。
当時は冥王星が見つかっていなかったため、天王星までです。冥王星が見つかったのは1930年です。しかし、近年「惑星の新定義」で、また冥王星は「惑星」にカウントされなくなったため、占星術上の惑星は最初から正しかったのですね。
なお「冥王星」は後から作曲され、ラトルのCDに収録されています。
火星:戦争をもたらす者
戦争を象徴するスネヤのオスティナート(繰り返し)で貫かれています。『惑星』の第1曲にふさわしい迫力のある人気曲です。
金星:平和をもたらす者
ホルンのソロから始まる平和な音楽です。ヴァイオリン・ソロも印象的です。
水星:翼のある使者
静かで速いテンポの小気味良い曲です。色彩的なオーケストレーションが素晴らしい曲です。
木星:快楽をもたらす者
『惑星』を代表する曲です。3部(A-B-A)構成でエルガーの威風堂々にも似た構成です。Aの部分はホルンの3拍子の主題が中心です。とてもホルストらしい曲であり、イギリス民謡風の主題を上手く取り入れています。中間部(Bの部分)は有名なメロディで親しまれています。
土星:老いをもたらす者
静かに重々しく始まりますが、徐々にクレッシェンドし、スケールの大きなクライマックスを迎えます。
天王星:魔術師
ダイナミックかつリズミカルで面白い曲です。演奏家の個性が出やすい曲です。
海王星:神秘主義者
神秘的で静かな音楽です。後半に女声合唱のヴォカリーズ(歌詞の無い歌唱)が入る。ドビュッシーの『夜想曲』を想起させます。
おすすめの名盤レビュー
それでは、ホルスト作曲組曲『惑星』作品32の名盤をレビューしていきましょう。
ボールト=ロンドン・フィル (1978年)
イギリスの名指揮者エードリアン・ボールトとロンドン・フィルの録音です。イギリス紳士を思わせる格調高い演奏です。組曲「惑星」の初演者でもあります。その後、何度も録音され、なんと5種類のディスクが残っています。それに敬意を表して、第1位はボールドの最新録音にします!もちろん演奏もイギリス的で素晴らしいです。
録音年代を羅列してみると、BBC交響楽団 (1945年)、ロンドンフィル(1953年)、ウィーンフィル(1959年)、フィルハーモニア管弦楽団(1966年), ロンドンフィル(1978年)となります。最初のBBC交響楽団の録音の時、既に演奏スタイルは確立されていると思います。ウィーンフィルとの録音が意外ですね。これはカラヤンが1961年に録音する2年前ですから、ボールドはカラヤン=ウィーンフィルの名盤のレヴェルアップにも貢献していると言えます。
ボールドの演奏はイギリス的で、他のカラヤン以降の現代的な演奏とは少し異なります。宇宙船とか人工衛星などよりは、占星術的なロマンのある「惑星」ですね。他のディスクを聴いて再度ボールト盤を聴いてみると、考え抜かれた表現とテンポ設定に感心させられます。特に『木星』が素晴らしく、中間部の有名なメロディもエルガーを思い起こさせるようなイギリス風な演奏です。ロンドン・フィルの弦楽セクションはイギリス的な格調のある響きで素晴らしいです。
カラヤン=ベルリン・フィル (1981年)
カラヤンは忘れ去られそうになっていた『惑星』を1961年にウィーン・フィルハーモニーとレコーディングし、再び人気に火をつけた立役者です。そしてカラヤン=ベルリンフィル盤では完成度が高まり、『惑星』を代表するディスクになりました。カラヤンの『惑星』は、占星術的な雰囲気と、モダンな宇宙時代の演奏の両方を兼ね備えています。ベルリンフィルとの録音は、演奏スタイルが安定していて、「カラヤンの惑星」と呼んでいい完成度だと思います。
『火星』はスケールが大きくダイナミックです。ベルリン・フィルは弦楽器の厚みがあり、それが独特の雰囲気を生み出しています。残響が多めの録音で、オルガンを思い切り鳴らしてスケールと異様な雰囲気の両方を出しています。『木星』はこのディスクの白眉です。テンポは速めで主部は金管が活躍し、重厚でダイナミックですが、どこか占星術的なボールト盤に近い雰囲気があります。中間部はベルリンフィルの弦楽器が響きが絶妙で、モダンでありながら味わい深いです。
『土星』は深みのある弦の響きが印象的で味わい深く、重厚に盛り上がっていく演奏で名演です。『天王星』は少し不気味さのあるダイナミックな演奏で、スケール大きく盛り上がります。『土星』~『天王星』は、非常にカラヤン盤の特徴が出ていると思います。
ダイナミックでリズミカルですが同時に重厚で異様さもあり、カラヤンの宇宙に対する感性を良く表していると思います。さらには、味わい深さが出ている部分もいくつかあります。
ラトル=ベルリン・フィル (2006年)
ラトルとベルリン・フィルの録音です。ラトルはイギリスの指揮者なので、ヴィルトゥオーゾ性のあるベルリン・フィルで母国の曲である『惑星』を録音するとなれば気合いが入るでしょうね。演奏は明晰で、録音もとても良いです。
このディスクの最大の特徴は、「冥王星」付きということです。「冥王星」を作曲したのはホルストの研究家でイギリス・ホルスト協会理事の作曲家コリン・マシューズで、「冥王星、再生する者」(Pluto, the renewer)という副題がつけられています。指揮者ケント・ナガノの委嘱に応じて2000年に作曲されました。しかし、「冥王星」は2006年に惑星の新定義により、冥王星は惑星から外れ、準惑星になってしまったので、たった6年間の命だったことになりますね。
「火星」はベルリンフィルの機能を活かしたダイナミックな演奏です。当時の音楽監督ラトルのコントロールが良く効いていて、ただパワーがあるだけの演奏では無く、細部までしっかりまとめられています。アンサンブルのクオリティはさすがこのコンビです。弦の響きもまとまりが良く、金管はきれいに響きます。トランペットの伸びのある演奏は素晴らしいです。ユーホニアムの響きもしなやかで理知的です。録音も良く細部まで分離が良いので、オーケストレーションの妙がよく分かります。「金星」はホルンがのびやかで透明感があり、高音質でノイズの少ない中で良く響き渡っています。木管やパーカッションも色彩的です。「水星」は速めのテンポでリズミカルです。
「木星」はイギリスらしい曲でもあり、ラトルの良さが出ています。ボールドとは違いますが、やはり紳士的な演奏です。遅めのテンポでしっかり演奏していて、各所のテンポ取りも的確で絶妙です。3拍子のリズムの取り方もイギリスの舞曲であるホーンパイプを思い出しますね。中間部は弦の響きに透明感があり、格調高いイギリスの響きです。スケール大きく盛り上がる正統派の演奏です。
「天王星」も正統派の演奏で軽快なリズムで演奏しています。リズムの取り方は「なるほど」と思える所が多いです。ベルリン・フィルの響きはダイナミックな個所でも新鮮さがあり、現代的な21世紀の宇宙旅行といった風情でしょうか。「海王星」は録音の良さが生きていて、静けさの中に神秘的な響きが印象的です。合唱のレヴェルも非常に高いです。
さて「冥王星」ですが、聴いてのお楽しみと思うので多くは書きません。「海王星」から上手く繋がっています。作風は現代的ですね。複雑な曲をラトルは非常に上手くまとめています。
「冥王星」が無くても十分優れた名盤です。ダイナミックなベルリン・フィルを上手くコントロールして、現代的な『惑星』のサウンドを引き出しています。
マゼール=フランス国立管弦楽団
マゼールの『惑星』は物凄い迫力で、特に『火星』は燃え上がりそうな演奏です。フランス国立管弦楽団は精緻な演奏とはいえないですが、火がつくと一気に盛り上がります。さらに、この「惑星」には言葉で説明しにくい魅力があります。
『火星』が白熱していて、燃え上がるような名演で特に凄いです。少し魔術的というか占星術的な惑星のイメージがあるのもこの時代の演奏としては珍しいです。
『木星』は速めのテンポで颯爽と始まりますが、とてもダイナミックでリズミカルです。3拍子のホルンの主題も速めのテンポで爽快です。そのままかなりアッチェランドしていきます。中間部は芳醇な弦楽器がダイナミックに歌い上げ、最後は燃え上がるような情熱です。フランス国立管弦楽団がこれほど凄い熱演をするのは、滅多にないですし、マゼールの気迫に圧倒されます。『天王星』は、中間の6/8拍子のメロディがとても速くリズミカルで心地良く聴けます。ティンパニなども思い切り鳴らして、ダイナミックで異様な雰囲気を盛り上げていきます。クライマックスは金管が全開で、最後のオルガンなど凄いです。これだけ異様な雰囲気を出せるのはさすがマゼールです。
マゼールの良さが良く出た名盤で、好みが合えば凄く気に入ってもらえると思います。
レヴァイン=シカゴ交響楽団 (1989年)
良い録音で圧倒的に強力な金管楽器を聴きたいならば、レヴァイン=シカゴ交響楽団です。レヴァインはショルティ並みにシカゴ響の凄さを引き出せる指揮者で、このコンビでいくつか録音がありますが、『惑星』は特に素晴らしいです。シカゴ交響楽団の金管セクションは、絶好調で『火星』から恐ろしく鳴り切っています。現代の宇宙開発が進んだ時代の『惑星』のスタンダードの一つです。『惑星』にスペクタクルを求めるなら、レヴァイン=シカゴ交響楽団は最右翼ですね。また、クオリティの非常に高い名盤です。
『木星』はシカゴ響らしい重厚なサウンドで、速めのテンポで始まります。土台の安定した低音の上に管楽器とパーカッションが色彩的な演奏を繰り広げます。3拍子のホルンのメロディは筋肉質なリズムで聴きごたえ十分です。中間部はシカゴ響の弦の音色で、パワーと共に透明感・清潔感のある響きです。2回目にフォルテになると金管も入ってスケールの大きなサウンドになります。
『天王星』は冒頭からスケールの大きな演奏です。テンポは中庸で結構リズミカルです。6/8拍子に入ると安定したシカゴ響の響きを味わうことが出来ます。そしてクレッシェンドしていき最後は重量級のダイナミックさです。
ダイナミックレンジも相当あるでしょうけれど、十分録音に入り切っています。『海王星』では、透明な静けさの中にチェレスタが響くのですが、凄い世界です。そして透明感のあるレヴェルの高い合唱が入ってきます。
デュトワ=モントリオール交響楽団
デュトワ=モントリオール交響楽団はカナダのオケらしい、非常に色彩的で透き通ったモダンなサウンドの演奏を繰り広げています。まさに現代的な宇宙船や人工衛星が出てきそうな『惑星』です。アメリカのオケに近い技術力とスイス出身のデュトワの作り出した新しいモダンな『惑星』です。
『火星』は管楽器が上手く、弦楽器に色彩が溢れた演奏で、パイプオルガンも上手く使って、現代的でスペクタクルな演奏を繰り広げています。中庸のテンポの中、ユーフォニウムのソロもとても上手いです。ホルストのオーケストレーションを活かしたダイナミックさがありますが、あくまで現代的なスマートさがあるクオリティの高い演奏です。『金星』『水星』などの比較的静かな曲も透明感の高いサウンドで、とても色彩的な洗練された響きを聴かせてくれます。
『木星』はスケール感のある標準的なテンポの演奏です。洗練されたホルンの響きが印象的です。ダイナミックさもありますが、響きはとても色彩的で洗練されています。中間部の主題は、色彩感のある弦楽セクションが朗々と歌っていて、じっくり味わえます。
『土星』では、透明感のある響きで、洗練されていながらも宇宙のロマンを感じさせます。『天王星』はダイナミックな金管で始まります。パーカッションも結構ダイナミックに鳴らしています。リズム感がとても良く、スペクタクルな響きを楽しめます。合唱の入る『冥王星』も非常に神秘的な名演です。
メータ=ロスアンジェルス・フィル (1971年)
ズビン・メータは「惑星」を非常に得意としていて、ロスフィル盤とニューヨーク・フィルハーモニック盤の2種類のディスクを録音しています。名盤はロスフィルの方で、最初の一枚を探している方にもお薦めします。この時代はちょうどアメリカのオーケストラの黄金時代でした。特にロスフィルの管楽器は非常に技術力が高くて、ヨーロッパのオケでは、なかなかこのレベルの演奏は出来ないですね。録音は少し古さがあるため、リマスタリングされたディスクで聴くのが良いです。
『火星』は少し速めのテンポで重厚かつスペクタクルで現代的なダイナミックさがあります。ユーフォニウムのソロは独特の響きで異様な雰囲気を醸し出しています。低音から高音までしっかり鳴っていて凄い重厚さです。それと共にテンポは速めでモダンな演奏でもあります。
『木星』は標準的なテンポでダイナミックな演奏です。パーカッションを効果的に使っていて、重厚ですがモダンな演奏です。ホルンの主題もしっかりしています。中間部の主題は色彩感のある弦が朗々と歌っていて、味わいがあります。
『土星』は神秘的な雰囲気が良く出ています。『天王星』は金管がダイナミックで、ティンパニも鋭く打ち込んでいます。ホルストのオーケストレーションを上手く生かし、色彩的でスペクタクルな響きを紡ぎだしています。リズムもしっかりしています。『海王星』は神秘的な雰囲気が良く出ています。
メータの指揮はダイナミックで堂々として、メータの長所がそのまま活きています。またロス・フィルの上手さが際立っています。モダンでスペクタクルな『惑星』の典型的名盤として、トータルとしてお薦めできるディスクだと思います。ロス・フィルはハリウッドに近いからか、スターウォーズなどの現代の宇宙に対する雰囲気を作るのが上手いです。
プレヴィン=ロンドン交響楽団 (1973年)
プレヴィン=ロンドン交響楽団の定評ある名盤です。若いプレヴィンのエネルギーを感じます。オケはイギリスで最もダイナミックさのあるロンドン交響楽団です。録音は1973年と若干古めですが、しっかりと安定した音質です。リマスタリングのおかげもあり、立体的な響きです。
「火星」は速めのテンポで燃え上がるような白熱した演奏です。ユーフォニウムの音色は柔らかく良く雰囲気が出ています。後半はティンパニを中心としたパーカッションの鋭い打ち込みが印象的です。金管も硬質でダイナミックな迫力があります。弦は独特の色彩感があります。「金星」のホルンも上手く、雰囲気が良く出ています。落ち着いて聴ける演奏です。
「木星」はイギリス的な堂々とした名演です。ホルンの3拍子の個所など、リズミカルでテンポ設定が上手く、スコアの読みも深いですね。中間部はまさにイギリスの格調高さのある響きです。
「土星」は奥深さのある佇まいです。響きはモダンであり、良く練られています。盛り上がってくるとスケールが大きく、金管の響きは現代的です。オーケストレーションを良く活かしていて聴き所が多いです。「天王星」はスケールが大きな主題提示で始まり、少しグロテスクさも伴いながら、リズミカルにダイナミックに盛り上がります。「海王星」は神秘的で色彩感があります。
イギリスな格調の高さをベースに、現代的でスペクタクルな面を加えた名盤です。メータ盤と共に『惑星』のモダンな演奏の草分けと言えると思います。迫力という面のみで見ても、色彩感があって多彩な響きで、十二分に楽しめるディスクです。
スタインバーグ=ボストン交響楽団 (1971年)
ウィリアム・スタインバークという指揮者はベートーヴェンの交響曲全集などでも名盤を残しているベテラン指揮者です。この『惑星』は結構スリリングで迫力があります。
「火星」はテンポが速く弦のリズムが強烈です。ボストン交響楽団もスリリングでダイナミックに演奏していて、ユーホニウムも白熱しています。このテンポの速さは凄いですね。マゼール盤には及びませんが、リズミカルで別の面白さがあります。「金星」などは遅めのテンポで美しくまとめています。アンサンブルのクオリティは少し落ちますが、上手く雰囲気を出していて楽しめる名盤です。
「木星」はちょうど良いテンポで始まりスタンダードでダイナミックな演奏です。ホルンの主題もスケールが大きいです。中間部もゆったり目のテンポで上手く歌わせていて、有名なメロディを存分に味あわせてくれます。後半もダイナミックな演奏で充実感があります。
「土星」はボストン響の弦の響きが味わい深く、表現にも深みがあります。「天王星」も少し遅めのテンポで異様な雰囲気をよく出しています。リズム感もあり、色彩感もあって聴きどころが多く楽しめます。
全体的に聴きどころが多く面白い演奏です。ボールトの演奏が好きな人はきっと気に入ると思います。ボールトほど、イギリス的では無いですが、ボストン響の金管は上手いですし、「土星」「海王星」などは芳醇に味わい深く聴かせてくれる名盤です。
組曲「惑星」の名盤:番外編
ランキング形式でレビューしてみました。番外編で挙げる演奏は物差しで測りにくいですが、聴いて新鮮さを感じる名盤ばかりです。
カラヤン=ウィーン・フィル (1961年)
この演奏が録音された1961年といえば、ちょうどアポロ計画で最初に月に着陸した頃です。「月」なので惑星ではなく衛星ですけど、確かに組曲『惑星』が再度世に出るのに、とても相応しいタイミングですね。その頃までは人工衛星などもなかった訳ですが、それから10年程度の間に長足の進歩を果たして、宇宙へのイメージが大きく変わっていくことになります。さらにはスペースシャトル計画も実行され、地球の周りには多くの人工衛星が打ち上げられていきます。
組曲『惑星』の再デビューを担ったカラヤン=ウィーン・フィルの演奏は、まるでアポロ計画の一環のような、異様なまでに勇ましい演奏になっています。これがウィーン・フィルだなんて、信じられないですね。しかもこの録音は非常に品質が良く、ハイレゾ化など高音質化技術の恩恵をよく受けられるディスクです。
「火星」から凄みが感じられます。ユーフォニウムのソロが物凄く前に出ていて、異様な迫力は他の演奏では聴けないものです。後半のリズムの打ち込みは凄い気迫で荒々しく、物凄いインスピレーションを感じます。
「木星」はカラヤン独特のテンポ取りで、ボールトなど歴史的な演奏とは一線を画しています。力強いドイツ的と思える演奏です。スタイリッシュな演奏スタイルは後続の演奏家に大きな影響を与えていると思います。中間部の有名なメロディはとてもスケールが大きいです。
「土星」は洗練されている所と神秘的な占星術を思わせる所が交錯しています。盛り上がる所では物凄い気合いですが、パーカッションが異様な雰囲気を漂わせています。「天王星」はやはりダイナミックで、神秘と異様さがあります。この演奏スタイルも後続の演奏家に大きな影響を与えていそうですね。
ウィーンフィルとは思えない気迫と、独特の異様な雰囲気を持った演奏ですが、当時の宇宙に対するイメージと、組曲『惑星』の凄さを聴かせてやろうという気迫、そして実際宇宙開発がまさに進み始めてアポロが月に初めて有人飛行する時代のリアリティを「これでもか!」と感じさせてくれる凄い演奏です。実は、カラヤンの前にエイドリアン・ボールトがウィーン・フィルと録音していて、ウィーン・フィルはその影響を受けているはずですが、実際聴いてみると大分違う演奏です。
ボールト=フィルハーモニア管弦楽団 (1966年)
ボールトの録音では、最後の録音から一つ前のフィルハーモニア管弦楽団との録音も聴いておくべき名盤です。
シャープかつダイナミックで、ボールトの若さと迫力を感じます。ロンドン・フィル盤と12年違いで、ちょうどアポロ計画が実行されていた頃の演奏でリアリティが凄いです。カラヤン=ウィーンフィル盤ほどの怪演ではなく、スタイルが確立しています。
このフィルハーモニア盤がボールトの『惑星』の最盛期かも知れません。聴き比べると演奏スタイルが大分違います。ロンドン・フィルとフィルハーモニア管でそれぞれ良い所があって、どちらが最高とも言い難いです。
ユロフスキ=ロンドン・フィル (2009年)
ユロフスキはロシア出身で西ヨーロッパで活躍している指揮者です。オケは、ボールトと名演を残しているロンドン・フィルです。ユロフスキの演奏は、最晩年のボールトとは正反対で、全体に速めのテンポとシャープで質の高いアンサンブルが特徴です。自作自演もテンポが速いので、元々そういう要素が『惑星』にはあるのだろう、と思います。
『火星』は、かなりのスピードで少しせせこましい感じもありますが、かなりシャープでダイナミックな演奏です。後半は特に迫力があります。アンサンブル能力も高く、正確な演奏です。2009年録音と他に比べて録音が新しいため、響きの透明度が高く色彩感があります。ボールトやカラヤンのテンポ取りも、「宇宙」というスケールの大きさを重視したものと感じますが、ユロフスキは普通のテンポで、ホルストの自作自演に近いです。
『木星』は相当スピーディです。スケールの大きさより、むしろリズミカルで軽快な演奏と言えます。ホルンの主題はしっかり吹かれていますが、アッチェランドすると凄いテンポになります。中間部はさすがロンドン・フィルで弦楽器のイギリス的な響きが楽しめます。後半は、スコアをしっかり読みこんで正確なテンポ取りをしている所に好感が持てます。
組曲『惑星』で、これまでの演奏であまり聴こえていなかった、リズミカルな音楽が聴けることは新鮮です。
スヴェトラーノフ=フィルハーモニア管弦楽団 (1994年)
ロシアの巨匠スヴェトラーノフの『惑星』です。オケはスウェーデン放送交響楽団ですが、完全にスヴェトラーノフの術中にハマっています。スヴェトラーノフは晩年テンポが凄く遅くなりましたね。
この遅いテンポの「火星」からして凄いスケールを感じます。この重量感はなんなんでしょう?こんな演奏は初めて聴きました。中間の静かなところも響きを噛みしめるようにして、じっくり演奏しています。また盛り上がってきてもテンポはそのまま。金管は遅いテンポでがんばって吹かねばなりません。それも含めて妙な迫力に繋がっているように思います。
(自作自演)ホルスト=ロンドン交響楽団
『惑星』に関して、ホルストの自作自演をどう評価するか難しい所です。このテンポの速さはかなりのものです。最初はCDがおかしいのかと思いました、笑。1930年代だとテンポの速い演奏が多く、その影響もあるかも知れません。
聴いていると、これは「吹奏楽のための組曲」や「セントポール組曲」など、ホルストが普段作曲しているイギリスの民族音楽に似ています。なるほど、こんな要素が「惑星」にもあったのか、と少し目から鱗(うろこ)で、この曲を良く知りたい方は、必聴です。特に「木星」はイギリス民謡の要素が多く入っており、ホルストらしい曲であることが分かります。
「惑星」は良く聴くと、面白い音楽です。それはイギリスの民族音楽の要素が入っているからだと思います。基本的な作曲技法自体は、他の民族的な曲とそれほど違わないのでしょうね。
小澤征爾=ボストン交響楽団 (1979年)
小澤征爾と手兵ボストン交響楽団の『惑星』です。小澤征爾と言えば、凄くダイナミックな演奏を期待するかも知れませんが、この『惑星』は一番フレッシュな名盤です。エイドリアン・ボールトやデュトワも含めて、ほとんどのディスクがダイナミック路線なので、この小澤盤に順位をつけるのは凄く難しいです。1972年に録音したディスクが今まで生き延びてきて、今でも高く評価されているということは、それだけの内容を持っているからです。
第1曲『火星』は、他の演奏に比べるとそれほどスケールはありませんが、響きがとてもフレッシュです。暴力的な部分や毒々しさはなく、きれいな響きのまま盛り上がります。ボストン交響楽団は金管を中心にハイレヴェルでとてもフレッシュなサウンドです。第4曲「木星」は、すっきりまとまっています。これも他の演奏は重厚なので、クオリティの高い演奏ですね。第6曲「天王星」はダイナミックですが、フレッシュさは失いません。最後の「海王星」も色彩的できれいにまとまっています。ニュー・イングランド合唱団のレヴェルの高さは特筆に値します。
これまでのダイナミックな『惑星』を聴いてきた方には、新鮮さがあって目から鱗がおちる部分もあります。特に静かな曲をスッキリと聴きたいなら、小澤盤意外にないように思います。
佐渡裕=NHK交響楽団 (2005年)
佐渡裕とNHK交響楽団の演奏です。このコンビの演奏はもちろんダイナミックですが、クオリティが高く品格があります。『惑星』というと、ボールト盤は占星術的な怪しさがあり、デュトワ盤であっても不気味さがあります。佐渡裕は熱気がありながらも品格があって奥ゆかしいです。テンポ取りの的確さも特筆すべきと思います。良く聴くと他では聴けない『惑星』であることが分かると思います。
「火星」はN響らしくマッシヴ(筋肉質)で迫力があり、スケールが大きく盛り上がりますが、同時に丁寧さがあります。ユーフォニアムのソロなど、しっかりきれいに演奏されています。弦のレヴェルは高いです。金管もダイナミックです。和音も先入観なくきれいに響いています。「金星」も良い演奏です。これだけ練り上げた金星は他では聴けないものだと思います。ホルンのソロも素晴らしいです。
「木星」は佐渡の上手いテンポ取りが絶妙で、とてもリズミカルでありながら、ユロフスキ盤のように速すぎることはありません。ホルンの主題のアッチェランドもスケール感を失わない程度に速めのテンポです。中間部は遅めのテンポで、透明感のある弦が朗々と歌い、クレッシェンドしても品格があります。
「土星」は厚みのあるサウンドで、不気味さはありませんが、じっくり演奏されていて充実感があります。N響の奥ゆかしさの中に佐渡裕の熱気がありますね。「天王星」はダイナミックな金管で始まります。金管はレヴェルが高く、昔のN響と比べると隔世の感がありますね。佐渡裕の軽妙なリズムと熱気のあるテンポ取りが心地よく、盛り上がります。「海王星」は透明感が高く、高音質が効果的です。
ガーディナー=フィルハーモニア管弦楽団 (1994年)
古楽器中心に活動しているジョン・エリオット・ガーディナーが『惑星』を振るとは思っていませんでした。しかし、ガーディナーもイギリス人です。同じイギリスのフィルハーモニア管とイギリスのコンビで『惑星』を録音しました。
「火星」は意外にテンポが遅めで重厚、低音域が素晴らしいです。ユーフォニウムのソロも上手いです。迫力はまあまあですが、アンサンブルのクオリティが高いです。オケは迫力を出そうと気合いが入っているが、ガーディナーは別のものを求めているようで、落ち着きを失いません。「金星」も落ち着いています。「木星」は速いテンポで小気味良く開始。ホルンの主題になると少しテンポを落としてしっかり聴かせてくれます。有名な中間部はきれいに歌っています。ただイギリス風ということではなく、ボールトの演奏の反動なのかも知れません。「海王星」の合唱は特筆すべきで、非常に神秘的でモンテヴェルディ合唱団のレヴェルの高さが分かります。
CD,MP3をさらに探す
楽譜
ホルスト作曲、組曲『惑星』のスコアと楽譜を挙げていきます。
ミニチュア・スコア
No240 ホルスト 組曲惑星 (Kleine Partitur)
5つ星のうち4.4 : 3個
オイレンブルクスコア ホルスト 組曲「惑星」作品32 (オイレンブルク・スコア)
解説:コリン・マシューズ
5つ星のうち4.4 : 3個
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。
大型スコア
Holst: The Planets in Full Score
レビュー数:94個