
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (Ludwig van Beethoven, 1770~1827)作曲の交響曲 第9番 ニ短調 作品125 『合唱付き』(Sinfonie Nr. 9 d-moll op. 125 Choral) の解説と、評判の良い名盤をレビューしていきます。 『第九』『合唱』などの愛称で呼ばれ、年末にアマチュア合唱団なども含めて第九のコンサートが行われるなど、広く親しまれています。
1万人第九のコンサートなどは世界的にも有名になりました。初演もプロ・アマ混成で行われていますし、ベートーヴェンの思想にも相応しいですね。
お薦めコンサート
🎵インキネン、日本フィル
■2023/5/20(土)17:00 開演 ( 16:10 開場 )会場:横浜みなとみらいホール 大ホール (神奈川県)
シベリウス:交響詩《タピオラ》op.112
ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱》 ニ短調 op.125
[指揮]ピエタリ・インキネン [独奏・独唱]森谷真理(S) / 池田香織(A) / 宮里直樹(T) / 大西宇宙(Br) [合唱]東京音楽大学
解説
ベートーヴェンの交響曲第9番『合唱付き』を解説します。
ベートーヴェンは『運命』『田園』と同じころ、『合唱幻想曲』という作品を作曲しています。これは交響曲第9番の原型と言われています。交響曲に合唱を持ち込むという試みは、既に他の例が発見されているため、初めて、という訳ではないようです。ベートーヴェンが先例を知っていたかどうか分かりませんが、知っていたとしても余程の名作でない限り、あまり参考にしなかったと思います。この曲は、交響曲の作曲家であると共に対位法の作曲家であるベートーヴェンの総決算だからです。
作曲
1815年ごろからベートーヴェンは作曲を開始しました。第九の作曲については様々なことが言われています。例えば、7番、8番、9番は3連作として作曲される予定だったなどです。
しかし実際は、1814年以降10年間は、フランス革命に端を発した貴族の没落により、交響曲の需要が減ってしまったこともあり、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」を勉強し、対位法に強い影響を受けた『ハンマー・クラーヴィア』ソナタや宗教音楽である『ミサ・ソレムニス』など、ベートーヴェンの作曲技法に対しては、かなり重要な作品を作曲していました。
そして、1822年52歳の時にロンドン・フィルハーモニック協会から新しい交響曲の作曲依頼を受けます。実は、交響曲第8番を作曲する前の1809年頃から第九のスケッチが存在するため、第九のアイデアは10年以上も前からあった可能性があります。上述の7番、8番、9番が連作として構想されていた可能性は十分あるのですね。
確実に言えることは、交響曲から離れていた10年間の間も、交響曲に対する作曲意欲が衰えていたわけではない、ということです。
自分が貧乏でなかったら無報酬でも作曲したいところである
との言葉が残っています。
「シラーの詩」に至っては、1790年に作曲したカンタータでもその思想を思わせる歌詞を使っています。実にベートーヴェンが若いころからのライフワークともいえます。
さてWikipediaによれば、当初は2曲並行して作曲する予定だったようですが、
しかしさまざまな事情によって、交響曲を2つ作ることを諦めて2つの交響曲のアイディアを統合し、現在のような形となった。
Wikipediaより
依頼から2年後の1824年に初稿が完成し、その後、何度も手直しして、1824年5月7日に初演が行われました。
初演と評価
第九の初演はプロ・アマチュアの混成で、弦楽器のみで50人、管弦楽トータルで80~90人、合唱は40人という説と80人という説があるようです。とにかく当時としては大人数だったということですね。しかし、当時のオケだと合唱80人ではオケが聴こえなくなりそうです。
ウィーンのケルントナートーア劇場において、ミヒャエル・ウムラウフの指揮も下で行われました。練習不足と歌手が若手であること、直前に2人が変更になったこと、アンサンブルの崩壊を防ぐためピアノが入ったこと、などがWikipediaに記載されています。
そして一番面白い逸話というべきか、耳が完全に聴こえなくなってしまったベートーヴェンは、指揮者のウムラウフと共に指揮台に上がり、ウムラウフに対してテンポを指示したということです。初演時に作曲家が練習に立ち会って意見を交換するのは当然ですけど、指揮者の二人羽織って、本当だったのですかね。
それでも第九の初演は大成功でした。しかし、聴衆の拍手が聞こえなかったベートーヴェンは初演を失敗と勘違いし、しばらく聴衆のほうへ振り返らず、ウムラウフに促されてやっと初演の成功を知ったという逸話があります。(これは有名な逸話かもしれませんね。)
楽曲構成
第九では交響曲に合唱を組み入れるという構想を実現するため、ベートーヴェンはあらゆる作曲技法を組み合わせています。それこそ、交響曲、オラトリオ、オペラの様々な技法を組み合わせています。
前半3楽章はこれまでベートーヴェンが築き上げてきた交響曲がベースとなり、スケールを大きくしたものです。
あまり難しい話は避けますが、第4楽章は長いうえにストーリーがあります。それを頭に入れておくと5分程度の音楽にわけて聴くことができます。
第1楽章~第3楽章
第1楽章が弦のトレモロで幻想的に始まるのは特徴的で、弦のロングトーンから始まる曲はよくあるのですが、トレモロに変えたことで神々しい音楽となっています。これは後年、ブルックナーに大きな影響を与えています。ブルックナー開始はここから来ています。
また第2楽章にスケルツォを置き、第3楽章を緩徐楽章としたことで、第4楽章に管弦楽のみの序奏的な音楽を置くことが出来ました。
第4楽章
第4楽章はチャレンジングな楽章となりました。ここに合唱を入れるために、ここまでの3楽章を作曲してきたわけですが、第4楽章もすぐに合唱が入るわけではありません。
♪第0部:管弦楽のみ
第1楽章から第3楽章の回想から始まります。勝手に第0部と命名しました。
この部分は管弦楽のみよるレチタティーヴォという非常に独創的で矛盾した音楽です。レチタティーヴォは通常オペラやオラトリオで歌手がセリフを語るときに使用される形式です。第4楽章はまずオペラから引用してきた様式で、合唱が出るまでの準備をしているのです。
歌手や合唱がいるのに管弦楽によるレチタティーヴォというのはとてもユニークです。弦楽器がセリフを語るように演奏しますが、楽器ではセリフは言えませんから、難しいし聴いているほうも物足りないですね。
第4楽章の1/3にさしかかるころ、低弦によりpで『歓喜の歌』のメロディが提示されます。そしてカノンの技法により、徐々に参加するパートが増え、最後にはオーケストラのトゥッティとなります。すなわち管弦楽のみの『歓喜の歌』です。
「管弦楽のみでは物足りない」ついに合唱が入る下地が整いました。
合唱が入るとそこから先は、対位法が中心となり、バッハやヘンデルから学んだ技法を一気に放出しています。しかし、その外側を大きく見ると、3部形式 (または2部形式)で、(いびつですが)展開部なしのソナタ形式とみることも出来ます。
堅固な形式の中で、対位法などの古い音楽様式が使用されていきます。ベートーヴェンが知っていたバッハの作品は、鍵盤など器楽曲が多かったため、主にヘンデルのオラトリオをベースにしていると思いますが、それだけでは説明できません。オラトリオは小さな楽曲が連続して出来ています。交響曲の様式と対位法の様式をベートーヴェンなりに解釈して、合成させて昇華した音楽といえます。
♪第1部
『歓喜の歌』が管弦楽で演奏されましたが、最初の強烈な音楽によって引き戻されます。この後、初めてバリトンの歌唱が出てきてレチタティーヴォで「おお友よ、このような音ではない!」と歌います。ここまで管弦楽による第1楽章~第3楽章までの音楽が回想され、『歓喜の歌』を演奏してきたわけですが、最初の歌詞はここまで演奏してきた管弦楽だけの音楽をいきなり否定しています。
そして『歓喜の歌』が合唱を含めて再度演奏されます。全体の流れを見ると、ここまでの音楽は、このために作曲されてきたといっても過言ではないと思います。このセクションの最後は合唱のキツいロングトーンで有名ですね。
第1部は先ほどの合唱による『歓喜の歌』から始まり、対位法を用いた音楽が展開されていきます。
後半は6/8拍子の軍隊風の「行進曲」になります。シンバルなど打楽器群を用いた行進曲は壮大に盛り上がっていきます。その後、管弦楽のみの複雑で力強く、苦悩に満ちたフガートが演奏されます。このフガートはオーケストラセクションでは難しくて有名な「間奏」で、第九の中でも凄い厳しさを伴った音楽で、バッハの影響が伺えます。
♪第2部
トロンボーンによる荘重なコラール風の新しい旋律が登場します。「抱擁の詩」です。さらに「創造主の予感」が引き続き歌われます。ソナタ形式で見た場合はこれが第2主題でしょうね。(調性未確認)
♪第3部
有名な「ドッペルフーガ」(二重フーガ)に入ります。2つの主題を持つフーガのことです。ここでは「歓喜」と「抱擁」の2つの主題によるドッペルフーガです。ソナタ形式で見ると第1主題と第2主題のドッペルフーガになるので、ちょっと無理がありそうです。
速いテンポの2拍子となり、4人の独唱が「歓喜の歌」をフーガ風に歌います。そこに合唱が入ってきます。また4人の独唱のアンサンブルに戻り、独唱はここで終わりです。曲調も終わりに近づいたことが感じられます。
最後は、Prestoでクライマックスを築いていきます。4小節間マエストーソとなり、最後に「歓喜の歌」を合唱で歌い上げた後に、管弦楽のみPrestoに戻り曲を閉じます。
おすすめの名盤レビュー
ベートーヴェン作曲の交響曲第9番『合唱』(通称『第九』)の名盤をレビューしていきます。
バーンスタイン=ウィーン・フィル
バーンスタイン=ウィーンフィルの第九はスケールの大きな名演です。バーンスタインの円熟が感じられます。録音は1979年ライヴで、良くも悪くもないですが、聴きやすいです。
第1楽章は中庸で自然なテンポ取りです。余分な力が入っておらず、しなやかで自然な音楽が楽しめます。テンポは特に遅くはなく盛り上がる所はダイナミックに盛り上がります。ソナタ形式の第1楽章は充実しています。第2楽章は結構速めのテンポのスケルツォです。第3楽章は遅めのテンポで静かにゆっくりと進んでいきます。神妙さもあり、味わいも深いです。フルトヴェングラーとはまた違った、美しさのある名演です。
第4楽章はかなりの不協和音から始まります。レチタティーヴォはじっくりゆっくり演奏されています。『歓喜の歌』も遅いテンポで、特に弦楽器が美しい音色を出しています。テノールは声が太くスケールが大きく、油絵のような音楽となって進んでいきます。もともとテンポが遅い上に、合唱のロングローンは長く、クレッシェンドしていて凄いです。オケのみの間奏部分は迫力があります。コラールは合唱が凄いです。天上の女声が現世の男声と上手く絡み合って、独特の響きを引き出しています。これを聴くとドッペルフーガの意味も分かりますね。最後はテンポが速くなり、熱狂の中で終わります。
全体としては、レナード・バーンスタインの円熟期の演奏で、指揮のテクニックは全く落ちていませんから、味わい深さのあるスタンダードな名盤です。
バーンスタイン=バイエルン放送響 (ベルリンの壁崩壊記念)
1989年にベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一され、その年のクリスマスに演奏された第九です。バイロイトの第九と並び称される歴史的名演です。バイエルン放送交響楽団が中心ですが、シュターツカペレ・ドレスデン,ニューヨーク・フィルハーモニック,ロンドン交響楽団,キーロフ劇場(現マリインスキー劇場)管弦楽団,パリ管弦楽団のメンバーなど、東ドイツやロシアからもメンバーが駆け付け参加しました。本当に一期一会です。
第1楽章は遅いテンポでスケールが大きな演奏です。フォルテになると金管やティンパニをダイナミックに鳴らしています。一方、さまざまな国、オーケストラからやってきた楽員たち、一応バイエルン放送交響楽団が中心になっていますが、東西でも分断されていた長い期間に大分演奏スタイルに違いが感じられます。バーンスタインは楽員たちのスタイルの違いをおおらかに合わせていくように、じっくりとした歩みで演奏しています。
第2楽章は遅めではありますが、そこそこなテンポで演奏しています。リズム感はオケ内部でも大分合ってきた雰囲気です。細かい所は色々な個性があって面白いですけど。第3楽章は素晴らしいです。じっくりと遅いテンポで、とても円熟味があり味わいがあります。後半、短調が多くなってくると、さらに味わい豊かになります。至る所でテンポを落とし、じっくりと味合わせてくれます。
第4楽章も遅くスケールが大きい演奏で始まります。レチタティーヴォの歌いまわしは本当に円熟味が感じられます。この辺りでは、第1楽章で感じた楽員同士のズレはもう感じられません。これは凄いことですね。じっくりと盛り上がっていく「歓喜の歌」は神々しさを感じるほど、素晴らしい演奏です。合唱の水準はとても高いです。東西の混成合唱団が素晴らしい合唱を聴かせてくれます。とてもスケールが大きく、ここまでテンポが遅い演奏は他にはないかも知れませんね。ドッペルフーガは、とても合唱の響きが素晴らしく聴いていて充実感があります。最後は一気にスピードアップし、一気に盛り上がります。
ブラヴォーコールも臨場感があっていいです。第九の演奏のクオリティなら、ウィーンフィル盤の方が良いですが、こういう記念コンサートはまた違った楽しさがあります。
テンシュテット=ロンドン・フィル
テンシュテットとロンドン・フィルを主体とした演奏です。ソプラノのルチア・ポップなど、有名な歌手も揃っています。録音はライヴですが、スカッとした心地よい録音です。
第1楽章からテンシュテットらしい熱気に溢れた名演です。オケのクオリティも高く、しっかりした構造が感じられます。絶妙なテンポ取りで、この楽章が持つしっかりした構造と熱気のバランスが上手く取られています。金管楽器の強奏が印象的です。第2楽章はスケールの大きさもありながら、テンポの速いシャープな演奏です。クレッシェンドでは白熱して盛り上がります。中間部のテンポは余裕があり、ホルンの音色など良く楽しめます。
第3楽章はしみじみと落ち着いた演奏で、感情表現も巧みです。ゆっくり目のテンポでじっくり聴かせてくれます。
第4楽章はとてもダイナミックで壮大です。前半は劇的な表現でテンシュテットらしさがあります。合唱が入ると結構レヴェルの高い合唱団で、自然でスケールの大きさを感じさせます。後半に入ると白熱してきて、ラストは凄い盛り上がりです。最後は割れんばかりの拍手が録音されています。
テンシュテットは気迫あふれた名演が多いですが、この第九は気迫や熱気だけではなく、壮大な響き設計やクオリティの高さもあります。第九の初心者にもお薦めですし、玄人にもお薦めできる質の高さがあると思います。
カラヤン=ベルリン・フィル (1980年代)
カラヤン=ベルリンフィルの録音です。カラヤンは第九を遠慮なくダイナミックに演奏しています。カラヤンのスタイルを突き詰めた名盤です。1980年代のカラヤンは円熟して独特の響きを紡ぎだしていて、第九は1980年代の演奏がピークと思います。
第1楽章から物凄い気合いでダイナミックな演奏です。このサウンドには圧倒されます。他の演奏でも第1楽章は感銘を受けますが、それとはまた違ったクオリティの高さです。第2楽章は速めのテンポで生きいきと演奏されています。どんな所でもダイナミックでありながら、サウンドに濁りが無い所に凄みを感じます。第3楽章は朗々と歌わせていてスケールが大きいですね。円熟期のカラヤンらしいシルバー色の響きが聴けます。インテンポで進んでいきますが、少しゆとりを感じます。
第4楽章は凄い速さで始まります。レチタティーヴォは速めのテンポで進み、『歓喜の歌』が始まると一気に雰囲気が変わり、神妙に盛り上がっていきます。アンサンブルのクオリティの高さを感じます。コラールの女声やオケは天上の音楽のように響きます。ドッペルフーガは非常に立体的に聴こえて大聖堂にいるかのようです。その後、最後までダイナミックに高いクオリティと緊張感を維持して演奏しきっています。
小澤征爾=サイトウキネンオーケストラ
小澤征爾とサイトウキネン・オーケストラの第九は、シャープですっきりした美しさを感じる演奏です。サイトウキネン・オーケストラのアンサンブルは完璧ですし、力強さで誤魔化さず、丁寧にまとめています。DVDも持っているのですが、小澤征爾の指揮は力強くしっかり拍を刻んでいます。指揮ぶりを見られるので、DVDのほうが良いかも知れませんね。
第1楽章からシャープで力強い演奏です。しかし、極端なダイナミックさはなく、丁寧さが常に感じられます。小澤征爾のベートーヴェンは解釈は、昔から大きな変化がなく、常に一つの方向に向かって迷いなく進化しています。しかし、ヨーロッパの指揮者と違って水彩画のような繊細さも併せ持ち、近道せずに徐々に自分の音楽を表現できる範囲が広がってきた感じです。
率直に言うと小澤征爾はもともとベートーヴェンのような古典派の音楽はそれほど得意としてはいないと思います。小澤征爾の名盤と言えば、プロコフィエフ、ヤナーチェクやプーランク、オネゲルなどの近現代作品が多いですね。鋭い感性を持っていて近現代の作品に一番あっているのです。ヤナーチェク『シンフォニエッタ』やオネゲルの『火刑台のジャンヌダルク』は超名演の部類です。でもベートーヴェンは賛否ありますね。第九は小澤征爾という天才にとっても努力の賜物なのです。サイトウキネン・オーケストラという自分と音楽性の近いオケを結成できたことも大きな力となっていると思います。
第4楽章はあくまで丁寧であり、不協和音がドロドロと響くこともありませんし、アンサンブルはどんな時も正確で、羽目を外すことはないです。レチタティーヴォでは、弦楽器中心で管楽器は軽く入るのみです。
やがて冒頭の不協和音が戻り、テノールが入り合唱が入るとスケールを増してきます。6/8もリズミカルですが、雑さは全くありません。盛り上がって器楽の間奏に入るとオケはかなり凄みのある演奏をしていますが、端正さは失われません。コラール部分も合唱はかなり盛り上がってきています。終盤はかなり味わい深くなりますが、指揮ぶりを見ていても、やはり最後まで端正さがあり、典型的とも言えるテンポ取りでダイナミックな中でも最後まで緩みはありません。
でもとても充実感のある演奏で、演奏後には会場は熱狂的なブラヴォーコールに包まれますし、DVDで見ていても凄い充実感と感動を覚えます。それは小澤征爾=サイトウキネンが最後まで一点の妥協もなくやり遂げたことへの充実感なのだと思います。
「何も足さない、何も引かない」ニッカ・ウィスキーのような演奏です。そう考えると小澤氏の円熟もかなりあるのかも知れません。数か所、つまんで聴くだけだと妙にスッキリした演奏に聴こえるかも知れません。やはり全曲通しで聴くことは大事ですね。
フルトヴェングラー=ウィーン・フィル (1952年)
フルトヴェングラーとウィーンフィルの名高い第九です。ウィーン・フィルの透明感のある響きを活かした神々しさのある名演で、筆者は昔からフルトヴェングラーと言えばこちらの演奏を聴いていますが、聴けば聴くほど素晴らしさが身に染みる名演です。ライヴ録音のため段々と感情が入って盛り上がってきます。
第1楽章は、遅いテンポで始まり段々速くなってきます。ライヴのせいか、盛り上がってきて充実したソナタ楽章を聴かせてくれます。第2楽章は、意外と速めです。録音の良さのおかげもあって聴きやすいです。特にトリオは速めのテンポで良いです。
第3楽章は変奏を楽しむかのような演奏です。枯れた表現の中に愉しさすら感じられます。そして、2か所出てくるトランペットとその後の感情表現も素晴らしいです。この感情表現はフルトヴェングラーにしか出来ない芸当ですね。こんなに味わい深い所があると、やはりフルトヴェングラーは永遠の名盤なんだなと思います。
第4楽章は(録音のせいもあって)凄い不協和音から始まります。他の演奏では軽く流しがちなレチタティーヴォや回想部分も力を入れて演奏しています。『歓喜の歌』の出だしはとても良い雰囲気です。やがてテノールや合唱が出てくると凄いスケールと熱気に包まれます。6/8も盛り上がり、オケの間奏もなかなか凄いです。コラールは合唱が上手く、とても神々しい響きです。おそらく合唱の人数も多めだと思うのですが、このディスクの合唱はとても上手く、雰囲気も出ています。ドッペルフーガも神々しいです。
ここから先は、フルトヴェングラーらしい自由なテンポ取りが全開です。盛り上がってくるとアッチェランドし、じっくり聴かせるところは思い切り遅くし、最後は古楽器演奏よりも早い爆速テンポで終わります。こんな味わい深い演奏はフルトヴェングラー以外にはありません。超名盤です。正直、フルトヴェングラーで慣れてしまうと他の演奏が聴けなくなってしまう位、凄いです。
ヘレヴェッヘ=シャンゼリゼ管弦楽団
ヘレヴェッヘ=シャンゼリゼ管弦楽団の録音は、古楽器オケの中では抜きんでた名演奏です。単なる古楽器での録音というだけでなく、ヘレヴェッヘの円熟とこの曲への思い入れが詰まった名盤です。切れ味鋭くテンポは躊躇(ちゅうちょ)ない速さですが、集中力が高く情熱に溢れていて速すぎるとは感じません。
第1楽章はpからクレッシェンドしてくるとすぐにシャープでダイナミックで圧巻な演奏となり、この時点でもう引き込まれてしまいます。細かいアーティキュレーションなど古楽器らしいですが、それより強く感じるのはベートーヴェンらしい意思の強さです。爆発的ともいえるクレッシェンドとダイナミックな演奏に圧倒されます。第1楽章はベートーヴェンのソナタ形式の曲としても充実した名作なわけですが、こんな演奏なら何度でも聴いても飽きない名演です。第2楽章も出だしのシャープさ凄いです。アクセントを上手く利用して、テンポは速めですが弦には厚みがありリズムに重さが感じられ、凄く密度の濃い演奏です。
第3楽章も速めのテンポです。アダージョとアンダンテの組み合わせなので、そこまで速くて良いのか?という気もしますが、テンポが速いことで変奏曲としての見通しの良さを感じます。味わいもありますし、変奏や対位法的な動きがパトス(感情表現)に埋没せずに分かり易く聴こえるのが良い所です。そんな工夫があったのか、と気づく新鮮味があります。
第4楽章の冒頭の不協和音綺麗に響き、回想とレチタティーヴォの部分はさらっと演奏しています。あっというまに『歓喜の歌』のカノンに入ります。テノールが入った後は、少しテンポを落とし、じっくり聴かせてくれます。合唱が入り充実感が増していきます。でもそこまでダイナミックではなく強いアクセントをつけたりはしていないですね。6/8に入るとかなり速くなります。オケのみの間奏部分はかなりシャープでダイナミックです。トロンボーンが先導するコラールは柔らかさがあり、合唱の後、テンポを落としてじっくり聴かせてくれます。ドッペルフーガは遅いテンポでモダンオケよりも遅いテンポかも知れません。終わりに向かってスケールが大きくなっていきます。独唱の4重奏もじっくり聴かせてくれます。
非常に内容が濃く密度が高いディスクで、非常に情熱的で感動的な名盤です。古楽器オケで第九を聴いたことが無い方は、是非、この録音で聴いてみることをお薦めします。賛否両論あると思いますが、第九に対する認識が変わってしまう位、聴く価値のある名盤です。
ガーディナー=オルケストル・レヴォリュショネル・エ・ロマンティク
古楽器オケのパイオニア、ガーディナーの第九です。もう新しい古楽器演奏は沢山ありますし、ヘレヴェッヘ=シャンゼリゼ管弦楽団も素晴らしいしい十分でしょう、と思いましたが、聴いてみてやはりこの演奏は外せないと思いました。古楽器のベートーヴェンを聴くなら今でも欠かせない、偉大な全集ですね。
第1楽章は凄くシャープでテンポもとても速いです。それをダイナミックに演奏するわけで、弦楽セクションは超絶技巧ですね。スリリングで速いほうがいいと思わせてくれます。力強く充実した演奏です。第2楽章も同じ方向性ですね。リズミカルでダイナミックですが余計な力は入っていないので、小技も効きます。
第3楽章は少し遅めです。古楽器らしい透明感のあるサウンドで、意外にゆったりと聴けます。味わいも豊かです。木管やホルンの響きが古楽器らしい木目調なのも良いですね。変奏も楽しげに弾いているのが分かります。
第4楽章は冒頭からあくまでダイナミックです。シャープですが不協和音はそのまま響かせています。管弦楽のみの『歓喜の歌』も美しく、最後はかなりダイナミックに盛り上がります。ガーディナーはリズムに非常に鋭敏で、少しの変化も逃さず聴かせてくれます。6/8になると、どんどん前に進んでいきます。管弦楽のみの間奏もかなりの迫力と超絶技巧です。ドッペルフーガ付近は少し遅めです。といっても、このテンポでも低弦は凄いことになっていますけど。最後はまたテンポアップして行きます。最後は少し遅いですが、スコアを見ると凄いことになっているので、基本的に超絶技巧であっても、弾けるテンポは超えないようにしているのでしょうね。
ガーディナーは奇を衒うことなく真摯に演奏しています。この第九のリズムに対するヴォキャプラリーは『英雄』以上で、充実した名盤です。
小澤征爾=水戸室内管弦楽団
小澤征爾と水戸室内管弦楽団の演奏です。水戸室内管は常設オケですので、アンサンブル能力は年1回のサイトウキネン・オーケストラより上です。人数も少なめなので、弦楽セクションのレヴェルの高さは世界でも有数です。管楽器も昔、フィリップスで発売されていたラヴェルなどの頃に比べて、大分レヴェルアップしてきています。
この第九は小澤征爾の体力を考えて、コンサートでは第1楽章、第2楽章はホルン奏者のパボラークが指揮を担当しています。第3楽章、第4楽章を小澤征爾が指揮しています。CDでは第1楽章、第2楽章は別途セッション録音されていて、全ての楽章を小澤征爾が指揮しています。
第1楽章は小澤征爾らしい力強さもありますが、円熟した味わいがあります。セッション録音のほうが力強さがあり、充実したソナタ形式を堪能できます。第2楽章も意外にシャープでリズミカルです。水戸室内管の演奏はハイレヴェルです。第3楽章は、心持ち遅めのテンポで進んでいきます。水戸室内管の弦楽セクションは細かなニュアンスをつけて非常にクオリティが高いと同時に味わいがあります。やはり無観客の第1楽章、第2楽章とは違いますね。味わいの深みが増しています。小澤征爾はライヴで実力を発揮するタイプですからね。
第4楽章は鋭い不協和音から始まります。ティンパニはかなり硬めの撥を使って効果的なアクセントをつけています。テンポは遅めで丁寧です。「歓喜の歌」は心持ちじっくり歌っていて味わい深いです。テノール・合唱が入ってくると、そのレヴェルの高さに釘付けになります。合唱は少数精鋭でまさに天上の合唱で、遅めのテンポでじっくり味わえます。
コラール~ドッペルフーガは合唱を十二分に味わえる特に素晴らしい部分です。その後も落ち着いたテンポでその美声を心行くまで楽しませてくれます。もちろん、盛り上がる所は盛り上がりますが、熱狂という所までは行きません。その代わりに最後まで高いクオリティを失わず、最後の目まぐるしいオケも綺麗に弾けるテンポで終わります。それでいて会場もとても盛り上がっています。CDで聴いても充実感の高い演奏です。
後半は、遅めのテンポになっていますが、基本的な方向性は2002年サイトウキネン盤と大きな違いはありません。そういう意味で小澤征爾の目指してきた第九はサイトウキネン盤でほぼ完成したのだと思います。
この水戸室内管盤は、小編成ならではのクオリティの高さと、小澤氏の円熟の度合いが増したことが、はっきりと聞き取れる名盤です。ただ、セッション録音とライヴとの差が結構あるので、椅子に座って指揮しても全曲ライヴにできなかったのかな、とは思います。
ネルソンス=ウィーン・フィル (2018年)
新進気鋭のネルソンスとウィーンフィルの2018年録音の新しい第九です。録音が新しいため、音質は素晴らしいです。残響もあり、聴き易いです。
第1楽章はテンポは中庸でしょうか。特別に尖ったところは無さそうです。こういう普通の演奏もいいですね。少しスケールが大きめで、ダイナミックさもありますが、カラヤンのような凄みはなく、普通の演奏です。日本人が聴いても十分理解できるし、納得もできる充実感のある演奏だと思います。第3楽章は落ち着いたテンポですが、平坦になってしまわないように、上手く目立たないようにテンポを動かしています。変奏では、細かいニュアンスもあり、聴こえにくい声部もきちんとまとめています。適度に感情も入っていて充実感もあります。
第4楽章は不協和音が聴こえる様に入りますが、それほどダイナミックではないですね。レチタティーヴォのところは、あまり力を入れず、すぐに終わってしまう感じです。『歓喜の歌』がオケで出てくるところはなかなあ雰囲気を出しています。細かいアンサンブルまで完璧で細部まで自然でしなやかです。合唱が入るとダイナミックになってきて、盛り上がってきて充実感があります。6/8はかなり盛り上がり、オケの間奏も凄みがあります。その後の合唱も充実感があります。コラールも良いです。力強い男声、天上の音楽のような女声、合唱のレヴェルも高いです。ドッペルフーガもとても良いテンポ設定です。最後もスタンダードなテンポ設定で細部まできちんとした演奏を繰り広げています。
全体的に、現代の真面目な指揮者が普通にやるタイプの第九の演奏で、それをレヴェルアップしたものと考えて頂ければいいか、と思います。フルトヴェングラー盤やカラヤン盤のような特別さを感じる演奏ではありませんが、いろいろな要素のバランスが良く年末に聴くにはちょうど良さそうですね。
ショルティ=シカゴ交響楽団 (旧盤)
ショルティ=シカゴ交響楽団は最近見直されてきて評判が良いですね。確かに改めて聴いてみると、気付かされることが多い第九です。このショルティの録音は、第九のスコアをほぼ完全に演奏した名盤です。録音も素晴らしいです。ショルティの力強さのある指揮のもと、シカゴ交響楽団は全てのパートが聴こえるくらい実直で素晴らしい演奏をしています。この後、同じショルティ=シカゴ交響楽団の組み合わせで、再録音していますが、こちらの旧盤のほうを評価する声が大きいですね。
第1楽章はマッシブな力強い演奏です。カラヤン盤ともまた違った魅力があります。速めのテンポで行くのかと思っていましたが、意外と遅めですね。後半はリズムで躍動感もあり楽しめます。ヨーロッパのオケが多いので、シカゴ響の響きはすっきりしていて、また良いです。重厚なシカゴ響から小気味良さのある響きを引き出せるのはショルティの凄さですね。
第2楽章は、第1楽章と大差ないかと思いきや、意外に面白く聴けます。表現のヴォキャブラリーが多いと感心します。第3楽章は、遅めのテンポですが、神妙とか感動的な演奏とは違って肩の力を抜いて聴ける演奏です。いろいろな音が聴こえてきて面白いです。そんな動きがあったのか、と新たな発見があります。結構、味わい深さもあります。こんなに味わい深い演奏だったのは意外でした。
第4楽章の冒頭はレチタティーヴォでなかなか歯切れのよい表現が多いです。テノール、合唱が入ってくるとダイナミックになってきますが、歯切れが良いので、気持ちよく聴けます。6/8のオケの間奏は迫力があって聴きものです。コラールも良く、合唱のレヴェルは高いですね。男声と女声の位置づけがあまり変わらないので、天上から女声が響いてくる感じは少ないですが、筋肉質なドッペルフーガは聴き物です。少し速めのテンポとマッシヴなリズムで最後まで行きます。
ショルティらしいとても清々しい名盤です。
M.T.トーマス=サンフランシスコ交響楽団
M.T.トーマスとサンフランシスコ交響楽団の録音は、ピリオド奏法や古楽器オケともまた違った、楽譜に忠実な演奏です。ライヴですが2012年と新しいため高音質です。基本的にシャープなサウンドで、長い演奏の伝統のあるヨーロッパのオケと異なり、サンフランシスコ交響楽団は非常に上手い一方、ナチュラルな演奏スタイルを持っています。M.T.トーマスは、スコアの細かいところまできちんと見極めて再現しています。非常に知的にまとまっていて、充実感があります。
第1楽章はドイツ的な響きはありませんが、シャープで透明感の高い響きで、知的で整理された演奏を聴くことが出来ます。強い感情が入ることはありませんがツボはしっかり押さえていて、下手なヨーロッパのオケよりも新鮮で聴きごたえがあります。音楽自体が語っているのかも知れません。第2楽章も同様でテンポは速くも遅くもなく、しっかりリズムを刻んでいます。トリオに入ると大分テンポアップして、古楽器オケ並みにどんどん前に進んでいきます。
第3楽章は透明感のある響きで、かなり遅めのテンポで味わい深いですね。管楽器のソロも上手いですし。テンポはほぼ一定でルバートもあまりかかりません。途中、弦が動き始めるとテンポがアップします。変奏の面白さを上手く活かしています。トランペットの後の余韻も適度に活かして味わい深さが良く出ています。
第4楽章の冒頭は不協和音を活かしています。レチタティーヴォのテンポは中庸で丁寧です。テノールや合唱が入っても盛り上がり過ぎずに、落ち着いて丁寧に演奏しています。管弦楽の間奏も落ち着いています。コラールは大分ダイナミックです。とはいえドッペルフーガも知的な演奏です。知的さを失わない程度にパッションをコントロールしつつ、最後まで合唱も綺麗でオケのアンサンブルが雑になることはなく、しっかり演奏しきっています。
情緒や感情ばかりの第九に飽きた人には、ショルティ盤と共にとてもお薦めです。マッシヴなショルティ盤とは大分違いますが、どちらも聴きごたえがあります。
フルトヴェングラー=バイロイト祝祭管弦楽団 (バイエルン音源)
フルトヴェングラーバイロイト祝祭管弦楽団の名盤です。「第九」といえば、バイロイトの演奏、というくらい有名です。戦後、復活された直後の1951年の演奏がやはり力強く感動的です。ちなみにバイロイトはもう一つあります。バイロイト1953年の演奏です。どちらも良いですが、まずは1951年ですね。ウィーンフィルやベルリンフィルとの演奏も名演ですが、迫力とか気合いでいえば、やはりバイロイト盤のほうが上です。ちなみにバイロイトの第九は、2000年代に入って、本物が発見され、いままでのCDは実はリハーサルだった可能性が高いということです。
世紀の再発見!待望の一般発売!
バイエルン放送音源による「バイロイトの第九」登場!
録音:1951年7月29日バイロイト音楽祭ライヴ・音源:バイエルン放送
「レコード芸術」2007年9月号(※詳細はP.70~74、P.211~214をご参照ください)にて大きく取り上げられた、フルトヴェングラー・センター盤「バイロイトの第九」。そもそも会員向け頒布という性格のため、同センターへの入会が必須条件という特殊CDでしたが、弊社とORFEOとの粘り越しの交渉の末このたび市販流通化が実現しました。EMIとはちがう、フルトヴェングラー1951年「バイロイトの第九」のまったく新たなソース。演奏内容についてはすでに折り紙つき。このバイエルン放送音源による録音の意味はいくら言葉を費やしても尽くせません。ぜったいに、間違いなく、ことしの第九はこれでキマリといえましょう。
ADD;モノラル [コメント提供;(株)キング・インターナショナル]
タワーレコード
それでも、あれだけ凄みがあるわけですから凄いですね。リハーサルは、会場の響きを確認したり、と言ったことが目的で、気合は本番に取っておく場合が多いと思いますが、バイロイトの場合はリハの段階から、それだけ凄みのある演奏だったわけです。
第1楽章は、今までと印象は変わりません。バイロイト祝祭管弦楽団のヴィブラートが強く、ダイナミックな響きはきちんと捉えられていて、充実した演奏です。特に後半盛り上がってくるのはライヴゆえでしょうか。
第2楽章もダイナミックでテンポを見てもフルトヴェングラーらしいですね。第3楽章はウィーンフィル盤などと比べても味わいが深いと思います。基本的にはオケの違いだと思いますけど。
第4楽章は録音の悪さはEMI音源と変わりませんが、縦の線がきちんと合っていて、これが普通のライヴ録音だと思います。オケもきちんと採れていますし合唱もばっちりです。ただ、EMI音源は上のほうから合唱が響いてくる感じがあったのに比べ、この音源では普通に同じ舞台上にいるのが分かります。残響が減っていたりして、神々しい部分も少なくなっている気がします。最後の畳み込むような盛り上がりはバイロイト独特で、かなりの迫力です。
最後の拍手はありません。録音の問題ですが、音の密度もEMI音源のほうが濃く感じます。
フルトヴェングラー=バイロイト祝祭管弦楽団, 他(EMI音源)
リハーサルかも知れないと難癖をつけられた格好のバイロイト第九のEMI音源ですが、長年名盤として親しまれてきたのは意味があってのことです。仮にリハであってもこれだけ凄い演奏なんですから。
第1楽章はバイロイト祝祭管弦楽団のダイナミックな響きが印象的です。弦楽セクションなどのまとまりはウィーンフィル盤のほうが綺麗ですが、バイロイト祝祭管弦楽団は迫力があります。ウィーンのムジークフェラインとバイロイト祝祭劇場の違いもあると思います。バイロイト祝祭劇場は中に入ったことはありませんが、外から見ても木造の建物で響きにこだわったホールという印象でした。本当に音響がいいようですね。第2楽章もダイナミックです。ウィーンフィルとはテンポが少し違います。トリオはバイロイトが遅いです。ウィーンフィル盤のほうが、すっきりしています。第3楽章は遅いテンポで、ウイーンフィル盤より輪郭がはっきりしています。大きなヴィブラートもこのバイロイト祝祭管弦楽団の特徴ですね。遅いテンポで味わい深い演奏です。
第4楽章は冒頭からレチタティーヴォは荒々しさのある迫力です。テノールは良いです。合唱は少しズレがありますね。これはバイロイト祝祭劇場の音響の問題かも知れません。オケピットが客席の下にあるので、時間差があるらしいです。第九ではオケも合唱も当然舞台上にいるわけですが、合唱が随分遠い感じで、6/8に入ってもテノールは合わせるのが大変そうです。マイクの位置や、オケピットが残響に悪さをしているのかも知れませんねぇ。その後のオケの間奏は凄い迫力です。ドッペルフーガに入ってフルトヴェングラーは結構速めのテンポで演奏しているので、舞台上ではあまり実感は無いのかも知れませんけど。
最後に向かって、どんどんテンションがアップしていきます。テンポもどんどんアップして行き、大迫力です。最後の速さは半端じゃないです。
フルトヴェングラー=ベルリン・フィル
フルトヴェングラーには、戦時下にあたる1942年の第九もあります。手兵ベルリン・フィルを振ったもので、さぞ録音が悪いだろう、と思いきや意外にしっかりした録音です。
アバド=ベルリン・フィル
アバド=ベルリンフィルのベートーヴェンは全体的にシャープでダイナミックで、テンポが速めであり、ピリオド奏法の影響を受けています。ただ曲によって大分違いますし、アバドの視点から必要な所だけピリオド奏法を取り入れています。第九はその中でも特にピリオド奏法の影響が強い方だと思います。ただ、ガーディナー盤やヘレヴェッヘ盤のように極端な速いテンポではなく、少し速いという程度で、シャープな印象があります。
第1楽章から速めでシャープさのある演奏です。リズムをしっかり刻み、テンポを詰めていって情熱的に盛り上がります。聴いていると、第九はこんなにもリズミカルな音楽だったんだな、と目から鱗が落ちる思いです。細かい所にリズミカルな合いの手が入っている個所もあります。速めのインテンポで密度が高く、充実した演奏になっています。聴いていてソナタ形式をよく認識できます。第2楽章は非常にシャープでティンパニも思い切り鋭い音で叩いています。トリオは思い切ったテンポですね。第3楽章もかなり速いテンポでそのままアゴーギク少な目で最後まで通しています。音が薄手で変奏が手に取るように分かります。
第4楽章は速めのテンポで、少し繊細に始まります。不協和音を思い切り鳴らしたりはせず、レチタティーヴォ~オケの歓喜の歌までは、あっという間です。テノールが入ると雰囲気が少し変わり、シャープさのある合いの手が入りますが、テンポも落ち着いてきます。合唱も上手いですね。オケの間奏はかなりシャープで迫力があります。
後半も結構速めで、ダイナミックな盛り上がりもあり、そこではさらにアッチェランドしていきます。テンポの変化が大きな演奏で、かなり熱気もあります。最後は、モダンオケ風なテンポの速さで、熱狂的に盛り上がって終わります。
古楽器オケの演奏をいくつか聴いた後でも、なお新しい発見のある名盤です。
ベーム=ウィーン・フィル (1970年)
カール・ベームとウィーン・フィルによるの第九です。演奏のクオリティが高く、ゴシック建築のような重厚さのある名盤です。
第1楽章、第2楽章のテンポは少し遅めです。ウィーンフィルらしいふくよかさがあり、それに重厚感が加わっています。凄くスケールの大きな演奏で、フォルテでのテンポが遅めですね。響きはウィーンフィルの柔らかさがありますが、なかなか峻厳(しゅんげん)で構築力のある演奏です。盛り上がりはフルトヴェングラー盤を連想します。第3楽章も遅めのテンポでじっくり聴かせてくれます。響きがとても美しく完成度が高いです。
第4楽章は冒頭は普通のテンポで始まり、完成度の高い演奏を聴かせてくれます。響きの美しさはこのページの名盤の中でも特に抜きん出ています。合唱のレヴェルが非常に高く綺麗にまとまっています。6/8はゆっくりめで、オケの間奏は少し遅めで演奏され丁寧です。コラールは壮大で、盛り上がるほどにテンポを落としていくので凄いスケールになっていきます。女声は本当に天上から歌っているように感じられます。ドッペルフーガもそのスケールのまま演奏されていきます。凄い完成度の高さを感じますね。そのまま最後まで演奏しきります。
峻厳さと完成度の高さがある名盤です。ベームの演奏が目指す方向とリスナーの好みがマッチすれば、完成度が高いだけに凄い名演だと思います。
カサド=フライブルク・バロック・オーケストラ
2019年録音の古楽器による第九です。フライブルグ・バロック・オーケストラは、ドイツの3大バロックオケの一つで、非常に高いクオリティの演奏をします。ここでは、弦のプルトを増やし、管楽器・打楽器を追加して演奏しています。
第1楽章は独特なリズミカルな演奏で、オケのほうも響きの厚みが感じられません。カサドはスペインの指揮者ですが、独特なリズムの感性を持っていますね。特に裏拍を徹底して強調しています。最近の古楽器演奏は裏拍を上手く使っている演奏が多いですが、カサドは徹底しています。それと少し色彩的な所があり、独特な歌いまわしも意外な表現がどんどん出てきて全く飽きさせません。第2楽章になると慣れてきたのか、独特の響きは気にならなくなります。この楽章は速めですが、普通のテンポです。大事な所はしっかり演奏しているので、物足りない所はありません。第3楽章も速めのテンポながら、とても味わいのある名演です。古楽器演奏のせいか、管楽器は少し曇った音色になっていますが、これも独特の味わいに繋がっています。アーティキュレーションはユニークですがとても面白いです。
第4楽章は鋭い不協和音から始まります。レチタティーヴォの自由なテンポ取りと、アーティキュレーションの面白さ、バロック演奏の基準で考えても音の長さを思い切り短めにしています。「歓喜の歌」が始まると、普段聴いているような演奏スタイルで、こういう大事な所は奇を衒わずにしっかり演奏しています。
テノールが出てきてもユニークなスタイルは変わりません。合唱のレヴェルも高いです。伴奏のオケはユニークさがありますが、歌手や合唱は普通に上手く、聴いていて充実感があります。オケの間奏はテンポアップしてスリリングに聴かせてくれます。コラール~ドッペル・フーガは遅めでじっくり聴かせてくれます。四重唱の所は遅いテンポでじっくり味わい深く聴かせてくれます。その後、最後に向けてまたテンポアップして、凄い熱狂の中、曲を閉じます。
第九を聴いた充実感もある面白い演奏です。思うにカサドという指揮者は、独特のセンスで、お客さんを満足させる演奏を知っている指揮者だと思います。バロック~モダン的な奏法まで上手く使い分けた充実感のある演奏です。
鈴木正明=バッハ・コレギウム・ジャパン
第1楽章は標準より少し速い程度のテンポです。古楽器オケとは思えない機能性で、とても技術的に素晴らしいです。音色はモダン楽器のような澄んだ音色です。もちろん古楽器奏法なのは良く聴こえます。新しくて録音が非常に良いせいもあるかも知れません。基本は日本人的というか、ダイナミックさのある第一楽章です。
第2楽章は鋭い弦楽器が印象的です。割とモダンでもあるテンポで演奏しています。
現在の古楽器のテンポはガーディナーが譜面に書いてあるメトロノームテンポで演奏したことに源流がありますが、やはり速すぎですよね。曲によりますけれど。それまでのフルトヴェングラーらのテンポはワーグナーの影響が大きく遅すぎることは事実ですが、メトロノームテンポが正しいか否かは分かりません。
そもそも当時のオケが、そんな速いテンポで演奏できるほど上手いとも思えないです。第九に至っては編成が大きいこともあり、プロ・アマの混成だったことを考えれば尚更ですね。
第3楽章もテンポは少し速い程度です。第3楽章は変奏曲であるため、テンポが速めな方が全体が良く見えて分かり易くなるメリットはありますけど。
第4楽章になるとテンポは普通にモダンと変わらないです。古楽器の響きが良いですね。ライヴで良くここまできれいにアンサンブルできるものですね。不協和音もダイナミックに演奏していますが、汚くは聴こえません。
テノールは、少し独自の装飾も入れてますね。合唱は、縦の線も声の質も、驚くほど揃っています。とてもライヴとは思えません。オケの力強い間奏のあと、コラールはとてもきれいな合唱を聴くことが出来ます。人数も絞っているとは思いますが、これだけきれいなコーラスは、なかなか聴けないと思います。ドッペルフーガはどの声部も天上の響きに聴こえます。
最後はダイナミックに盛り上がり、モダン演奏と変わらない終わり方です。
素晴らしい演奏ですが、どの瞬間も日本人的な丁寧さを失わない演奏です。ドイツ語の発音などよく分かりませんけれど、最後のほうで盛り上がっても丁寧さがあって、それは小澤盤もそうなのですが、欧米の指揮者やオケとは少し違う所です。これだけ日本の演奏レヴェルが上がってくると、それも悪いことでは無いのかも知れません。
パーヴォ・ヤルヴィ=ドイツ・カンマーフィル
P.ヤルヴィ=カンマーフィルのピリオド奏法の録音です。CDとDVDもあります。DVDだとカンマーフィルの楽器編成が大枠わかります。ホルンはモダン楽器、木管もモダン楽器、Tpだけ古楽器です。Tpは管が長く、音が鋭いのが特徴で、古楽器になるととても難しい楽器になります。Tpが古楽器なのでティンパニも古楽器にすれば軍楽隊風になりますが、ティンパニはモダン楽器です。バスドラムは古楽器に見えます。第九はトロンボーンがハーモニー楽器として使われていないのですが、実は古楽器のトロンボーンは音が細くハーモニーが苦手です。第九は第4楽章で合唱を先導するだけなので、その時に分かりますね。
第1楽章はテンポは速いので、弦楽器は大変そうですが、演奏は自然な感じで、普通のモダンオケの演奏を聴いているような雰囲気です。やはりアクセントをつければモダン楽器の響きになりますし、演奏スタイルがモダンのシャープな演奏とあまり変わらず、ノリントンらと違いそこまで個性的でも実験的でもないですね。でも、とてもシャープで力強い名演です。テンポが速い分はスタイリッシュに聴こえます。第2楽章もテンポ意外に取り立てて大きな差はないです。トリオもそうですね。力強さがあり、スタイリッシュです。
第3楽章も意外以外は普通で『運命』のような斬新さは無さそうですね。モダン楽器だからか、ヘレヴェッヘのように対位法が良く聴こえるほどの透明感は無いようです。編成の大きさの問題かも知れませんし、『運命』の時と違って、P.ヤルヴィに気合いが入り過ぎているのかも知れません。P.ヤルヴィは特別ピリオド奏法の指揮者では無いですからね。その代わり、ピリオド奏法としてはじっくり聴かせてくれる演奏です。
第4楽章は速いテンポで不協和音もモダンオケ並みに演奏しています。レチタティーヴォはあっという間におわり、『歓喜の歌』に入ります。Tpが入る頃にはダイナミックになっています。冒頭の不協和音が戻り、テノールが入ります。テノールが入るとオケには透明感が出てきて、明らかに響きが変わります。6/8は凄く速いです。オケのみの間奏は凄い迫力で聴きものです。
さてコラール風のところはテンポを落としてスケールがあります。トロンボーンはモダン楽器ですね。ドッペルフーガは遅めのテンポです。スケールが大きくなってくるとモダンとあまり変わらなくなってきます。もっともヘレベッヘも後半は遅かったので、テンポの指示が遅いのかも知れませんけれど。むしろ、さらにテンポを落として壮大な音楽を作り出していきます。この先はモダンと大差ないですね。モダンオケも速いですから。ダイナミックな第九でした。
うーむ、P.ヤルヴィの第九はテンポ以外はモダンオケに近いですね。細かい所で工夫も見られましたが、驚くような新鮮味はないかも知れません。ピリオド奏法のスタイリッシュな第九ですが、テンポと奏法以外はモダンに近いので聴きやすいとは思います。
ハイティンク=ロイヤル・コンセルトヘボウ管
マタチッチ=チェコ・フィル
マタチッチがチェコフィルとライヴ録音した第九です。マタチッチはチェコフィルと良い関係にあって、ブルックナーなどで名盤が残されています。マタチッチが指揮したオケの中で、もっともレヴェルの高いオケの一つだと思います。1980年のライヴ録音で当時東側の技術なので、音質はあまり良いとは言えませんが、聴きやすい音質ではあります。
第1楽章はマタチッチらしい筋肉質な演奏です。特別個性的というわけでもなく、ただ結構推進力を感じます。チェコフィルは木管が良く、味わいがあります。後半になってくると、段々と熱が入ってきてマタチッチらしい盛り上がりで熱演になってきます。第2楽章は速めのテンポです。マタチッチらしい力強さのある演奏です。
第3楽章は素晴らしい演奏です。最初からチェコフィルの響きもあって味わい豊かで、曲が進むにつれて色々な色彩を放っていきます。ヨーロッパの少し田舎の自然の多い地方の雰囲気ですね。テンポは遅くはなく、ちゃんと変奏曲として聴けます。後半の盛り上がりは金管を思い切り鳴らして凄いです。
第4楽章の合唱はチェコ語で歌われています。確かに演奏家の名前を見ても全員チェコ系の人のように思います。冒頭からレチタティーヴォにかけてはマタチッチらしいマッシヴな演奏です。「歓喜の歌」に入ると意外に速いテンポで進み、ダイナミックに盛り上がります。さらにテノールが入るとスケールが大きくなりダイナミックに盛り上がります。
ドイツとチェコは隣国ですが、言語は大分違います。不自然とは思いませんが、語調はなんとなくグラゴル・ミサを思い出します。4人の独唱者は言葉が聴き取れるようにしっかり録音されているようですね。マタチッチの音楽作りは東欧系と良く合うのでチェコ語でも良いのですが、オケとのバランスがちょっと不自然かも知れません。オケの間奏はスケールが大きく、かつリズミカルに進みます。
コラールも壮大です。合唱のレヴェルは高く、女声は天上から聴こえてくるようです。ドッペルフーガも迫力ある合唱です。終盤は、かなりテンポが速めになり、パーカッションを派手に鳴らして熱狂的に曲を締めくくります。
マタチッチらしさのある演奏と思いますが、録音が悪いことと、チェコ語の歌唱を大きめに録音しています。考えてみれば、チェコ人向けになんでしょうね。
マタチッチは他にNHK交響楽団ともライヴ録音があります。
マタチッチ=NHK交響楽団
CD,MP3をもっと探す
映像 (DVD, Blue-Ray)
バーンスタイン=バイエルン放送響 (ベルリンの壁崩壊記念)
CD,MP3をもっと探す
楽譜
ベートヴェン交響曲第9番『合唱』の楽譜・スコアを紹介します。


















![ベートーヴェン : 交響曲 第9番 「合唱付き」 (Beethoven : Symphony No.9 / Bach Collegium Japan | Masaaki Suzuki | Ann-Helen Moen | Marianne Beate Kielland | Allan Clayton | Neal Davis) [SACD Hybrid] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51sEIHJ4loL._SL500_.jpg)




![バーンスタイン/ベートーヴェン:交響曲第9番~ベルリンの壁崩壊記念コンサート~ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51j-Xd8bMVL._SL500_.jpg)
![ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 作品125[合唱付] 全音ポケットスコア](https://m.media-amazon.com/images/I/41z6ZppSqeL._SL500_.jpg)












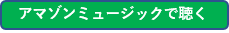
私のお気に入りの第九は、サイモン・ラトル指揮ウィーン・フィルのコンビ(2002年録音)です。メリハリの利いた演奏が、とても心地よく感じられます。
コメントありがとうございます。ラトルは良さそうですね。ウィーン・フィルとの全集を持っているのですが、何故か第九はあまり聴いてませんでした。今度、聴いてみます。私はバーンスタインやフルトヴェングラーも好きですが、ヘレヴェッヘ=シャンゼリゼ管弦楽団が今は一番のお気に入りです。賛否両論ですが、こんな衝撃的な演奏は滅多にないですね。