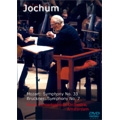アントン・ブルックナー (Anton Bruckner,1824-1896)作曲の交響曲第7番 ホ長調 (Symphony No.7 E-Dur)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。
ブルックナーの交響曲の中でも名作であり、第4番『ロマンティック』と同じ位、聴きやすい交響曲で、ブルックナーの入門者から玄人まで、誰にでもお薦めできる交響曲です。ブルックナー開始(弦のトレモロ)が印象的で生演奏で聴くと何倍も感動する曲です。スコア・楽譜までワンストップで紹介します。
解説
ブルックナーの交響曲第7番 ホ長調について解説します。
交響曲第7番は、1881年9月に作曲が開始されました。ブルックナーは既に57歳です。遅咲きの作曲家ですね。1882年の終わりごろには第1楽章と第3楽章が完成します。そして第2楽章のスケッチを書いている時にワーグナーの訃報が届きます。
敬愛するワーグナーの死
第2楽章を作曲していたブルックナーの元に尊敬していたワーグナーが危篤であることを知ります。そしてワーグナーは1883年2月13日に亡くなります。悲嘆に暮れたブルックナーは第2楽章のコーダに4本のワグナーチューバを使用したワーグナーへの葬送音楽を付け加えます。非常に美しい音楽で、もともと清涼な雰囲気を持つ第2楽章をさらに深みに誘うような音楽です。
この葬送音楽は、1896年10月15日カール教会でのブルックナーの葬儀の際、編曲されて宮廷歌劇場の金管奏者により演奏されました。
初演の大成功
1883年9月5日に全楽章が完成します。初演は1年以上経った1884年12月30日です。アルトゥル・ニキシュ指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団によりライプツィヒ歌劇場で行われました。この初演はブルックナーの交響曲では初めて、大成功をおさめます。指揮者ヘルマン・レヴィ(1839年-1900年)の推薦よりバイエルン国王ルートヴィヒ2世に献呈されました。
そしてブルックナーは交響曲作家としての地位を確立します。といっても、ブルックナーの交響曲はウィーンフィルなどで初演されてきたのですから、元々そこまで評価が低いとは思えませんけれど。
ブルックナー交響曲第7番はブルックナーの三大交響曲の最初の一曲です。第7番、第8番、第9番とどれをとってもそれぞれ個性を持った名作で、三大交響曲がこの第7番で始まったことは幸運と言えるかも知れません。
ハース版とノヴァーク版
交響曲第7番はブルックナー自身による改訂があまり行われていない交響曲です。後世の指揮者は色々変えてしまいましたが、ブルックナー自身のいわゆる「原典版」が大成功を収めたので、改訂による混乱はあまりありません。ハース版もノヴァーク版もブルックナーの「原典版」を元にしていますが、ハースは第2楽章のシンバルとトライアングルについて疑問を抱きました。そこで、ハース版はシンバルとトライアングルは入れず、参考として載せています。
フルート×2、オーボエ×2、クラリネット×2、ファゴット×2
ホルン×4、トランペット×3、トロンボーン×3、ワグナーチューバ×4(テノール×2とバス×2)、コントラバス・チューバ
ティンパニ、シンバル、トライアングル、
弦五部
おすすめの名盤レビュー
それでは、ブルックナー作曲交響曲第7番 ホ長調の名盤をレビューしていきましょう。
ブロムシュテット=ドレスデン・シュターツカペレ (1980年)
ブロムシュテット=ドレスデン・シュターツカペレの演奏は、響きの良さと自然美で昔から定番とされている演奏です。初めてブルックナーを聴く人にもお薦めできます。まさにドイツの深い森のイメージです。深い森とか、黒い森と言われていますが、日本の例えば富士の樹海のほうがずっと深い森です。なので、ドイツの「深い森」は適度に深い森でロマンティックなイメージがあります。まさにこの曲のブルックナー開始の弦のトレモロが生み出す響きや朗々と歌う弦楽器やホルンがイメージにピッタリ合います。
第1楽章は少し速めのテンポですが、ドレスデン・シュターツカペレの響きを最大限に活かしています。弦セクションやホルンの響きはまさにドイツの深い森です。あまり暗さやシリアスさがなく、あくまで自然美であってロマンティックであることもこの演奏の特徴です。第2楽章はとても清涼です。人間の精神に深く入り込むようなシリアスさには欠けますが、この澄んだ清涼な感じは、なかなか他の演奏では聴けません。テンポも遅すぎず、爽やかさすら感じます。
第3楽章はテンポが速めでリズミカルなスケルツォです。こんなに聴いていて爽快なスケルツォは他の演奏ではありません。中間部はテンポを落として味わい深いです。第4楽章はテンポが速めで、快活さと透明感のある響きがバランスしています。特別ロマンティックさや自然美を目指しているわけでは無く、真摯に高いクオリティで演奏していて、結果としてロマンティックに聴こえる演奏です。熱気やダイナミックさもあり、強奏の部分は思い切り鳴らしています。
ブルックナー交響曲第7番の魅力を凝縮したような名盤です。はじめて聴く方もこの曲の魅力が良く理解できると思います。
ヴァント=ベルリン・フィル (1999年)
ヴァントが円熟した時期にベルリン・フィルに客演した際の録音です。手兵の北ドイツ放送交響楽団との重厚な演奏も素晴らしいですが、ベルリン・フィルはやはりオケのしての機能性が違います。響きにとても透明感があります。録音は1999年のデジタル録音で、解像度も良く優れた音質です。
第1楽章はベルリン・フィルのレヴェルの高い弦の透明感が高く、繊細なトレモロから始まります。この曲はコンサートで聴くとブルックナー開始の効果を堪能出来て実演が有利なのですが、それに近い空気感を味わえます。ヴァントは円熟して、テンポ取りはスタンダートですが懐の深い指揮ぶりです。落ち着いた中にも一定の緊張感が貫いていて、弦の音色やソロのアンサンブルなど、神々しさも感じられます。じっくり音楽に浸かることが出来ます。終盤のクレッシェンドは非常に透明感があり、雲間から陽光が差し込むようです。
第2楽章は透明な弦がしなやかに歌いこんでいきます。テンポはヴァントとしては少し速めと思います。ベルリン・フィルはとても自然な演奏を繰り広げています。フルートの音色の素晴らしさは実際聴いてみてください。静かで繊細な空間で、こういう演奏はなかなか聴けないと思います。
ヴェントとベルリン・フィルの録音は、深みや味わいもありますし、オケの機能性もハイレヴェルで、録音も良いという3拍子揃ったディスクです。
ヨッフム=アムステルダム・コンセルトヘボウ管 (1986年来日ライヴ)
ヨッフムはベルリンフィルとブルックナー全集を収録したり、ブルックナーに対しても力を入れて演奏していました。ただヴァントなどと違い、テンポの変化が大きな演奏スタイルでした。しかし、晩年になり円熟して深みが増してくるとヨッフムのブルックナー演奏も誰もが認める名演となりました。特にこの来日時のアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団との演奏は、素晴らしく心が洗われるような名盤です。
第1楽章はアムステルダム・コンセルトヘボウ管の弦の響きが清涼で、まさに心が洗われるような響きです。ブルックナー7番はコンサート会場で聴くと全然違い、弦のトレモロが非常に美しいので、恐らく生演奏で聴いた人は相当感動したでしょうね。ヨッフムのテンポは若いころより遅めです。テンポの変化は結構あり、演奏スタイルを変えたわけでは無いと思います。第2楽章になるとテンポを落とし、さらにグッと深みが増します。人見記念講堂も木の響きの良いホールですが、まるで教会で演奏しているかのようです。清らかさと自然美を感じます。後半、どんどん深みを増していき、ワーグナーのコラールに自然に入っていきます。いつの間にか時間の経過を忘れて音楽に浸かっています。
第3楽章も遅めのテンポですが、アクセントがついていてリズムはしっかりしています。中間部でもあまりテンポを変えなくて良い位、遅めのテンポです。第4楽章は透明感のある弦の響きから始まります。ヨッフムらしい快活な演奏で、フィナーレもとても盛り上がります。
ヨッフムは様々なオケとの演奏が出ていますが、録音の音質も演奏内容もこの来日時の演奏はとても素晴らしいです。映像もリリースされています。
カラヤン=ウィーン・フィル (1992年)
カラヤン=ウィーンフィルの演奏は、いわゆるブルックナー指揮者の演奏と大分違います。カラヤンはブルックナーをロマン派音楽というより、絶対音楽としてみていて、スコアを深く読みこむことに力を入れています。緊張感のある演奏を繰り広げています。自然が主題の一つでである第7番もそのスタイルの演奏をしています。オケがウィーン・フィルで艶やかな響きを引き出しています。
第1楽章からまるで教会にいるような雰囲気です。ウィーン・フィルは磨き抜かれた艶やかな響きが美しいです。きっとコンサート会場に居た人は凄い壮麗な響きに包まれたのではないかと思います。それでも中盤以降はウィーン・フィルが作り出した響きや木管のソロなど、深みが感じられ聴き所も多いです。第2楽章はさらに美しい響きが印象的で、天上の音楽のようです。円熟してきたとはいえ、根底に厳しさのある音楽です。後半になると自然と深みを増していきます。ウィーンフィルの弦のモチーフは格調が高い響きです。そして頂点ではハース版ではオプションのシンバルとトライアングルが入ります。
第3楽章は遅めですけどリズミカルです。中間部は壮麗で聴き物です。第4楽章は意外に軽快に始まり、少しホッとしますね。結構、緊張感が強い演奏です。金管のユニゾンは思い切り鳴らして壮麗です。最初から最後まで一定の緊張感を維持していて、それがこの演奏の壮麗さや天上の響きにつながっていると思います。
このCDは他の演奏とは方向性が根本的に違いますが、カラヤンの方向性も一つの答えだと思います。
マタチッチ=チェコ・フィル
マタチッチとチェコ・フィルの録音です。1967年の録音ですが音質はとても良くpp~金管が咆哮するレヴェルまで良好に録音されています。マタチッチは旧ユーゴスラヴィアの出身ですが、一流オケの指揮台に立ったのはチェコ・フィルとウィーン響あたりで、日本でとても人気がある割に欧米ではそこまで評価されていないのかな、と思ってしまいます。しかし、マタチッチとチェコ・フィルはとても相性が良く、ブルックナーはどれも名演です。その中でも7番の演奏は人気が高いですね。管理人は5番が一番良いと思います。
第1楽章の冒頭から神々しく始まります。マタチッチらしい力強さも健在です。神々しさを保ちながら、盛り上がりでは金管が思いきり咆哮して凄い迫力です。かなりテンポも動かしていて、ワーグナー的な所もありますが、それでも自然に聴こえる所がマタチッチの良い所です。ラストは壮大に盛り上がり、ダイナミックに締めくくります。第2楽章は味わいのあるチェコ・フィルの弦で始まります。チェコ・フィルのコクのある音色を活かして、段々と深みに入っていきます。終結部の葬送音楽はとても神々しいです。
第3楽章はリズミカルで力強い演奏です。この頃のチェコ・フィルの機能性を活かして、ダイナミックで爽快な音楽を作り上げています。木管の音色も印象的です。第4楽章は落ち着いたテンポで、ワーグナーを思わせるような表現です。作為的な表情づけは無く、とても自然に聴こえます。マタチッチはブルックナー指揮者である所以(ゆえん)ですね。コラールのユニゾンは力強くリズミカルです。明るく、ダイナミックに盛り上がっていきます。
マタチッチはチェコ・フィルの響きを活かして、濃厚な表現もしています。ワーグナーのようなテンポ設定も、マタチッチがやるととても曲に相応しいものになります。生来のブルックナー指揮者ですね。
クナッパーツブッシュ=ケルン放送交響楽団 (1963年ライヴ)
クナッパーツブッシュとケルン放送交響楽団の名盤です。ウィーン・フィルとの1949年ザルツブルグの名盤もありますが、こちらは1963年ライヴで新しい録音です。クナのブルックナーの中でも特に素晴らしい不滅の名盤で、こちらの方がテンポ取りや表現が自然で、スケールの大きなクナッパーツブッシュらしい演奏です。
遅いテンポのブルックナー演奏のパイオニアですが、この録音は特に素晴らしく、ヴァントや朝比奈隆らに大きな影響を与えていることが分かります。改訂版と言われる楽譜を使っていますが、クナッパーツブッシュが演奏すると不自然さは全くないです。改訂によって少し劇的になっている所もあるので、むしろ相応しい楽譜なのかも、と思ってしまう位です。
第1楽章は遅めで自然なテンポ取りと円熟して枯れた表現の名演です。この時期の演奏は完全に遅いテンポが板についています。素朴さの中にホルンの音色が印象的で、少しワーグナーのオペラようなドラマティックさもあります。第2楽章は少しだけテンポを前に進めて動きをつけています。高弦が神々しく響きます。第2主題の瑞々しく平和な世界はこの演奏の白眉の一つです。とても自然なニュアンスで曲が進んでいくため、聴いていてどんどん引き込まれていきます。やがて、ピークに達すると凄いスケールの大きさで、シンバルなども思い切り鳴らしています。その後のワーグナー追悼音楽はとても味わい深いです。
第3楽章はスケルツォとしては遅いテンポで、いぶし銀の演奏です。アクセントはしっかりついていて劇的な表現もあり、リズミカルさもあります。第4楽章はリズミカルに始まります。テンポの緩急が大きく、他の演奏に比べても特にテンポが遅いです。この楽章でも枯淡の境地が感じられます。ブルックナー・ユニゾンはスケールが大きく、ダイナミックです。緩急を付けながら、遅いテンポでスケールを増していき、圧倒的なダイナミックさで曲を締めくくります。
モノラルのライヴ録音で、歴史的名盤の位置づけではありますが、内容がとても素晴らしく、今聴いてもとても自然で染み入るような味わいのある名盤です。
シューリヒト=ハーグ・フィル
シューリヒトとハーグ・フィルの録音です。ハーグ・フィルはベルギーのハーグのオーケストラです。シューリヒトはベルリン・フィルやウィーン・フィルなど一流オケとのライヴも残していますが、このハーグ・フィルとの録音は昔から定番です。録音はしっかりしたアナログ録音でダイナミックな所では少し荒いですが、十分な音質と思います。無論、リマスタリングやSACD化の効果は高いと思います。レコードで聴くにも良いですね。
第1楽章はシューリヒトらしい少し速めのテンポで、素朴ながらも弦の響きがまとまっており、美しい響きを聴かせてくれます。盛り上がってくるとアッチェランドして白熱してきます。感情表現も素朴ながらしっかりされており、小気味良くまとまっていて、シューリヒトの良さが良く出た軽妙で味わい深い演奏です。こんな自然な演奏はなかなか聴けないと思います。第2楽章はさりげなく始まり、弦セクションの響きが味わい深いです。曲の深みに自然に分け入っていき、時に自然賛歌のような幸福感があります。無理に遅くする所がなく、比較的速めのテンポなので、却って自然な表現で、盛り上がると少しアッチェランドして、白熱していきます。ノヴァーク版のシンバルがとても効果的です。
第3楽章スケルツォはテンポが速くスリリングです。軽快で盛り上がると熱狂の渦という感じです。シューリヒトは聴き所のツボは全て押さえていて、さりげなく絶妙にテンポをコントロールしています。胸が躍るような、ブルックナーのスケルツォはそういう所がありますが、遅いテンポの演奏が多いので、シューリヒトでないと聴けないものだと思います。第4楽章は小気味良くリズミカルです。コラール風の所では金管をかなり鳴らしていますが、粘りが無いので、すっきりしたまま白熱しています。ホルンや木管は雰囲気が良く出ていて、味わい深いです。ラストはダイナミックで速いテンポのまま締めくくります。
スケール感はあまりないですが、金管などかなり鳴らしています。シューリヒトの演奏は何より聴いた後の後味が良いですね。重さが無いので聴き疲れすることもありません。
セガン=モントリオール・メトロポリタン管 (2006年)
セガンとカナダのオケであるモントリオール・メトロポリタン管の演奏です。若いセガンの実力と感性、カナダのオケらしく透明感の高い響きが相まって、かなりの名演奏となっています。並みいる巨匠の演奏と比べても、また違った魅力が前面に出てきています。高音質で立体的な音響も素晴らしいです。
第1楽章は透明感が高く凛とした響きで、細かく丁寧なテクスチャで音楽を作り込んでいます。落ち着いた中にもただ譜面通りに演奏したのではなく、あくまで格調高い演奏ですが、ストーリー性も感じられます。遅めのテンポでスケールも大きいです。
第2楽章はじっくりと深みのある音楽で始まります。弦の響きも厚みとコクがあって味わい深いです。滋味に溢れています。深くて穏やかな世界観で、若い指揮者という感じもしないですが、円熟した巨匠とはまた違ったフレッシュさが同居しています。後半は柔らかい音色で深みが増し、感情的にも盛り上がっていきます。ワーグナー・チューバも味わいのある音色です。金管はしなやかな音色でクオリティも高いです。フルートなど木管の音色も素晴らしく、ドイツのオケとはまた違った少し色彩感のある味わいがあります。
第3楽章はリズミカルです。透明感と色彩感もあって気持ちの良い演奏です。トランペットなど金管の上手さも光ります。中間部はじっくりと弦を厚めに響かせて歌わせています。第4楽章は小気味良いリズミカルな演奏です。ドイツ的な重厚感より色彩感があり、木管は森の中の小動物を思わせます。響きの透明感もあって爽やかな演奏です。弦や金管はスケールが大きく、速めのテンポで盛り上がって自然賛美のうちに曲を閉じます。
これまでの巨匠の演奏では見えてこなかった魅力があり聴きごたえのある名盤です。
朝比奈隆=新日本フィル (1992年)
朝比奈隆のブルックナー交響曲第7番は沢山のCDが出ています。手兵の大阪フィルにするか、技術レヴェルの高い新日本フィル、東京都交響楽団などにするか迷う所です。一番、安定した支持を得ているのは、この新日本フィル盤(1992年)です。
朝比奈隆=大阪フィル (1975年聖フローリアン・ライヴ)
朝比奈隆と大阪フィルは1975年に欧州ツアーを敢行しています。当時、日本のオケがヨーロッパに行く機会は滅多にないと思います。今でもNHK響、都響など、在京のトップオケなら行くこともあるでしょうけど、欧米ツアーはそんなには無いと思います。そして、当時すでにブルックナーの演奏スタイルを確立していた朝比奈隆は、手兵大阪フィルと初めてブルックナーの聖地である聖フローリアン大聖堂で演奏することになります。今考えると、1970年代には既に朝比奈氏のブルックナーの演奏スタイルはほぼ確立していたんですよね。CDで1970年代の録音を聴いても若くて物足りないということはありません。

朝比奈隆の代表盤とまで言われつつ、神々しいまでの音楽を演奏し、いくつか偶然も重なって、まるでブルックナー自身があの世で祝福してくれているような名盤です。しかも、終演後にはノヴァーク氏が楽屋にやってきて、お礼を言ってくれたのです。
さて、普段、日本のドライなホールで演奏していて、録音の経験も少ない(自分たちの音を細かく聴いていない)当時のオケ、しかも第2の都市とはいえ、大阪のオケが、急に大聖堂のお風呂場のような長大な残響のある所でCD録音したら、どうなるでしょうか?それがこの名盤の問題です。技術的に、あまりにもミスが多すぎるし、音程も悪いし、アンサンブルも第3楽章で大崩れです。ホルンなんて、気温のせいか音を外しまくっています。金管がここまで不調なのは10月だから微妙ですけど、かなり気温が低かったのかも知れません。(金管は気温が低いと高音が出しにくい。)
ただ、そういう難点を我慢して聴けば、良い所も沢山ある名演なので、感動する瞬間も非常に多いです。特に深みのある第2楽章の最後のワーグナーの追悼音楽の後に、フローリアン大聖堂の鐘の音がなりはじめます。その頃に鐘が鳴るのは時間を計算すれば分かることですが、朝比奈氏の静かで穏やかな追悼音楽の終わりに合わせて、鐘が鳴ったという奇跡。第3楽章の演奏を始めるのを待つのですが、その時間の心地よさはブルックナーの本質の一つだと思います。しかし、第3楽章ではアンサンブルが大崩れ、第4楽章では金管がヘタってしまったのか音を外しまくり、弦楽器と聖フローリアンの豊かな響きが、この名演奏を救っています。リマスタリングなどやり過ぎると、ミスが目立つだけかも知れません。
このCDを入手するなら、技術的には色々問題があることを知っておいた方がいいです。筆者は昔持っていましたが、手放してしまい、後悔しています。良い所も沢山あり、感動的な演奏なのは間違いありません。
CD,MP3をさらに探す
演奏のDVD,Blu-Ray,他
ヨッフム=アムステルダム・コンセルトヘボウ管 (1986年来日ライヴ)
ヨッフムとアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の来日公演の映像です。上でレビューしましたが伝説的名演です。
DVD,Blu-Rayをさらに探す
ブルックナー交響曲第7番は上記で紹介したほかにも多くの映像があります。
楽譜・スコア
ブルックナー作曲の交響曲第7番 ホ長調の楽譜・スコアを挙げていきます。
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。


![ブルックナー:交響曲第7番、モーツァルト:交響曲第33番 (Jochum / Bruckner : Symphony No.7, Mozart : Symphony No.33) [2 SACD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51f0h32MUmL._SL500_.jpg)



![ブルックナー : 交響曲第7番 (改訂版) / カール・シューリヒト、ハーグ・フィルハーモニー管弦楽 (Bruckner : Symphony No.7 / Carl Adolph Schuricht & Hague Philharmonic Orchestra) [CD] [国内プレス] [日本語帯・解説付き]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Felr5v8vL._SL500_.jpg)


![ブルックナー : 交響曲 第7番 ホ長調 WAB.107 (ハース版) (Bruckner : Symphony No.7 / Takashi Asahina | Osaka Philharmonic Orchestra) [Live]](https://m.media-amazon.com/images/I/51m09CS+ptL._SL500_.jpg)