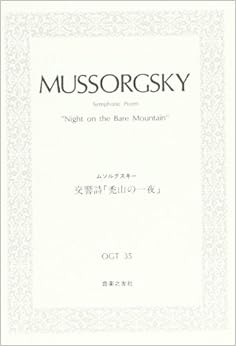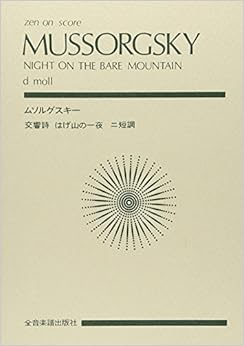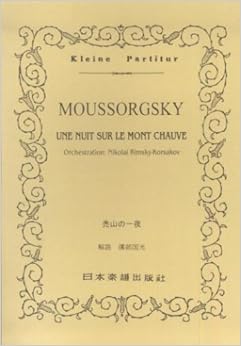モデスト・ムソルグスキー (Modest Mussorgsky,1839-1881)作曲の禿山の一夜 (Night on Bare mountain)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。交響詩『禿山の一夜』は、迫力と有名なメロディで人気がある曲です。このページでは『禿山の一夜』の解説と、お薦めの名盤のレビューをしていきます。
解説
交響詩『はげ山の一夜』の解説をします。
「聖ヨハネ祭前夜、禿山に地霊チェルノボーグが現れ手下の魔物や幽霊、精霊達と大騒ぎするが、夜明けとともに消え去っていく」とのロシアの民話をもとに作曲された交響詩です。
ムソルグスキーの原典版
この曲は通常は、リムスキー=コルサコフによる編曲版が使われます。しかし、この編曲版はオーケストレーションのみではなく、曲の内容を大幅に変えてしまっているのです。
ムソルグスキーのオーケストレーションによる原典版を聴いてみると、かなりグロテスクな音楽になっています。まさに「魔物や幽霊、精霊達と大騒ぎ」という雰囲気で、ベルリオーズの幻想交響曲などを思い出してしまいます。でも、ここまでグロテスクさを上手く描き出した音楽は無いかも知れません。ムソルグスキー自身も気に入っていたようですが、初演のしてくれる演奏家は結局いませんでした。
ムソルグスキーは初演してもらおうと、いくつもの改訂を行ったり、オペラ「ムラダ」や「ソロチンツィの市」の中に使うことも考えましたが、肝心のオペラのほうが未完に終わりました。結果として原典版と言われるものは、4つあります。
ムソルグスキーは「展覧会の絵」もラヴェルによってオーケストレーションされていますが、本当はもっと別のベルリオーズのような才能のある作曲家だったのかも知れませんね。
リムスキー=コルサコフの編曲版
以前は、リムスキー=コルサコフによるオーケストレーションの上手さが強調されていましたが、実際に聴き比べてみると、全く違う音楽です。4つの原典版の中でリムスキー=コルサコフは一番最後の「ソロチンツィの市」を元に編曲とオーケストレーションを行いました。
スヴェトラーノフ=USSR国立管弦楽団。
でも、リムスキー=コルサコフ版は、理解しやすく、スマートすぎますが、確かに良いオーケストレーションで、演奏効果は高いと思います。原典版がカオスに聴こえる(ムソルグスキーはカオスな音楽を作曲したかったのだと思いますが。)のに対して、リムスキー=コルサコフ版はテーマがしっかり提示されており、テーマ自体もキャッチーで聴きやすく、この曲が人気があるのはリムスキー=コルサコフのおかげでしょうね。
おすすめ名盤レビュー(リムスキー=コルサコフ編曲版)
『はげ山の一夜』のリムスキー=コルサコフ編曲版をレビューしていきます。この編曲が普通の『禿山の一夜』です。
ゲルギエフ=ウィーン・フィル
ゲルギエフはテンポは速めですが、ロシアの指揮者の中では割と普通の演奏をする指揮者ですね。見た目はかなり爆演系に見えるのですが、実際聴いてみるとしっかりした演奏が多いです。ただロシアものは民族的な演奏になっていることが多いです。
オーケストラはウィーンフィルです。こちらはムソルグスキーが得意な感じは全くしないのですが、民族的な音楽を演奏すると意外に名演になったりします。その代表はハチャトゥリアンのガイーヌですね。ゲルギエフとウィーンフィルの組み合わせは相性が良いようです。特に近年のウィーンフィルは技術的にも向上して、速いテンポにもついていけている場合が多いです。ロシア的で民族的なところも上手く表現しています。
ゲルギエフ=ウィーンフィルの演奏は、速いテンポでスリリングさがありながら、爆演というわけでもなく、民族的な味もあります。トータルとしてはスタンダードとして通用するなかなかの名演奏になっています。
スヴェトラーノフ=ロシア国立管弦楽団 (1992年)
スヴェトラーノフとロシア国立交響楽団との録音も出ています。上のYouTubeの演奏よりも新しいCDでこちらは入手しやすそうです。実際聴いてみると1992年というスヴェトラーノフがまだ爆演をしていた時期で、スヴェトラーノフの解釈はソ連時代と同じで、ロシア国立響を爆発的といってもいい位、ダイナミックに鳴らしています。録音は良くなっています。
冒頭の高速のうねるようなクレッシェンドも健在で、テンポの速さもソ連時代と変わらぬ迫力です。金管のレヴェルも落ちていません。理想的といえる迫力です。後半、少しテンポを落とすのも同じで、スヴェトラーノフの『はげ山の一夜』の演奏スタイルはしっかり確立しています。迫力のある部分も、その後の静かな部分もロシア的な土の香りを感じ、味わい深さもある名演です。
カップリングの『展覧会の絵』もスヴェトラーノフならではのロシア的な名演で、スヴェトラーノフの凄さを知りたい人には非常にお薦めのディスクです。
シノポリ=ニューヨーク・フィル
シノポリとニューヨークフィルの録音です。この『禿山の一夜』は、テンポが速くシャープさと迫力があり、名演です。ニューヨーク・フィルの金管も安定していて、オーケストラ全体としても、なかなか重厚です。録音も新しいため、迫力のあるサウンドが良く収録されています。
シノポリは速めのテンポでシャープな熱気のある指揮ですが、盛り上がってくるとさらにテンポアップしていきます。ロシア人以外の『禿山の一夜』では、一番刺激的な爆演だと思います。ニューヨーク・フィルも力強く白熱した演奏を繰り広げています。
ライナー=シカゴ交響楽団
ライナー=シカゴ交響楽団の録音です。録音は1959年で、少し古いですが、しっかりしたスタジオ録音です。
ダイナミックで非常に迫力があります。鋭いアクセント、シャープさがあり、迫力という点では、スヴェトラーノフ盤に匹敵するものがあります。(個性はスヴェトラーノフほどではないですが)シカゴ交響楽団は、ショルティ時代と変わらない金管のレヴェルがありますし、ライナーは遠慮なく鳴らしてきます。
フェドセーエフ=モスクワ放送交響楽団
フェドセーエフ=モスクワ放送交響楽団は、テンポは遅めですがロシア的で味のある演奏を繰り広げています。モスクワ放送交響楽団もロシアのオケでは最高峰のダイナミックさを持つオケで、迫力のある演奏です。
マルケヴィッチ=ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
マルケヴィッチはキエフに生まれ、2~3歳のころに西側のスイスに亡命しました。ですのでロシア人ですが、ラファエル・クーベリックの例を出すまでもなく、亡命した人が東側のオーケストラに客演するのは難しいことだと思います。ですので、東ドイツのライプツィヒ・ゲヴァントハウスに客演するのは難しいし、そもそも音楽的なスタイルを考えても、当時いぶし銀のオーケストラと言われたゲヴァントハウスにマルケヴィッチのような爆演系指揮者が客演する理由もよく分からないですね。
演奏を聴いてみると、マルケヴィッチのシャープさは健在で、なかなかの爆演ですが、オーケストラによって上手く丸められていて、ちょっと中和されている気もします。昔のスヴェトラーノフ=ソビエト国立交響楽団のような凄い演奏を知っている人からすれば、まあ普通に聴こえるかも知れませんね。でも、いま入手できるディスクの中ではかなりシャープで迫力のある演奏で、おすすめです。
スヴェトラーノフとソヴィエト時代のソヴィエト国立管弦楽団の録音です。上のYouTubeの爆演ですが、Amazonでは入手しにくそうですね。レビューも一つも上がっていません。でも、凄い演奏なので中古が出てくるかも知れませんし、一応挙げておきます。
聴いての通りですが、YouTubeで伝わるものか分かりません。CDでは、かなりスケール感のある演奏で低音も効いています。テンポの取り方や強弱のつけ方が、さすがスヴェトラーノフで、西側の演奏ではありえないような解釈です。非常にロシア的、民族的なところもある演奏です。
「禿山の一夜」原典版のおすすめCD
禿山の一夜の原典版は、実は4種類あります。
アバドはムソルグスキーの才能に共感したのか、ムソルグスキーのほぼ全作品をディスクに収録しています。オペラ「ボリス・ゴドゥノフ」まで全曲録音している位です。
演奏のほうもベルリンフィルやロンドン交響楽団といったダイナミックなパワーを持つオーケストラを使って、荒々しい演奏を繰り広げています。ベルリンフィルとの「原典版」が一番定番ですが、ロンドン交響楽団との息の合った演奏も素晴らしいです。
アバドの指揮であれば、どの原典版の演奏であっても、ムソルグスキーの理解度が大きく深まることは間違いなしですね。ただアバドはイタリア人なので、イントネーションがハッキリしすぎていて、ダイナミックに管楽器や打楽器が活躍する場面はバッチリですが、暗い場面やモヤがかかったような場面では、ちょっとはっきり演奏しすぎるところがあるかも知れません。
ロシア的で民族的な部分は、少し弱いですが、ムソルグスキーの粗削りながら隠れた魅力を十二分に引き出した名盤であり、今後、原典版の定番としての位置を得ていく演奏だと思います。
アバドとロンドン交響楽団の名盤です。以下の曲が収録されています。
1.歌劇『ホヴァーンシチナ』~第4幕第2場への間奏曲(追放されるゴリツィン公の出発)
2.ヨシュア
3.歌劇『サランボー』~巫女たちの合唱
4.スケルツォ変ロ長調
5.センナヘリブの敗北
6.聖ヨハネ祭の夜の禿山(交響詩『禿山の一夜』原典版)
7.歌劇『アテネのオイディプス』~神殿の人々の合唱
8.歌劇『ホヴァーンシチナ』~前奏曲『モスクワ河の夜明け』
9.凱旋行進曲『カルスの奪還』
(1-3,5,7-9:リムスキー=コルサコフ編曲)
アバドとベルリン・フィルの録音です。こちらも原典版ですが、合唱が入ったバージョンです。音詩『聖ヨハネ祭前夜の禿山』という曲にあたるものです。
冒頭の有名なメロディが合唱で歌われます。かなり迫真の演奏で、クオリティも高いです。ムソルグスキーのオペラの一節に出てきそうな自然な音楽です。この音楽だととてもインパクトがありますね。テノールも出てきてスケールの大きな音楽になっていきます。合唱が入ることでムソルグスキーのオーケストレーションも説得力が出てきます。破滅的なラストも印象深いです。
入手が難しめですが、『禿山の一夜』を詳しく知りたい人には、必携のディスクだと思います。カップリングのムソルグスキーの音楽も非常にクオリティが高く熱気のある演奏で、ムソルグスキーの管弦楽曲の神髄を知りたいなら、お薦めします。
ロジェストヴェンスキー=BBC交響楽団
ロジェストヴェンスキーとBBC交響楽団の録音です。このロジェストヴェンスキーの演奏は、歌劇「ソロチンスクの市」からの抜粋です。ですが、一つ上のアバドの合唱バージョンと同じです。確かに「聖ヨハネ祭前夜の禿山」と書いてあります。演奏は、こちらの方が大胆でオペラのようで面白いです。
ゲルギエフ=マイリンスキー劇場管弦楽団の録音です。アバド=ベルリンフィルと比べると、やはりベルリンフィルのほうがダイナミックで、技術的にも上ですかね。でもゲルギエフ=マイリンスキー劇場管弦楽団にとって、お国物ですから、民族的な味があって良いです。ベルリンフィルは民族的な味はほぼ無くて、インターナショナルなサウンドなので、その点はムソルグスキーのロシア的な土臭さを求めるなら、ゲルギエフ=マイリンスキー劇場管弦楽団のほうが、ずっと良いです。
ロシアのオケですが、ゲルギエフが振ると適度に民族的な演奏になります。それに、原典版が自然に聴こえるのが、この演奏の面白い所です。ムソルグスキーのオーケストレーションが今一つだったとしても、演奏者が少し工夫すれば良い程度のものかも知れません。ロシアの魔女の集会の物語が自然に表現されているように聴こえます。ごく当たり前に演奏できていて、リムスキー=コルサコフ編曲版なんて、聴衆受けを狙った編曲に聴こえてしまいます。
ちなみにこのディスクには歌曲集「死と歌の踊り」(ショスタコーヴィチ編)も入っていて、ムソルグスキーの重要な曲がかなり網羅されています。非常に良い選曲だと思います。
サロネン=ロサンゼルス・フィル (原典版)
作曲家でもあるサロネンとロサンジェルス・フィルの録音です。始めはリムスキー=コルサコフ編曲かなと思った位、知的でクールな演奏です。ムソルグスキーの編曲だからといって、ダイナミックに演奏せず、譜面を読みこんで丁寧に演奏しています。
ロサンゼルス・フィルが演奏しているので、やろうと思えばもっとグロテスクにもダイナミックにもできるはずですが、サロネンはそういう風にはしないようです。作曲家でもあるからでしょうか。でも、ムソルグスキーのオリジナル版を、きれいに演奏しても、ちゃんと曲になっていることが分かります。サロネンが演奏すると物語性が前面に出てくるようです。
冒頭はシャープでとても迫力があります。重低音を活かして、グロテスクさも出ています。細かいアンサンブルのレヴェルが高くさすがロス・フィルですね。オーケストレーションの薄い個所も上手く対処していて、オーケストレーションの良くない所が表面化していないのも、さすが作曲家のサロネンです。
パーヴォ・ヤルヴィとNHK交響楽団の録音です。とうとうN響からもこんな意欲的なプログラムが出てくるようになりましたね。指揮者がパーヴォ・ヤルヴィですから、やはり原典版を選ぶようです。
しかもメジャーレーベルへの録音ということで期待してしまいます。しかし、、この「禿山の一夜」原典版に関して言えば、N響があまりに演奏に慣れていない様子で、随分大人しい原典版になっています。とはいえ他のヨーロッパのオケだって、原典版を頻繁に演奏するオケは少ないでしょうから、N響ももっと大胆さとか適応力が必要なんでしょうね。
ただ細かい所の繊細な表現力は、録音の良さも相まって、色彩的で面白いです。ところどころ音が薄くなってしまうのは、むしろムソルグスキーのオーケストレーションを忠実に再現したからかも知れません。
ライヴ録音ですし、「展覧会の絵」はなかなかの演奏なので、トータルとしては良いディスクです。「展覧会の絵」のページで書いてみたいと思います。
「禿山の一夜」その他編曲版
もっともポピュラーなリムスキー=コルサコフ版と原典版について紹介してきました。ここでは他の編曲によるディスクを紹介します。
ストコフスキーとロイヤル・フィルの録音です。ストコフスキー自身の編曲版によるもので、ベースはリムスキー=コルサコフの編曲版を元にしています。ディズニーの映画「ファンタジア」でも、ストコフスキー編曲版が使用されました。
ストコフスキー編曲版は、比較的スマートなリムスキー=コルサコフ版を逆に少し荒々しくしたもので、原典版に近い方向に編曲されています。ならば、原典版を使えば良かったのでは?と思わなくもないですが、ストコフスキーの時代だとまだムソルグスキーの研究が進んでいなかったかも知れません。もちろんディズニーのようなアメリカの産業がバックにあったこともあるでしょうけれど。それにしてもストコフスキーは研究家でもないのに、直観のみで編曲したのですから、よほどのセンスの持ち主ですね。
探すとナッセンや山田和樹など、ストコフスキー版を使った録音も出てきています。
レイボヴィッツ=ロイヤル・フィル
レイボヴィッツとロイヤル・フィルの録音です。レイボヴィッツはリムスキー=コルサコフの編曲が物足りないと思ったのか、リムスキー=コルサコフの編曲を、さらに編曲しています。レイボヴィッツ版ですね。
結果として原典版の『はげ山の一夜』を思い出させるような、奇抜でグロテスクなオーケストレーションになっています。まだ、アバドによる原典版ブームが到来していなかった時代では、貴重な録音です。演奏もロイヤル・フィルにしては、かなり荒々しいもので、ロシア的な迫力のあるものになっています。このグロテスクなまでの荒々しさはさすがレイボヴィッツです。オーケストレーションの達人らしく、ウィンドマシンまで使っています。後半は静かになって終わるので、リムスキー⁼コルサコフ版をベースにしている、と言えますね。しかし、ラストは壮大に盛り上がって曲を締めます。
CD,MP3をさらに探す
楽譜・スコア
ムソルグスキー作曲の禿山の一夜の楽譜・スコアを挙げていきます。
ミニチュア・スコア
OGTー35 ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」
解説:菅野 浩和
3.0/5.0レビュー数:1個
スコア ムソルグスキー 交響詩「禿山の一夜」ニ短調 (Zen‐on score)
解説:園部 四郎
3.0/5.0レビュー数:1個
No.23 ムソルグスキー 禿山の一夜 (Kleine Partitur)
3.0/5.0レビュー数:2個



![ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」 [xrcd]](https://m.media-amazon.com/images/I/51LsTB5omBL._SL500_.jpg)