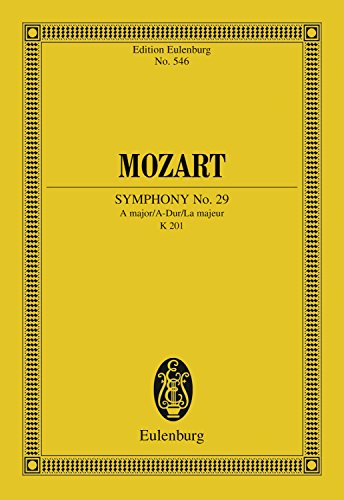ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト (Wolfgang Amadeus Mozart,1756-1791)作曲の交響曲 第29番 イ長調 K.201(186a) (Symphony No.29 a-dur K.201(186a))について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。ワンストップでスコアや無料楽譜(IMSLP)なども紹介していきます。
解説
モーツァルトの交響曲第29番について解説します。
25番と並んで、20番台の人気曲
モーツァルトの交響曲は第1番から残っていますが、全集などで無ければ、あまり演奏はされません。しかし、交響曲第25番ト短調の人気が高く、次に人気があるのがこの交響曲第29番です。
小編成ですが、しっかりした交響曲であり、昔から前半のプログラムとして良く取り上げられてきました。第1楽章のメロディは優美で有名です。
作曲の経緯
1773年~1774年にモーツァルトは9曲の交響曲を作曲しています。1773年に人気のある第25番、それに1974年に第29番が書き上げられています。そして、第30番まで一気に作曲されています。一連の交響曲を書き上げた時点でまだ十代でした。
その次の交響曲第31番『パリ』は1778年の作曲で少し間が空いており、楽器編成もかなり大きくなっています。
当時のモーツァルトはまだ4楽章形式以外に、「イタリア風序曲」と呼ばれる3楽章形式の交響曲も作曲していました。これらは10分以下で演奏できる短い曲で、今の交響曲というより、急-緩-急の3楽章形式のシンフォニアに近いものです。モーツァルトがイタリア旅行からザルツブルクに帰ってきた時期であり集中して作曲されています。
その元祖はアレッサンドロ・スカルラッティ(1660年-1725年)が作曲した3楽章形式のシンフォニアで、オペラの序曲から独立したもので、1686年にはその形式は確立しています。これは交響曲のルーツの一つです。ここからヴィヴァルディなどのシンフォニアが生まれ、ソロ・コンチェルトもこの流れから生まれています。
ちなみにアレッサンドロ・スカルラッティの息子はスペインで活躍した有名な作曲家ドメニコ・スカルラッティで、鍵盤(チェンバロ)のための作品を多く残しています。
曲の構成
典型的な4楽章構成で、演奏時間は約20分です。
第1楽章:アレグロ・モデラート
ソナタ形式です。序奏の無い普通のソナタ形式で、冒頭からいきなり有名な主題で始まります。展開部も十分な長さがあります。
第2楽章:アンダンテ
緩徐楽章で、ソナタ形式です。味わいのある緩徐楽章で、メロディも素晴らしく、この時期のモーツァルトとしては聴き応えのある名曲です。
第3楽章:メヌエット – トリオ
複合3部形式です。
第4楽章:アレグロ・コン・スピーリト
ソナタ形式です。テンポの速い最終楽章です。
オーボエ×2、ホルン×2
弦五部
おすすめの名盤レビュー
それでは、モーツァルト作曲交響曲第29番の名盤をレビューしていきましょう。ちなみに管理人は昔、ワルベルク指揮NHK交響楽団を良く聴いていたため、遅めのテンポが刷り込まれていますね…
バーンスタイン=ウィーン・フィル
円熟期のバーンスタインとウィーン・フィルの録音です。音質はしっかり安定しており、ライヴのハンデはありません。
第1楽章は昔ながらの遅めのテンポで、とてもロココ調の雰囲気が良く出ています。ウィーン・フィルの音色もこの曲に良く合っています。編成も大きめなので、アクセントはしっかり厚みもあります。しっかりしたソナタ形式の演奏と思います。第2楽章はロココ調の雰囲気がさらに良く出ています。特にホルンはウィーン・フィルにしか出せない音色と思います。優美で息の長い旋律を、優雅に歌っていきます。
第3楽章はリズミカルで伸びやかです。高弦の音色は艶やかです。中間部はロココ調の味わいのある演奏です。とても丁寧に演奏されています。第4楽章は少し速めでスリリングさもあります。ウィーン・フィルの音色の良さもあって、ロココ調に聴こえます。
昔ながら遅めのテンポが好みの方にはお薦めの名盤です。カップリングもクラリネット協奏曲で有名です。
ノリントン=SWRシュトゥットガルト放送交響楽団
ノリントンとSWRシュトゥットガルト放送交響楽団によるピリオド奏法での録音です。新しめの録音で高音質です。
第1楽章は速いテンポでスリリングです。遅い演奏が多いので、速すぎるように聴こえますが、これは慣れですね。チェンバロが入っていて、優美な雰囲気です。強弱もメリハリが良くついていて、軽快でスリリングな演奏になっています。第2楽章は凄く速いテンポですね。このテンポでも聴いているとすぐに慣れてきます。弦の優美な旋律は美しく歌われています。軽妙さは見事です。少し冗長に感じた第2楽章がとても生き生きとして聴こえます。目から鱗が何枚か落ちます。
第3楽章は溌剌としたメヌエットです。適度なアクセントがあり、自然に聴こえます。中間部は味わい深さがあり、優雅さもあります。第4楽章は凄く速いです。編成が小さいため、小気味良い響きが心地よいです。展開部はスリリングに盛り上がり、少し対位法的な細かい弦のアンサンブルが素晴らしいです。ラストはダイナミックに曲を締めます。
ノリントンのピリオド奏法は好き嫌いが分かれそうですが、目から鱗が落ちる所が沢山あります。何度か聴くと慣れて来て、この演奏こそモーツァルトらしいものだ、と思えてきます。
ブリテン=イギリス室内管弦楽団
イギリスの著名な作曲家ベンジャミン・ブリテンとイギリス室内管弦楽団の録音です。音質は少しザラツキがありますが、安定しています。作曲家としての目線も踏まえて、ブリテンは指揮も上手いです。
第1楽章は少し速めのテンポで小気味良く始まります。メリハリが良くついていて、聴いていて爽やかな演奏です。適度なロココ調の雰囲気があり、展開部もスリリングさがあります。イギリス室内管は一糸乱れぬ弦セクションが印象的です。第2楽章は少し遅めのテンポで落ち着いて味わい深く演奏していきます。
第3楽章は小気味良くリズミカルです。第4楽章は速めのテンポですが、優美さと爽やかさは失わず、とても聴き心地の良い演奏です。展開部はダイナミックさもあります。
交響曲第29番をとても真摯に演奏しており、スタンダードな名盤です。聴いた後の充実感もなかなかのものです。
CD,MP3をさらに探す
演奏の映像(DVD,Blu-Ray,他)
DVD,Blu-Rayをさらに探す
楽譜・スコア
モーツァルト作曲の交響曲第29番の楽譜・スコアを挙げていきます。

![モーツァルト : 交響曲 第12番、第29番、第39番 (Mozart : Essential Symphonies Vol. II ~ No.12, 29, 39 / Roger Norrington, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR) [輸入盤]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qfG2UeoVL._SL500_.jpg)

![Karl Bohm: Mozart - Symphonies[DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/41rPSK9BCsL._SL500_.jpg)