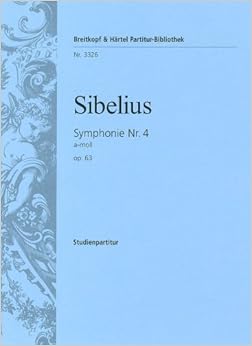ジャン・シベリウス (Jean Sibelius,1865-1957)作曲の交響曲第4番 イ短調 op.63 (Symphony No.4 a-Moll op.63)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。
シベ4といえば、あまり明るい曲では無く、内面に深く沈みこんでいくような曲調で、それまでの交響曲に比べてもかなり地味です。しかし、力強さやスケールの大きさもあり、最近は結構注目も浴びている曲でもあります。実はシベリウスの交響曲の中でも名曲の一つとされています。
解説
シベリウスの交響曲第4番 イ短調 op.63について解説します。
背景
交響曲第4番にはいくつかの出来事が影響していると考えられています。まず、1907年にペテルブルクとモスクワに演奏旅行しましたが、喉の痛みに悩まされます。帰国後、今度はインフルエンザで倒れ、翌年の演奏旅行をキャンセルしました。そして借金をしてベルリンまで行き喉の腫瘍の手術を行いました。その後、療養生活がしばらく続きました。
もう一つは、1909年9月に北カレリアのコリ山地へ旅行し、大自然の力強さを知り、創作意欲を取り戻します。
私の生涯で最も素晴らしい体験の一つ
と書き記しています。
生死にかかわるような腫瘍の手術、もう一方で雄大な大自然のスケールを目の当たりにしたことは、この交響曲第4番へ影響していると考えられています。シベリウスは交響曲第4番を「精神的交響曲」と呼んでいます。
作曲と初演
交響曲第4番の作曲は1910年~1911年3月にかけて行われました。初演は1911年4月13日にシベリウス自身の指揮によりヘルシンキ・フィルで行われました。
曲の構成
交響曲第4番は一応、通常の4楽章形式をとっています。しかし、楽章間が曖昧で聴いているうちに何楽章を聴いているのか分からなくなる時があります。いずれ、第5番以降では第1、第2楽章が有機的に結合され、第7番では単一楽章の曲になりますが、その流れが始まったのが交響曲第4番と考えられます。
■第1楽章:テンポ・モルト・モデラート、クワジ・アダージョ
独自に拡張されたソナタ形式です。通例に反し、緩徐楽章でもあります。憂鬱な主題で始まり、通常のソナタ形式となりますが、最後はまた不気味な余韻を残して終わります。聴いていると細かいモチーフが目立ちソナタ形式という感じがしないですね。
■第2楽章:アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ
スケルツォです。3部形式ですが、中間部は短いものです。最後は幻想曲風になっています。最初はスケルツォ風ですが、この楽章もシリアスで曖昧模糊としています。
■第3楽章:イル=テンポ・ラルゴ
緩徐楽章です。深い瞑想のような音楽が続きます。分割された細かいモチーフが絡み合うように進み、やっと後半になり主題の全体が現れます。その後、大きく盛り上がりますが、またpに戻ります。
■第4楽章:アレグロ
ロンド風の楽章です。イ長調で始まるがイ短調で終わります。ヴァイオリンの主題に細かいモチーフが絡み合います。ヴィオラかチェロの主題は民族楽器フィドルだと思います。ノルウェーのものが『ペール・ギュント』の抜粋や全曲盤に出てきます。フィンランドはまた少し違うかも知れません。
おすすめの名盤レビュー
それでは、シベリウス作曲交響曲第4番 イ短調 op.63の名盤をレビューしていきましょう。
カラヤン=ベルリン・フィル (1965年)
カラヤン=ベルリンフィルの1960年代の録音で、ベルリン・フィルの低弦が効いていて重厚なサウンドです。
第1楽章は重厚な響きで始まります。不協和音などもスコア通りに演奏していますが、この頃のカラヤンはパワフルです。弦セクションと言いトランペットと言いスケールが大きく、精神的深みに沈んでいく、というより大きな山に登っていくような雰囲気です。これも上述したように壮大な自然を表している可能性もあるので、一つの良い表現だと思います。他の演奏で聴くと不協和音がキツかったり、グロテスクだったりするのですが、カラヤンの演奏は根底に壮大なダイナミックさと意志の強さがあり、様々な表情のモチーフがどんどん現れてきても混乱することはありません。
第2楽章も深い森の中で小動物が急に出てきたりと、そういうイメージで十分聴けます。それは根底にスケールの大きさと厳しさがあるからだと思います。第3楽章になると、さらに神秘的になり壮麗さも出てきます。厳しさはありますが、むしろ清涼さがあり教会で自己を探求しているかのようです(ちなみに筆者はキリスト教では無いですけど)。後半の弦の主題の演奏からは深い嘆きを感じます。そして圧倒的に盛り上がり、これは感動的です。精神面が浅いとか、そういうことは一切感じられないですね。
第4楽章は現代音楽的な不協和音が多く出てきますが、カラヤンは20世紀の音楽は実は得意なので、現代音楽の要素が出てきても全く迷いはありません。民族楽器フィドルのようなモチーフも民族的に上手く演奏して、その後の変化も本当に上手く演奏しています。
シベリウスはカラヤンの演奏を高く評価していましたが、その意味がよく分かる名演です。ヘルシンキ・フィルに比べて、根底にダイナミックさや厳しさがありますが、この辺りはドイツ的ですね。
ベルグルンド=ヘルシンキ・フィル
ベルグルンド=ヘルシンキ・フィルの演奏です。難解な曲、といえど、ヘルシンキ・フィルはシベリウス自身の指揮で初演を行ったオーケストラです。そこに指揮者がベルグルンドということで、ヘルシンキ・フィルの歴史とベルグルンドの直截的な表現が上手くマッチした名盤です。
第1楽章はスケールの大きさがメインです。やはり何か大きなスケールのもの、フィンランドの大自然などを描いているように思います。ヨーロッパ室内管と異なり、響きに暖かみがあり、スケールに浸っているうちに第2楽章に入ります。第2楽章は不穏ですけど、ヘルシンキ・フィルだと大自然を感じます。深い森の中にいるような雰囲気です。カラヤンに近い気もしますが、シリアスさは無く暖かみがあります。尾高=札響に近いかも知れませんね。
第3楽章は寂しげに始まり、静寂な空間にフルートが響きます。ホルンが神々しく響きます。ただ全体的には教会の壮麗さは無く、人間的な暖かみがあります。中間付近からの弦の主題は味わい深く響きます。嘆くようにして、少しずつ感情的に盛り上がっていきます。第4楽章はここまでで初めてフィンランドのオケですが、民族楽器フィドルの主題もそれらしく演奏していますね。ヘルシンキ・フィルで聴くとユニークなモチーフがどんどん現れて「なるほど」という感じです。シリアスさが全くないとは言いませんけど、あまり強調されていないです。短調になっても人間の精神力の方が勝っている、という雰囲気です。
ベルグルンドでもヘルシンキ・フィルの方が本質に迫っているように思います。やはりシベリウス演奏の長い伝統を感じさせます。
ヴァンスカ=ミネソタ管弦楽団
ヴァンスカ=ミネソタ管弦楽団の演奏です。第4番に関して言えば、ラハティ交響楽団の演奏が民族的な暖かみのある響きで素晴らしいのですが、軒並み廃盤です。少しクールですが、すごく上手いミネソタ管弦楽団の演奏をレビューしようと思います。ヴァンスカの解釈はラハティ響の時とさほど変わっていませんが、第3楽章は2分も短くなっています。
第1楽章の冒頭で奥の深い響きで、音質の良さとオケのレヴェルの高さを感じます。透き通った響きの中で、ヴァンスカはシリアスな面ばかりを強調せず、木管やチェロのソロが味わい深く響きます。不思議な弦の不協和音も深い森の中で小動物に出会うようなロマンティックさがあります。息の長いクレッシェンドは外側に広がっていく感じです。第2楽章は速いテンポで民族的な舞曲に聴こえます。小気味良く進めていきますが、不協和音やスフォルツァンドなどは結構迫力あります。
第3楽章はひたすら静かな世界が繰り広げられ、ピアニシモの中から様々なパッセージが現れます。この透明感はミネソタ管弦楽団ならでは、です。後半の弦は息の長い悲壮な表現ですが、それも消え、静寂に包まれます。弦の分厚いメロディは非常にスケールが大きな演奏です。第4楽章は軽快さが目立ちます。フィドルのようなチェロの主題も良いです。管楽器のアンサンブルもクオリティが高く、楽しめます。盛り上がってきても細かい所まで目が行き届いており、しっかり音にしています。
色々な要素が入っており、カラヤン盤やベルグルンド盤に比べると変化に富んでいます。ただ、表情が頻繁に変わるので、何がいいたいのか良く分からない感じもします。第4番自体が元々そういう曲かも知れませんけれど。
ベルグルンド=ヨーロッパ室内管弦楽団
ベルグルンド=ヨーロッパ室内管の演奏は、あまりフィンランドの自然を描いていないので、本質にストレートに近づいていきます。なので、比較的分かり易いのですが、第4番のような深みのある曲だと、ストレート過ぎてクールな感じもします。
第1楽章は静けさと深い森の中を思わせる不思議さで満ちています。深い森の中で急に小動物が出てきて驚いたりするような感じです。一方で、トランペットが鋭い音で出てきます。かと思えばホルンが北欧風の主題を吹いたり、と細かいモチーフが良く再現されています。ソナタ形式という構成もつかめずいるうちに、いつの間にか終わっています。
第2楽章はオーボエが主題を吹きますが、この演奏はストレートで、ずっとクールで不穏な雰囲気です。しかし、この演奏をもってしても第2楽章はいつの間にか終わり、さらに深く名曲である第3楽章に入っていきます。第3楽章は精神の深みの底に達したような雰囲気で、静かにじっくりと演奏されていきます。中盤から低弦の動きが出てきて、高弦の主題が聴こえてきます。終盤になって少し盛り上がりますが、やはり本当にシリアスな演奏です。第4楽章もしっかり聴いていないと、いつの間にか始まっています。不穏な主題で不協和音も多いですが、明るさも少し入ってきています。チェロのモチーフは民族楽器フィドルを上手く模倣しています。明るくなったり暗くなったりを繰り返しつつ、つかみ所の無いような音楽が続き、そのまま終わります。
うーん、予想以上に難解な演奏ですね。
尾高忠明=札幌交響楽団
尾高忠明=札幌交響楽団は交響曲第4番で適度な深みと味わいのある、かなりの名盤です。結構、緻密な部分もありますが、札響の暖かみのある響きのせいか、ベルグルンド=ヨーロッパ室内管のようなクールな演奏にはなっていません。尾高忠明は長い間、シベリウス好きのイギリスでBBCウェールズ交響楽団の指揮者をやっていたため、シベリウスに精通しています。交響曲第4番の難しさ、シリアスさを理解した上で、分かり易く聴きやすい演奏をしています。
第1楽章は弦の深みのある響きで始まり、現代音楽のようなパッセージや北欧のロマンを感じるホルンなど挟みつつ進んでいきます。第2楽章は淡い不安感が混じっている感じで、明るい音楽の中に現れる不安感の表現が上手いです。特に第3楽章は自然に聴けます。味わい深く暖かみがあり、シベリウスが表現したいことが演奏に反映されていると思います。後半の弦の盛り上がりは感動的ですらあります。第4楽章も不協和音はしっかり演奏しているにも関わらず、長調のモチーフも上手く目立たせ親近感が感じられ理解し易いです。
全体的に聴きごたえのある充実した演奏です。このCDは第5番よりも第4番の方が名演ですね。
CD,MP3をさらに探す
楽譜・スコア
シベリウス作曲の交響曲第4番 イ短調 op.63の楽譜・スコアを挙げていきます。
ミニチュア・スコア
大型スコア
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。


![シベリウス : 交響曲 第1番&第4番 (Sibelius : Symphonies Nos 1 & 4 / Minnesota Orchestra , Osmo Vanska) [SACD Hybrid] [輸入盤]](https://m.media-amazon.com/images/I/41fYCin-AcL._SL500_.jpg)