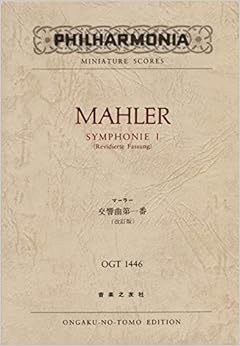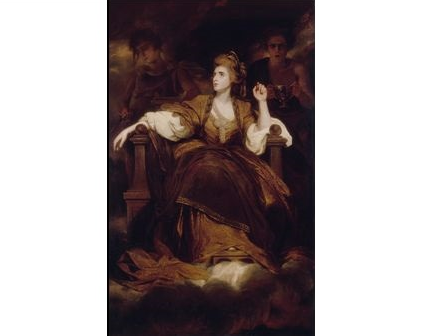グスタフ・マーラー (Gustav Mahler, 1860~1911) 作曲の交響曲第1番 『巨人』の、解説をした後、お薦めの名盤をレビューしていきます。
交響曲第1番『巨人』はマーラーの最初の交響曲です。非常に人気がある曲で、レヴェルの高いアマチュア・オーケストラなどでも演奏されます。
お薦めコンサート
🎵小林研一郎、読売日本交響楽団
■2023/4/21(金) 19:00 開演 ( 18:30 開場 ) 会場:サントリーホール 大ホール (東京都)
メンデルスゾーン(ヴァイオリン協奏曲)/マーラー(交響曲第1番「巨人」)[指揮]小林研一郎 [独奏・独唱]青木尚佳(vl)
解説
マーラーの交響曲第1番『巨人』の解説をします。
作曲の変遷と「花の章」
この作品は1884年に着手されましたが時間をかけて作曲され、1888年にブダペストにて完成しました。これは第1稿と呼ばれます。
ただし、この時はまだ交響曲とは呼んでおらず、『2部からなる交響詩』と呼ばれていました。第1部「青春の日々から。花、果実、いばらなど」、第2部「人間喜劇」という標題がついていました。また、この時には「花の章」が付いていました。
この時、マーラーはブダペスト王立歌劇場の指揮者でした。翌年の1889年にマーラー自身の指揮により、初演されています。初演の反響は特に大きいものではありませんでした。
そこで改訂を行い、第2稿が出来ました。これは楽章の構成は従来と同じですが、『巨人』というタイトルがつけられました。タイトルや各楽章の副題はジャン・パウルの小説の影響を受けている、とのことです。ヴァイマールやハンブルクでこの第2稿を演奏しています。
第1部:青春の日々から、若さ、結実、苦悩のことなど
第1楽章:春、そして終わることなく
第2楽章:花の章
第3楽章:順風に帆を上げて
第2部:人間喜劇
第4楽章:座礁、カロ風の葬送行進曲
第5楽章:地獄から天国へ
その後、ベルリンでの上演の際に第2楽章に置かれていた「花の章」は削除されました。1896年の改訂(第3稿)で4楽章形式の交響曲となります。
『巨人』というタイトル
第2稿でマーラーは『巨人』というタイトルを付けました。そしてしかし、このタイトルの由来は、マーラーが愛読していたジャン・パウルの小説『巨人』です。しかし、第3稿で削除されました。
交響曲第1番の大きさや長さを考えれば、『巨人』というタイトルがついていても違和感はありませんが、描かれているのは、おそらく最初の標題である「青春」や「人間喜劇」です。『巨人』というタイトルや各楽章の副題は撤回されましたが、現在でも『巨人』の愛称で呼ばれています。
交響曲第1番『巨人』は4楽章構成です。「花の章」を入れる場合は、第2楽章の位置に入ります。しかし、交響曲となった時に正式に削除されている楽章です。ただ、後の交響曲第3番などを見ると、交響曲の形式に従っておらず、同様に第1番に「花の章」を入れてもそれほど違和感は感じません。
第1楽章
序奏付きのソナタ形式です。序奏は「ゆっくりと、ひきずるように」と書かれています。主部は「きわめて落ち着いて」と指示されています。
第2楽章
スケルツォです。「力強く、だが速すぎずに」と指定されています。
第3楽章
三部形式の葬送行進曲です。緩徐楽章として挿入されています。ドイツ民謡の「マルティン君」から採られた主題を使っています。中間部はマーラー自身の歌曲集『さすらう若人の歌』から採られています。
第4楽章
自由なソナタ形式のフィナーレです。「嵐のように激動して」と記されています。中間部分では静かになり、詩情豊かな音楽になります。最後は圧倒的なダイナミックさで終わります。
★花の章
交響曲になった時に削除された楽章です。抒情的な音楽です。5分台とあまり長い曲ではありません。もともと第1部「青春、花、いばらなど」から採られているので、単純に自然を扱ったものというより青春、あるいは女性を表現したもの、と思われます。
おすすめの名盤レビュー
マーラーの交響曲第1番『巨人』のおすすめの名盤をレビューしていきます。
テンシュテット=ロンドン・フィル
テンシュテット=ロンドン・フィルの全集に収録されている第1番『巨人』です。筆者が昔、気に入っていて良く聴いていたCDです。世間的にも一二を争う名盤ですね。ロンドン・フィルはパワーが弱い感じもしますが、第1番ではテンシュテットは新鮮で詩的な世界を描いていて、ダイナミックさは二の次だと思います。
第1楽章は自然描写から始まりますが、とてもナチュラルでフレッシュさがあります。木管のソロが印象的です。後半はダイナミックさも出てきますが、やはり新鮮で味わい深い所が印象的です。ラストは凄い熱気と迫力で盛り上がります。第2楽章のスケツルォもロンドン・フィルの弦の響きがコクがあって味わい深いです。中間部は幻想的です。第3楽章はロンドン・フィルのチェロのソロが深みのある音色で良いです。民謡から採った主題も味わい深い表現で、さすがテンシュテットです。第4楽章は白熱したダイナミックさです。確かにもっと濃厚で密度の濃いダイナミックさが出せるオケはありそうですが、この第1番『巨人』に関しては、この位が丁度よいです。弦セクションからは濃密な響きを引き出していています。この楽章では色々な表現が聴けるのですが、この演奏の場合、詩的な情緒がある所が良く、若いマーラーの新鮮さを感じさせます。ラストはスケール大きく白熱して終わります。
他にライヴ録音、シカゴ交響楽団との録音などもあります。ライヴ盤は名演奏です。
ロト=レ・シエクル (第2稿, 花の章付き)
フランソワ=グザヴィエ・ロトとレ・シエクルは、ピリオド演奏を特徴としていますけど、今回は改訂の多い交響曲第1番『巨人』です。1893年版、すなわち第2稿で「花の章」もまだ削除されていません。ロトはフレッシュな演奏を繰り広げ、非常に素晴らしい名盤になっています。
第1楽章は木管の色彩的なソロが印象的で、パストラル風の雰囲気を持っています。レ・シエクルの明るい響きも奏功しています。明るい響きの中で悩みなどの感情表現していて、絶妙なバランスです。当時良く使用されたポルタメントも何か所か使われています。第2楽章「花の章」はトランペットソロが上手く、パストラル風な春のイメージをとても上手く表現しています。精妙な感情表現といい、本当にいい演奏です。第4楽章はピリオド演奏なので低音が弱めですが、ナチュラルで味わいのある演奏です。透明感のある録音の良さも手伝って、独特の味のある響きとなっています。第5楽章はダイナミックです。ピリオド楽器でもこれだけダイナミックさが出るのはマーラーのオーケストレーションが上手いということですね。ラストの盛り上げ方も上手く、速めのテンポで白熱した演奏で終わります。
単に第2稿が聴けるとかピリオド演奏である、というだけではなく、とても内容の深い名盤です。非常に味わいがあり、表現の完成度も非常に高いです。第1番『巨人』の印象が大きく変わるかも知れません。第2稿の方が、多少冗長なものの、この曲の性格を上手く表していて、交響曲第3番以降につながっていく流れを感じます。
ワルター=コロンビア交響楽団
ブルーノ・ワルターとコロンビア交響楽団の『巨人』です。マーラーの弟子であったブルーノ・ワルターは、このマーラー最初の交響曲を実に親しみやすく演奏しています。録音は少し古めですが良好です。良い音で聴きたい方は高規格なCDをお薦めします。
第1楽章は中庸のテンポで静かな空間に木管が鳥のようにさえずります。そんな田園風景では終わらず、とてもスコアの読みが深く、繊細な表情付けがされています。ホルンも上手く、とても良い雰囲気を出しています。弦もとても爽やかです。そしてスケール大きく盛り上がっていきます。第2楽章は速めのしっかりしたリズムで、楽しめる演奏です。各楽器がしっかり演奏し、スケールの大きな音楽でもあります。中間部は穏やかに変わり、ポルタメントを使って、田舎のシャンソンのようです。
第3楽章は巨人が歩くようなスケールの大きな行進曲となっています。各所でテンポを変え、多彩な表情を付けています。第4楽章はスケールが大きな演奏です。マーラーブーム以降の感情表現を前面に押し出した演奏とは違い、明るさがあります。健全なアプローチの中で金管が咆哮しています。穏やかな所ではとても味わい深い表現で、しみじみと聴かせてくれます。
ワルターは奇をてらうことはなく、あたかもベートーヴェンの『田園』のように、自然体の表現をしています。最近のマーラーを聴いている人には、目から鱗かですね。
小澤征爾=ボストン交響楽団 (「花の章」付き)
小澤征爾は若いころからマーラーを得意としており、第2番『復活』などは折に触れて演奏しています。ユダヤ的なマーラーではなく、水彩画のような透明感のある演奏が特徴です。ボストン交響楽団も透明感のある日々いなので上手く合っていて、この『巨人』もなかなか詩的な名演奏です。
「花の章」付きというのが売りの演奏ですが、もともと小澤征爾の演奏スタイルは、「2部からなる交響詩」と呼ばれていた頃の標題である第1部「青春、花、いばらなど」に相応しいです。若いマーラーの敏感な感性が良く感じられ、フレッシュな演奏です。「花の章」も違和感なく演奏されています。第4楽章も味わいがあって聴き所が多いです。第5楽章のフィナーレはダイナミックで、美しさもあります。
この後、同じ組み合わせで全集を録音するときに「花の章」なしでフィリップスに再録音されていますが、こちらも素晴らしい演奏です。
CD,DVD,MP3をさらに探す
楽譜
マーラーの交響曲第1番『巨人』の楽譜・スコアを挙げていきます。
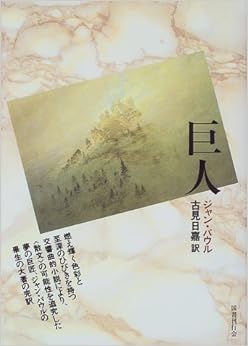

![マーラー : 交響曲第1番ニ長調「巨人」 (1893年版 花の章付き) / フランソワ=グザヴィエ・ロト | レ・シエクル (Mahler : Symphony No.1 / Francois-Xavier Roth, Les Siecls) [CD] [Import] [日本語帯・解説付]](https://m.media-amazon.com/images/I/51oWpJScA3L._SL500_.jpg)