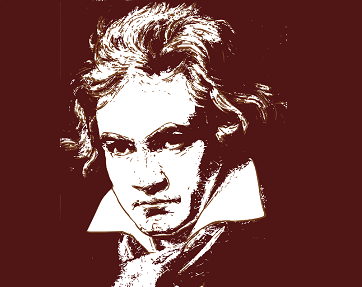ベンジャミン・ブリテン (Edward Britten,1913-1976)作曲の『青少年のための管弦楽入門』 ( young person’s guide to orchestra ) について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。ワンストップでスコアと楽譜まで紹介します。
解説
ブリテンの青少年のための管弦楽入門について解説します。
初心者のための良い入門
ブリテンは、ソヴィエトの大作曲家ショスタコーヴィチに比肩する位、才能があり、世に認められた作曲家でした。ショスタコーヴィチが交響曲第14番をブリテンに献呈し、西側で初演するよう依頼したこともあります。
そんなブリテンは青少年向けだから、といって格別に簡単な作品を書いたりはしません。この曲を作曲するに当たり、大編成のオーケストラを準備し、変奏曲という最も基本的で古い時代から存在し、かつ最も難しい部類に入る形式を選択しました。
主題はイギリスの作曲家パーセル
ブリテンが『青少年のための管弦楽入門』を作曲した時、どの程度成功するのか、まだ分からなかったはずです。しかし、忘れられていた自国イギリスのパーセルの主題を選びました。この曲の成功により、パーセルのキャッチーな主題も有名になり、パーセル自身の知名度も大きく増しました。バロック奏法全盛の現在、パーセルのオペラはヨーロッパ中のオペラ・ハウスで重宝されています。世にパーセルを広めた功績は大きいと思います。
バロック時代に活躍したイギリスの音楽家ヘンリー・パーセルの作曲した主題を使っています。今は、パーセルの古楽器演奏は人気がありますので、動画もあります。パーセルはバロック時代の作曲家の中でも響きの薄いシンプルな音楽を好んでいました。その後、イギリスからは大作曲家は出ず、エルガーが登場するまで長い冬の時代を迎えることになります。
とてもパーセルの主題とは思えない、ダイナミックでロマンティックな主題です。ブリテンも自国の作曲家とは言え、当時はまだバロックに関する知識はなかったでしょうから、仕方がないですね。
おすすめの名盤レビュー
それでは、ブリテン作曲青少年のための管弦楽入門の名盤をレビューしていきましょう。
バーンスタイン=ニューヨーク・フィル
バーンスタインとニューヨーク・フィルは『青少年のための管弦楽入門』を良く演奏しました。英語によるナレーションが入った演奏です。英語がスッと聞き取れる人はナレーションが入っていると色々な知識が得られると思います。
演奏もスタンダードで素晴らしいです。時代のせいか、主題提示はかなりダイナミックです。ナレーションは、変奏曲なので変奏の仕方を説明したり、楽器の説明をしたりしています。様々な楽器のソロが現れ、ダイナミックに変奏が展開していきます。最後はパーカッションで盛り上がります。バーンスタインは分かり易くダイナミックに演奏していて、ブリテンの音楽も現代音楽には聴こえず、親しみやすいものに聴こえてきます。
ラトル=バーミンガム市交響楽団
サイモン・ラトルはイギリス人で、ベルリンフィルの音楽監督になる前にブリテンの主な名曲はバーミンガム市交響楽団と録音しています。若いころの演奏ですが、内容も音質も素晴らしく、今でも貴重な録音です。
ラトルの『青少年のための管弦楽入門』は、バーンスタインや小澤征爾の録音からは少し時間が経っていることと、ラトルの知的な演奏スタイルもあって、大分違う雰囲気に仕上がっています。まず、主題提示が落ち着いていて、テンポが速めです。バーンスタイン盤はちょっと大げさかなと思っていたので、しっくりきます。変奏に入ってもクールさを失わない演奏で、ブリテンのオーケストレーションは最大限に活かしていますが、必要以上にダイナミックにはしません。
小澤征爾=シカゴ交響楽団
若き小澤征爾がシカゴ交響楽団を思い切り鳴らした名演です。シカゴ交響楽団はそんなに簡単に鳴らせるオケではなく、客演したもののシカゴ響の実力を出し切れなかった例は沢山あります。しかし、若き日の小澤征爾はシカゴ響と沢山の名演を残しています。ヤナーチェクのシンフォニエッタ、ストラヴィンスキーの春の祭典、その他、です。
そして、この『青少年のための管弦楽入門』も凄いスケールの演奏となっています。最初の主題提示から、ここまでスケールの大きな演奏はありません。そして、変奏も上手く処理していて、最後は盛り上がって終わっています。気合も凄いですが、気合だけではこういう演奏はできないはずです。
CD,MP3をさらに探す
楽譜・スコア
ブリテン作曲の青少年のための管弦楽入門の楽譜・スコアを挙げていきます。
ミニチュア・スコア
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。