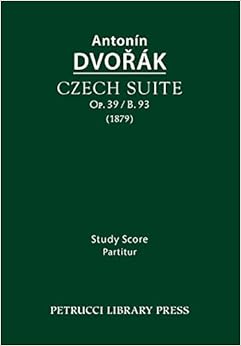アントニン・ドヴォルザーク (Antonin Dvorak,1841-1904)作曲の隠れた名曲である『チェコ組曲』ニ長調 Op.39(B.93) (Czech Suite D-Dur Op.39(B.93))について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。最後に楽譜・スコアも挙げてあります。
チェコ組曲はドヴォルザークの隠れた名曲で、リスナーからも実は人気があります。アマチュア・オーケストラでもよくコンサートの候補曲に上がります。でも、知名度が低いからか、あまり演奏されませんけれど。
以下にYouTubeを貼ってみましたが、お気に召しましたか?
解説
ドヴォルザークのチェコ組曲 ニ長調 Op.39(B.93)について解説します。
ドヴォルザークは1862年に新設された国民劇場のヴィオラ奏者になります。ここにチェコの国民楽派を代表するスメタナが1866年より指揮者として迎えられ、ドヴォルザークはスメタナの影響を大きく受け、民族主義的な音楽を作曲するようになります。
本曲は有名な『スラヴ舞曲集』に続き、1879年4月に作曲されました。初演は1879年5月に、ドヴォルザークもメンバーの一人であった国民劇場の管弦楽団により行われました。
曲の構成
チェコ組曲は以下の5曲で成り立っています。演奏時間は23分程度です。
第1曲:前奏曲(パストラール)
パストラールの名前が示すように、バグパイプを思わせる牧歌的な調べの音楽です。
第2曲:ポルカ
ポルカとしてはあまり活発ではなく、チェコの情緒的でメランコリックな音楽です。
第3曲:メヌエット(ソウセツカー)
メヌエットの一種と見做されていますが、ボヘミア地方の民族音楽でソウセツカーという舞曲です。
第4曲:ロマンス
フルートによる感傷的な夜想曲です。
第5曲:フィナーレ(フリアント)
ボヘミア民族舞曲のフリアントによる活発なリズムの終曲です。
おすすめの名盤レビュー
それでは、ドヴォルザーク作曲チェコ組曲 ニ長調 Op.39(B.93)の名盤をレビューしていきましょう。
ドラティ=デトロイト交響楽団
チェコ組曲と言えば、定番はこのドラティ=デトロイト響のCDです。デトロイト交響楽団の上手さと透明な響きも相まって、チェコの風を感じるような、さわやかさのある演奏です。またドラティの非常に丁寧な演奏が、この組曲の曲想に非常に合っていて、チェコ組曲の良さを上手く効かせてくれます。録音状態も非常に良いです。
また、曲目が全てドヴォルザークの知られざる名曲ばかりで、スラヴ舞曲や弦楽セレナーデも入っていません。メインはこの『チェコ組曲』という、潔いCDです。
ノイマン=チェコ・フィル (1971年)
ノイマン=チェコ・フィルの『チェコ組曲』は、民族的で濃厚な味を持つ超名演です。やはり地元だけのことはありボヘミアの自然を身近に感じています。自然はさわやかなだけではなく、曇ったり霧が出たりすることもある訳です。それに加えて、強い民族的な感情を加えると、随分濃厚になってきます。そこまで表現したことで感動的といえる位の名盤になっています。
またチェコフィルは、舞曲になると独特のリズムを刻んでいます。これはやはり地元のオケでないと出来ないでしょうね。
チェコ組曲の名演、というだけでなく、ノイマン=チェコフィルのドヴォルザーク演奏の中でも特に素晴らしい部類に入ると思います。
ヤクブ・フルシャとプラハ・フィルハーモニアの録音です。
CD,MP3をさらに探す
楽譜・スコア
ドヴォルザーク作曲のチェコ組曲 ニ長調 Op.39(B.93)の楽譜・スコアを挙げていきます。
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。

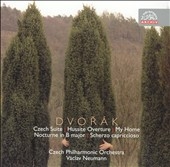
![ドヴォルザーク:チェコ組曲Op.39(B 93) 他 [Import] (CZECH SUITE / WALTZES & POLONAISE)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Emnk6DlGL._SL500_.jpg)