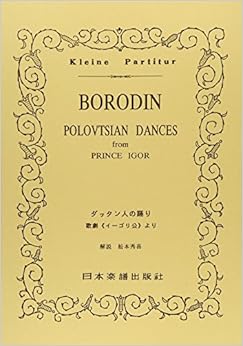アレクサンドル・ボロディン (Alexander Borodin, 1833-1887)作曲の『ダッタン人(韃靼人)の踊りと合唱』(ポロヴェツ人の踊り、Polovtsian Dances And Chorus)(歌劇『イーゴリ公』より)の解説と、おすすめの名盤をレビューし、スコアや楽譜の紹介をします。
解説
ボロディン作曲『ダッタン人の踊りと合唱』を解説します。
この曲はボロディン作曲の歌劇『イーゴリ公』の中の音楽です。第2幕の最後に演奏されます。
歌劇『イーゴリ公』はロシア版の蒙古襲来を描いた作品です。ロシアはモンゴルにほぼ完全に支配されてしまい、ロシアの大本である「ルーシ」はモンゴルに滅亡させられてしまいます。イーゴリ公はルーシの王です。
史実を見ると、ダッタン人(韃靼人)とは、モンゴル人のことを指します。中央アジアからシベリアまで広く分布していた騎馬民族です。タタール人とも呼ばれますし、タルタルソースの語源になったとも言われています。ロシアはもちろんのこと、東ヨーロッパは大きな影響を受けました。もう少しでヨーロッパを征服する、というところで、モンゴルの第2代王であるオゴデイ・ハーンが亡くなり、後継ぎ争いでヨーロッパから撤退しました。しかし、ロシアは完全に征服され、そうすると王の妃はモンゴル人となるようです。したがって、ロシアとモンゴルは実はかなり血のつながりが濃いのです。
ボロディン自身もモンゴル系の騎馬民族の血を引いていると言われています。そのため、この歌劇「イーゴリ公」はルーシの英雄を主人公としていますが、モンゴル人たちの勇猛で土俗的な戦士たちが、敵、というより、対等に描かれている非常にエキゾチックな歌劇でもあるのです。
そのエキゾチックな部分が良く描かれているのが、この『ダッタン人の踊りと合唱』です。イーゴリ公とその息子がモンゴルに捕らえられ、モンゴルの陣地に連れていかれます。そこで、モンゴルの敵将はイーゴリ公を懐柔しようと宴会を開きます。そのとき、踊られるのが『ダッタン人の踊りと合唱』です。
これはダッタン人の踊りだけではなく、ダッタン人が捕虜にした奴隷やカスピ海の美女たちも登場して踊ります。そして、奴隷たちが祖国を懐かしんで歌を歌います。最後は、大団円で全員で激しく踊りを踊ってそのまま幕となります。歌劇でみるととても絵になる場面です。
この歌劇は1869年に着手されましたが、ボロディンの急逝により完成できませんでした。その意を継いで、リムスキー=コルサコフがオーケストレーションを行って完成させています。
また、現在上演の際はバレエ団が入り、モンゴル風の踊りを披露します。この振付はバレエリュスで「火の鳥」「ペトルーシュカ」の振付をしたフォーキンによるものです。バレエ作品として単独上演も行われます。
ところで、歌劇『イーゴリ公』には、いくつか単独で演奏される曲があります。以下の曲はゲルギエフのDVDでの曲の位置です。
・イーゴリ公序曲
歌劇では序曲として最初に演奏されます。
・ダッタン人の娘たちの踊り
第1幕の3曲目に演奏されます。モンゴル人の女性たちが
くるくる回りながら、コケティッシュなダンスを踊ります。
・ダッタン人の踊り
第1幕の最後に演奏されます。一番盛り上がる個所ですね。
奴隷使いの指揮のもと、カスピ海の女性たちが妖艶に踊ります。
ダッタン人の踊りとなり、男性はダイナミックに粗野に踊ります。
女性は『ダッタン人の娘たちの踊り』に似た振付です。
・ダッタン人の行進
第3幕の前奏です。
他には、第1幕でイーゴリ公の息子と、敵将のコンチャック・ハーンの娘が恋仲になる流れの中で、デュエットがあり、これもなかなか名曲です。
おすすめの名盤レビュー
それでは、ボロディン作曲『ダッタン人の踊りと合唱』の名盤をレビューしていきましょう。
近年、歌劇『イーゴリ公』はゲルギエフ=マリインスキー劇場がDVDを出しており、これがかなり素晴らしいです。これを入手すれば、名場面とその音楽が全部入っているわけです。そこで映像も含めてレビューします。
ゲルギエフ=マリインスキー劇場(全曲)
ゲルギエフはいくつかのロシアのオペラを復刻しています。グリンカの歌劇『ルスランとリュドミラ』は非常に素晴らしい上演でした。
それに匹敵するのが歌劇『イーゴリ公』です。イーゴリ公はその前にハイティンク=コヴェントガーデンが100年に一度の上演、と銘打って復刻していますけれど。マリインスキー劇場は非常にクオリティの高い上演でゲルギエフの演奏も素晴らしいです。
ただ、マリインスキー劇場は舞台が小さめなので、そこだけコヴェントガーデンのほうが有利ですね。いずれもクオリティが高いですが、とりあえず入手しやすいゲルギエフ=マリインスキー劇場があれば十分だと思います。
『ダッタン人の踊りと合唱』は、第2幕の最後で、素晴らしい演奏です。ゲルギエフの気合いが伝わってくるようです。もちろんバレエ団もフォーキンの振付でキレのある踊りを披露しています。衣装なども中央アジアあたりの多くの民族の文化が入り乱れてとても華麗です。
演奏が進むにつれてゲルギエフの演奏も熱を帯びてきて、オーラすら感じる位、ダイナミックな演奏になっていきます。そして、大団円のあと、幕が閉まる様子まで見どころ満載です。
日本語字幕があったほうが良いので、それを選んでみました。英語字幕は輸入盤でもあったと思うので、英語に自信のある方はそれでもいいかも知れません。
この映画版イーゴリ公は面白いです。ちょっと古いでし、『ダッタン人の踊り』の途中に、イーゴリ公の息子とコンチャック・ハーンの娘の逢引のシーンが入っていたりして、かなり改竄されています。ただ凄く分かり易いです。
なぜなら、スタジオではなく、本当の草原でロケしているからです。ダッタン人のテントの様子などなるほど、と思います。キーロフ歌劇場は、ソヴィエト時代のマリインスキー劇場です。『ダッタン人の踊り』の演奏は、目茶苦茶、爆速でオケがついてこれておらず、演奏はボロボロです。
それでもこのDVDを薦めたいのは、ちゃんとフォーキンの振付で大草原でバレエを踊っているからです。
なにせ、外ですから、フォーキンのダッシュする振付も全力です。カスピ海の美女もいますし、モンゴル系のダンサーもいます。こんなにリアリティのある『イーゴリ公』は、金輪際ありえないと思います。
それに楽器も大きな太鼓をダッタン人が叩いていたり、と、どの位、考証されているのか分かりませんが、なかなかリアリティがあると思います。
そして、草原の民であるダッタン人の解放感。踊りが進むにつれてどんどん熱狂的になってきてとても迫力があります。どこにそんなにいるのか、踊りの上手さを見るとバレエダンサーだと思うのですが、明らかに黄色人種のバレリーナが本当の炎がバリバリ燃えている松明を手にコケティッシュなダンスを披露します。黄色人種の男たちもキレの良いダンスを披露しています。
筆者も実は最初演奏を聴いたときは「なにこれ!?」と思いましたが、ゲルギエフのクオリティの高いオペラ上演と並べてみると、色々理解できるし、面白いです。
ネーメ・ヤルヴィ=エーテボリ交響楽団
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニーは知る人ぞ知るレヴェルの高いオーケストラです。透明感があり、北欧のサウンドですけれど。
ロジェストヴェンスキーはこのオケの指揮者をしていたことがあり、ボロディンのツィクルスを録音しています。なんといっても、3曲なので1回の演奏会でツィクルスが出来てしまいます。
さて、『イーゴリ公』は、『ダッタン人の娘たちの踊り』から始まります。非常にリズミカルでコケティッシュです。ロシア的、というかモンゴル的な荒々しさはなく、アンセルメ盤に近いようにも思います。
次は『ダッタン人の踊り』です。合唱は入っていないようです。録音も良く響きも綺麗なので、ロジェストヴェンスキーが指揮していることを忘れてしまうくらいです。でも、エキゾチックな雰囲気は満点です。
テンポはゲルギエフに比べると少し遅めです。ただ、リズムはしっかりしていて、やはりバレエが得意な指揮者だなと思います。
太鼓が入ると一気にダイナミックな演奏になります。ダイナミックでエキゾチックです。北欧のオケらしく響きの透明さはダイナミックになっても失われません。
ロジェストヴェンスキーはただ荒々しい演奏をしている訳ではなく、踊りの特徴を活かしながら、エキゾチックさを忘れません。透明感のある中で普段の荒々しい演奏では聴こえてこないパートが良く聴こえます。
さすがベテラン指揮者という感じで、表現の上手さを感じます。普段とは異なるロイヤル・ストックホルム・フィルの特徴を上手く活かした演奏で、結構充実感があります。合唱があればもっと良かったですね。
アンセルメ=スイス・ロマンド管弦楽団
アンセルメは色彩感のあるロシア音楽も多く録音を残しています。ボロディンを世に広めたのもアンセルメかも知れません。
このディスクには『ダッタン人の娘たちの踊り』『ダッタン人の踊り』が連続して演奏されています。
1960年という古い録音にもかかわらず、音質は良好です。かなり強烈なリズムを刻んでいてロシア的な表現も上手いです。また、合唱も入っています。金管などはロシアのオケに比べると落ちますが、かなり頑張っています。
このアルバムは本曲を有名にしただけでなく、選曲が良く、他にも面白い曲が入っています。特にリャードフの交響詩『キキモラ』、グラズノフの交響詩『ステンカ・ラージン』は知名度は低いですが、隠れた名曲です。
イヴァン・フィッシャーとブダペスト祝祭管弦楽団の演奏です。つまりハンガリーのコンビなのですが、実はハンガリーはモンゴルに直接攻められています。ハンガリーを突破されれば、すぐにウィーンが危なくなり、次はフランス、という感じで、結構大事な戦いだったのです。ですが、モンゴルの大軍に苦しめられながらも、オゴデイ・ハーンの死によってモンゴル軍が撤退したので、ハンガリー人はむしろモンゴルに勝ったという風に考えているかも知れませんね。
この演奏は、結構テンポが速くて、パーカッションは迫力があるのですが、土俗的な雰囲気が少なく、スタイリッシュといってもいいくらいです。合唱は非常にきれいな響きを出しています。録音もなかなか良いです。
しかし何か物足りないですね。実はもう少し民族的な演奏を期待していたのですが、こんなに軽快な演奏だとは思っていなかったです。
CD,MP3をさらに探す
楽譜
ボロディン作曲のダッタン人の踊りと合唱の楽譜・スコアを挙げていきます。
ミニチュア・スコア
ボロディン:ポロヴェツ人の踊りと合唱(ダッタン人の踊り) (zen-on score)
レビュー数:3個
残り7点
No.90 ボロディン ダッタン人の踊り (Kleine Partitur)
レビュー数:6個
残り3点
![ボロディン:歌劇《イーゴリ公》 マリインスキー劇場版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51mqY65aMlL._SL500_.jpg)
![ボロディン:歌劇「イーゴリ公」映画版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/510S0XB3YFL._SL500_.jpg)