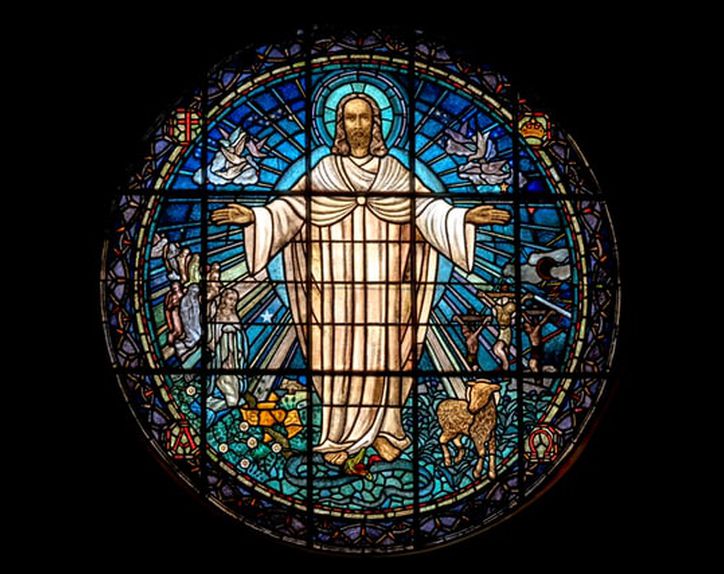オットリーノ・レスピーギ (Ottorino Respighi,1879-1936)作曲の組曲『鳥』 (“Gliuccelli”)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。ワンストップでスコアや楽譜までまとめています。第5曲「かっこう」はとても有名なメロディです。全体的に色彩的で独特の味わいがあり、とても楽しめる名曲です。
解説
レスピーギの『鳥』について解説します。
『鳥』は、1927年に作曲されました。17世紀のバロック時代の楽曲を引用し、作曲・編曲した管弦楽曲です。
初演は1927年6月、南米サンパウロの劇場にて、レスピーギ自身の指揮とシカゴ交響楽団の演奏により行われました。
第1曲:前奏曲
ストラヴィンスキーの『プルチネルラ』を思わせる新古典主義的な明るい音楽です。主部はガヴォットと思われます。
第2曲:鳩(はと)
第3曲:めんどり
バロック期にフランスで活躍したジャン=フィリップ・ラモーのクラウザン曲『めんどり』による音楽です。
第4曲:夜鶯(夜ウグイス, ナイチンゲール)
17世紀のヴァージナルのための楽曲(作曲者不明)による音楽です。
第5曲:かっこう
ベルナルド・パスキーニのピアノ曲『かっこうの鳴き声をもつトッカータ』による音楽です。親しみやすい色彩感のある有名なメロディと優れたオーケストレーションで始まる名曲です。
フルート×2(ピッコロ持ち替え)、オーボエ×1、クラリネット×2、ファゴット×2
ホルン×2、トランペット×2
チェレスタ、ハープ
弦五部
おすすめの名盤レビュー
それでは、レスピーギ作曲『鳥』の名盤をレビューしていきましょう。
シモーネ=ヴェネツィア合奏団
シモーネ率いるヴェネツィア合奏団は、比較的小編成でイタリア的な明るい音色が特徴です。バロック音楽を得意としていますが、このレスピーギの作品は新古典主義なので、相応しいレパートリーです。このレスピーギの管弦楽曲集でもレスピーギの曲にヴェネツィア合奏団の響きが良くあっています。そのためとてもリラックスして聴くことが出来ます。
第1曲「前奏曲」は溌溂とした演奏ですが、暖かみのある音色で味わい深さも同居しています。ヴァイオリンの独特のヴィブラートが暖かみがあって良いです。第2曲「鳩」は色彩感あふれる演奏です。オーボエのソロも葦笛といった風情で味わい深く聴けます。楽器が増えていき、クラやフルート、ヴァイオリン・ソロも出てきますが、上手く絡み合って情緒ある響きを醸し出しています。第3曲「めんどり」は快活でここでもオーボエやファゴットなどの木管が弦と上手く絡んでいます。
第4曲「夜鶯」は暖かみの中に穏やかさがあり、フルートは絶妙な演奏で夜のさわやかな雰囲気を表現しています。ホルンが出てきますが、とても素朴な音色です。チェレスタも心地よく響きます。第5曲「かっこう」はとても良いです。この演奏こそ、きっと色々なCMなどに使われていると思います。色彩感と言い、さわやかな雰囲気と言い、曲に相応しいものですね。ラストは段々と楽器が増えていき締めくくりますが、最後までいい味出しています。
レスピーギは20世紀に活躍していますが、新古典主義の中でも回顧主義的で、バロック期の作品に対する憧憬があるので、ヴェネツィア合奏団にとっては本当に合っていて名盤といえます。
ウルフ=セントポール室内管弦楽団
ヒュー・ウルフとセントポール室内管弦楽団の演奏です。組曲『鳥』の中では新しい録音ですが、オーケストレーションが優れた曲でもあるので、音質が良いのはとても効果的です。演奏もリズミカルで小気味良く、目の覚めるような瞬間が多い名演です。
オルフェウス室内管弦楽団
指揮者のいないアンサンブルであるオルフェウス室内管弦楽団の演奏です。組曲『鳥』のような新古典主義の音楽は、各奏者の自主的な演奏とアンサンブルがとても相応しいです。テンポも解釈も自然な演奏です。
前奏曲はリズミカルでバロック期の舞曲の雰囲気が良く出ています。第2曲「鳩」は、おだやかで少し憂鬱なヴァイオリン・ソロや木管のアンサンブルのクオリティが高いです。第3曲「めんどり」は、ユニークさを前面に出した演奏で楽しめます。第4曲「夜鶯」は、落ち着きの中にも小気味良さのある演奏です。第5曲「かっこう」のさわやかさは聴き物で、CMなどで聴いたイメージそのままです。その後も、この曲のオーケストレーションの良さを味わい深く聴かせてくれます。
ボーンマス・シンフォニエッタによる演奏です。ボーンマス・シンフォニエッタは、オルフェウス室内管ほどヴィルトゥオーゾなオケではありませんが、イギリスの室内管弦楽団の中でもレヴェルが高いオケです。シャンドス・レーベルらしい長めの残響で、オーケストレーションの良さが良く生かされた演奏です。自然でメリハリのある表現で、鳥の擬音が素晴らしく、聴いていてとても気分の良い演奏です。
前奏曲は自然で小気味良いリズムがあります。オルフェウス室内管のカチッとしたリズムも良いですが、より古典的な雰囲気を出していると思います。第2曲「はと」は、物憂げな雰囲気がとても良く出ており、味わい深さがあります。ヴァイオリン・ソロはヴィブラートが控えめで、とても上手い演奏です。第3曲「めんどり」は、シャープでメリハリがあります。バロック的な雰囲気の中で、原曲のラモーのユーモアにあふれた音楽を彷彿とさせます。第4曲「夜鶯」は、ひんやりとした響きで、夜の雰囲気が良く出ています。フルートの繊細なソロが素晴らしいです。途中からホルンやチェレスタが絡みますが、有機的なアンサンブルで雰囲気が良く、さわやかさがあります。
CD,MP3をさらに探す
楽譜・スコア
レスピーギ作曲の鳥の楽譜・スコアを挙げていきます。
スコア
電子スコア
タブレット端末等で閲覧する場合は、画面サイズや解像度の問題で読みにくい場合があります。購入前に「無料サンプル」でご確認ください。