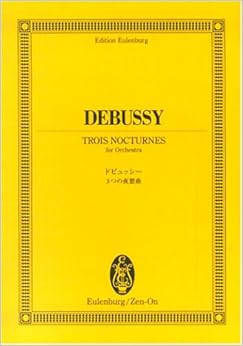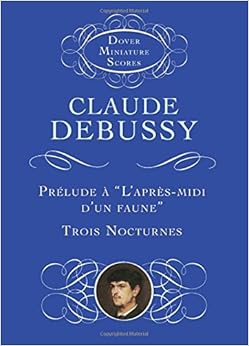クロード・ドビュッシー (Claude Debussy, 1862~1918) 作曲の『夜想曲』(Nocturnes)について、解説とおすすめの名盤レビューをしていきます。
『夜想曲』はドビュッシーの管弦楽曲の中でも特に人気のある曲の一つです。アマチュア・オーケストラではなかなか手が出ませんが、吹奏楽コンクール等ではよく演奏されますね。
解説
ドビュッシー作曲の『夜想曲』について解説します。
作曲の変遷
この曲は「たそがれの3つの情景」という名で1892年ごろに作曲が始められました。
その後、ヴァイオリン独奏をもつ「夜想曲集」として再度構想が練り直されました。当時のベルギーの名ヴァイオリニストであるウジェーヌ・イザイに依頼するつもりでした。しかし、理由は不明ですが、その構想は実りませんでした。
そしてまた構想を練り直し、今の形になりました。1899年に完成していますが、7年もの長い年月がかかりました。「雲」「祭り」「シレーヌ (海の精)」の3曲からなる管弦楽作品となっています。
ヴォカリーズの導入
特徴的なのは、第3曲「シレーヌ」にソプラノ8人、メゾ・ソプラノ8人からなるヴォカリーズ(無言歌, 母音唱法)のパートがあることです。この16人はオーケストラの楽器と同様に扱われ、幻想的で神秘的な雰囲気にするのに大きな効果をあげました。
この方法は、後世の作曲家も良く使うようになりました。例えばラヴェルの『ダフニスとクロエ』の第1部、ホルスト『惑星』の最終曲である『海王星』などですね。
他にもユニークなところがあり、よく考えてみると後世に大きな影響を与えた重要な音楽なのだ、と思います。
『夜想曲』の構成
『夜想曲』は3曲からなる管弦楽曲です。特に組曲という訳でもなく、『海』と違って交響詩でもありません。でも聴いてみればわかる通り、各曲の題は曖昧に表現する対象を示しています。
両端の「雲」「シレーヌ」は、霧がかかったような掴みどころのない曲になっています。そして中心にあるリズミカルな「祭り」が全曲を引き締めています。
第1曲「雲」
クラリネット、ファゴットでなどに弦がからみ、まさに雲に包まれたかのような音響空間となっています。
中間部からはフルートとハープが五音音階をベースとした主題を演奏し、少しエキゾチックな雰囲気を付け加えます。
第2曲「祭り」
シャープでリズミカルな弦の主題で始まります。シンプルではありますが、もやもやした感じがなく、リズミカルで楽しく聴ける曲です。
後半は一旦ピアノとなり、段々とクレッシェンドしていきます。トランペットを中心とした祭りの行列が近づいてきて、その後デクレッシェンドで、また遠ざかってくシーンを描いています。
こう見ると、ムソルグスキー『展覧会の絵』ラヴェル編曲版の「牛車」も同じ技法を使っているといえるかも知れません。ムソルグスキーのピアノ版は最初からフォルテシモで書かれていますが、ラヴェルが1922年にオーケストレーションした時にppから初めてクレッシェンドしてくようにし、牛車が近づいてきてまた離れていくことを表現しています。
第3曲「シレーヌ」
シレーヌは海の精で、人魚の姿で人を誘惑すると言われています。女声16人が入り、海の中の情景を描き出しています。海の波の感じや水面にゆれる輝きを表現し、神秘的で幻想的な空間を描いていきます。
おすすめの名盤レビュー
ドビュッシー『夜想曲』のおすすめの名盤をレビューしていきます。
ロト=レ・シエクル (2018年)
ロトとレ・シエクルの録音です。2018年と新しい録音で高音質で、演奏レヴェルも高いです。
「雲」は当時の響きをうまく生かしていて、ふんわりとした響きが印象的です。ソロも気怠さ(けだるさ)をうまく表現しています。「祭り」はとてもフレッシュに始まり、速めのテンポでリズミカルに演奏されていきます。当時のサウンドは低音が少し弱めで、なるほどこんな響きになるのか、と目から鱗(うろこ)です。後半はかなりダイナミックに盛り上がります。「シレーヌ」は暖かみのある響きで、他の演奏のクールな響きとは大分違います。こういう音色が逆に人魚らしい妖艶さを表現するのに相応しいと思います。ヴィブラートが少なく、個々のパッセージをしっかり演奏しきっていて、ふわっとした柔らかい響きの中にも見通しが良いです。ソロ、特にバスーンがとても妖艶に響き、フランス音楽の神髄を感じさせます。
ノンヴィブラート奏法ですが、それでもクールになりすぎることはなく、却ってふわっとした暖かみのある響きになるのは新鮮な発見ですね。初演当時はガット弦だと
デュトワ=モントリオール交響楽団
デュトワとモントリオール交響楽団の高音質で色彩感あふれる演奏です。このコンビらしい透明感の高い響きとまさに王道と呼べる解釈で、この曲のスタンダードといえる名盤です。
「雲」は上手く弦楽器の曖昧さを出していて、その上に木管のソロが乗っています。アンセルメ盤が古くて音質の問題があるなら、デュトワ盤はその後継に相応しいと思います。
「祭り」もリズミカルで良い演奏です。ピアニシモからクレッシェンドしていく所も、曖昧さのある響きから、輪郭が見えてくる所は面白いですね。「シレーヌ」は透き通った音色で、海のイメージにふさわしい演奏です。ホルンなどの管楽器のレヴェルの高さも特筆です。ただ「シレーヌ」は人を惑わす人魚だから、もう少し毒があってもいいような気もします。
デュトワ盤は洗練されたフランス風の演奏であることは間違いなく、演奏のクオリティの高い名盤です。
ハイティンク=ロイヤル・コンセルトヘボウ管
ハイティンクとロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の録音です。ハイティンクは明晰な指揮で、コンセルトヘボウ管自身が持っている透明感と色彩感を存分に引き出しています。とても響きが美しく、心地よい名演です。アナログ録音ですが、分離が良く透明感の高い音質です。
「雲」は少しひんやりとした手触りで、もやもやした響きではなく透明感があり、管楽器のレヴェルも高いです。ハイティンクは絶妙なコントロールで、フレッシュで粒の立った表現を聴かせてくれます。「祭り」は速いテンポでスリリングかつダイナミックさもあり、気分爽快です。後半もリズミカルに盛り上がり、弦も思い切り弾いていますが、ダイナミックな中にもフレッシュさがありますね。
「シレーヌ」は女声合唱が繊細で、ホルンを始め管楽器の上手さが際立っています。ハイティンクは繊細でありつつも、絶妙な手綱さばきで遅いテンポの部分でもとてもフレッシュに聴かせてくれます。スコアの読みも深く、アンサンブルの絡み合いがとても繊細で素晴らしいです。
ロトやデュトワとはまた違うフランスらしさとドビュッシーの管弦楽法の見事さを高いレヴェルで味わえます。ハイティンクの良さが際立った名盤です。
アンセルメ=スイス・ロマンド管弦楽団
アンセルメとスイス・ロマンド管の録音です。今となっては音質面でハンデを抱えるアンセルメ盤ですが、この『夜想曲』は素晴らしい名盤です。何しろ1957年録音ですから、下手をするとモノラルでもおかしくない時代です。
アンセルメ盤の良い所は、「雲」「シレーヌ」の雰囲気づくりと「祭り」の絶妙なリズムです。アンセルメは何の気どりも演出もなく、インテンポで演奏しています。ドビュッシーの名盤と言えばマルティノン盤のほうが良いことが多いのですが、『夜想曲』はアンセルメの凄さを感じますね。
「雲」の曖昧模糊とした雰囲気、「祭り」のしっかりしたリズム、ピアニシモからのクレッシェンド、「シレーヌ」の神秘的な雰囲気、いずれも絶妙です。「雲」の後半の5音音階のメロディが入る部分のテンポはかなり絶妙です。
もっとも「シレーヌ」の女声は今聴くと少しドライかもしれません。
『夜想曲』を吹奏楽などで演奏する人や詳しく知りたい人には、是非一度聴いてほしい名盤です。
マゼール=ウィーン・フィル
マゼール=ウィーン・フィルの録音です。最初のフレーズから素晴らしい曖昧な響きを紡ぎだしています。でも、実際はウィーン・フィルは普通に演奏しているように聴こえますし、デュトワ盤のように色彩的に色々な音の響きが残っているわけでもないです。つまり、ウィーン・フィルは『夜想曲』に向いている響きをもったオケだということですね。
マゼールの表現力なのか、ウィーン・フィルの表現力なのか分かりませんので、相乗効果ということにしておくとして、「雲」はあえて曖昧に演奏しているわけでもないのに、曖昧(あいまい)で霧がかかったような雰囲気が素晴らしいです。ウィーンフィルのセンスなのか、官能的な部分があれば、すぐそれに反応して、官能的に演奏してきます。さすが、としか言いようがありません。「祭り」はマゼールがかなり速いテンポで演奏させています。ここでかなり引き締まっているので、バランスも良くなります。「シレーヌ」は、本当にヴォキャブラリー豊富でウィーン・フィルの実力を見せつけられた感じです。女声合唱は低い音域では意外に太い声で歌っています。ヴォカリーズですが、いろいろな母音を使っています。深い海の中をイメージしたり、波打ち際をイメージしたりと、物凄い沢山の内容が詰まっています。これまで、いかにぼーっと聴いていたか反省させられますね。
この演奏は一つの『夜想曲』の本質が表れていますね。アンセルメ盤と十分タメをはれる演奏です。
ブレーズ=クリーヴランド管弦楽団
ブレーズとクリーヴランド交響楽団の新盤です。1993年の録音で音質が良いです。ブレーズの新盤の中でも「夜想曲」は素晴らしい演奏です。
「雲」から非常に高音質で色彩的です。少しだけ靄(もや)がかかったような雰囲気を出していますが、細かいところまでしっかり聴こえますし、クリーヴランド管弦楽団の演奏のクオリティの高さが良く分かります。
「祭り」は速めのテンポでリズミカルな演奏ですがシャープさは少なく、少し半透明なイメージで白昼夢のようです。途中pになる所も少し神々しさを感じるようなイメージです。これはギリシアの神々の「祭り」ですね。「シレーヌ」は色彩的で独特な雰囲気です。ヴォカリーズも非常にハイレヴェルです。弦の出だしなどシャープにならないように少し丸くしています。高音質も相まって、印象派の絵画のような暖かみと、はっきりしない輪郭線を上手く描き出しています。
他の演奏ではこんなに印象派らしいクオリティの高い演奏は聴けないと思います。
アバド=ベルリン・フィル
アバドはイタリア人ですがドビュッシー好きで、よくドビュッシーを取り上げますし、緻密で素晴らしい演奏をしてくれます。この『夜想曲』の特徴は、神秘的ながら、あまりモヤモヤしていないことでしょうか。フランスのオケの弦楽器は弓の返しのタイミングをばらしたりして、あえてモヤモヤしたような滑らかな音を出すのですが、ベルリン・フィルは普通にシャープに弾いています。なので、フレーズの発音自体は曖昧ではありません。まるで音と音の間の透明な空間が聴こえる様です。
録音会場のせいかセッティングのせいか、響きがとても良いので、その空いた隙間を非常に上手く埋めてくれます。
アバドのドビュッシーの特徴を理解したいなら、交響詩『海』の第2楽章を聴くとすぐにわかると思います。各パートがとても正確に演奏しているのです。それも効果的なのですが、そうすると絵画の印象派に影響を与えた画家ターナーみたいな曖昧さとは違う世界になってしまいます。

でも、アバドはあえてフランス音楽らしい性質を前面に押し出す代わりに、楽譜を読みこんで再構築しているように聴こえます。それで、フランス風演奏では聴こえなかった要素が聴こえたり、今までとは違った音響体験ができるので、すごい演奏だなと思います。
クリヴィヌ=ルクセンブルグ・フィル
フルネ=チェコ・フィル (1963年)
フルネとチェコフィルがスプラフォンに録音した演奏です。チェコ・フィルがドビュッシー?という気もしますが、これがとても深みのある名演です。音質は良いとは言えませんが、アンチェル時代のチェコ・フィルらしい情報量の多さです。
「雲」はこのページにある演奏の中でもトップを争う深みのある演奏です。弦の深みのある演奏の中で、チェコ・フィルの管楽器の表情豊かなソロを堪能できます。「祭り」は速めのテンポで盛り上がります。後半はダイナミックに盛り上がります。「シレーヌ」も奥深さを感じる演奏です。合唱はスケールが大きく、チェコ・フィルも重厚さのある響きで、フルネの彫りの深い表現がとても素晴らしく、聴きごたえがあります。後半はさらにテンポを落とし、じっくりと深みのある演奏を聴かせてくれます。
チェコ・フィルの弦は思い切り厚みのあるアンサンブルを繰り広げていますが、フルネの指揮は端正で職人的であり、しっかりフランスの音楽になっています。この曲が好きな人は一度聴いてみてほしい名演です。
サロネンはロサンゼルス・フィルをしなやかにドライヴしています。
「雲」では、特にフランス風の演奏という訳ではなく、ロサンゼルスフィルの管楽器の響きを活かして、繊細な音楽づくりをしています。ただ、もう少し微妙な色彩の変化などを活かさないと、ちょっと平坦になってしまう所もありますね。「祭り」は速めのテンポですっきり演奏しています。今回取り上げた名盤の中でも特に素晴らしいです。この曲でこれだけ色々な表現が出来るのだなぁと感心しました。「シレーヌ」も繊細でしなやかな演奏です。細かいアーティキュレーションには細心の注意が払われています。こんなパッセージがあったのか、と新しい発見があります。
サロネンとロス・フィルらしい真摯な姿勢が感じられ、とてもクオリティの高い演奏です。
バレンボイム=パリ管弦楽団
本場フランスのパリ管弦楽団の演奏です。といっても、バレンボイムやドイツ系指揮者が続いたおかげで、オケのレヴェルは上がったもののフランスのエスプリがかなり失われてしまったと言われていますね。
ワーグナーを得意とするバレンボイムは、どちらかといえばドイツ風で、「雲」は落ち着いたテンポで演奏されています。別に悪くはないのですが、印象派ではなくロマン派の音楽に聴こえます。ある意味新鮮で味わい深く聴ける演奏ですが、幻想交響曲の第3楽章を思い出してしまいました。
「祭り」はなかなかです。テンポ取りは絶妙で金管がどこかラテン系です。でも、このコンビの特徴が良く出ているかも知れません。パリ管はまだラテン系のオケで、バレンボイムはそこからシカゴ響のようなサウンドを引き出そうとしているように思えます。なんとなくパリ管に戸惑いがある感じですね。
「シレーヌ」は普通のテンポで始まります。でも、合唱もオケももう少し早いテンポで演奏したい雰囲気で、前のめりになってしまいます。それでも上手く行っている所もあって、バレンボイムらしい雰囲気が出ています。逆に所々でフランス風の響きも聴こえて、ちぐはぐですが面白いです。
CD,MP3等をさらに探す
楽譜
ドビュッシー『夜想曲』の譜面を上げていきます。
ミニチュア・スコア
オイレンブルクスコア ドビュッシー 3つの夜想曲 (オイレンブルク・スコア)
解説:ミヒャエル・シュテーゲマン
レビュー数:1個
![ドビュッシー : 牧神の午後への前奏曲、夜想曲 / フランソワ=グザヴィエ・ロト | レ・シエクル (Debussy: Prelude a l'apres –midi d'un faune, Nocturnes / Francois-Xavier Roth, Les Siecles) [CD+Bonus DVD] [Import] [日本語帯・解説付]](https://m.media-amazon.com/images/I/61kBVtjfXOL._SL500_.jpg)
![ドビュッシー : 牧神の午後への前奏曲、夜想曲 / フランソワ=グザヴィエ・ロト | レ・シエクル (Debussy: Prelude a l'apres –midi d'un faune, Nocturnes / Francois-Xavier Roth, Les Siecles) [CD+Bonus DVD] [Import] [日本語帯・解説付]](/wp-content/uploads/ToAmazon.png)








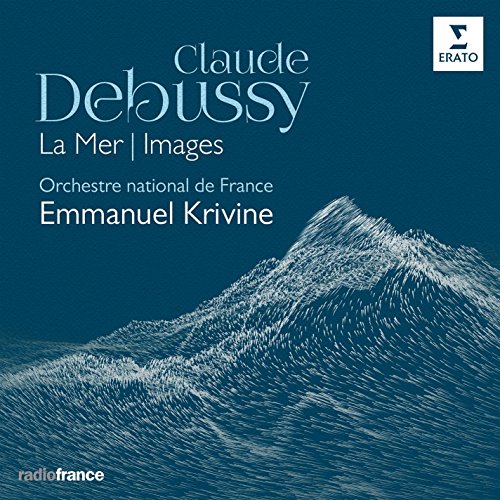
![プラハのジャン・フルネ (Jean Fournet in Prague) (3CD) [輸入盤]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tE5hLGu2L._SL500_.jpg)